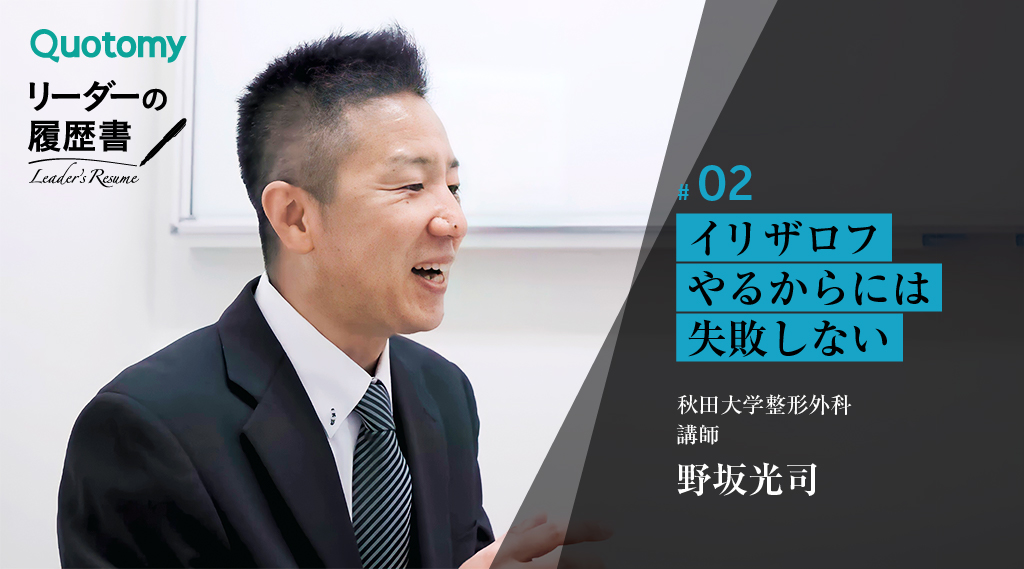
【#02 野坂光司先生】イリザロフやるからには失敗しない
本編に登場する論文
Effectiveness of circular external fixator in periprosthetic fractures around the knee
Koji Nozaka, Naohisa Miyakoshi, Michio Hongo, Yuji Kasukawa, Hidetomo Saito, Hiroaki Kijima, Hiroyuki Tsuchie, Motoki Mita, Yoichi Shimada
BMC Musculoskelet Disord. 2020 May 21;21(1):317. doi: 10.1186/s12891-020-03352-9.
── 突然、島田先生にイリザロフをやるよう言われたのですね。
実は過去の島田洋一先生のインタビュー内で若い女性のピロン骨折の症例とイリザロフ治療の話題が出ていました。
島田先生に声をかけられてから全てが始まりました。
我々もその患者さんのお話をお聞きしていて、ピロン骨折の女性が内固定手術で感染してしまい、感染制御できずにfailureが重なり切断に至った症例だったそうです。
それがずっと島田教授の心に残っていて、「秋田県でこのような症例を生んではいけない。
自分が教授になったらピロン骨折は百パーセント治せるような臨床グループを作る」というのが目標だったんですね。
── 当時、大学外の関連病院にいる野坂先生に話がきたのは何故でしょうか?
これはよく分からないです。
「イリザロフをやれ、イリザロフを学びに留学に行け」と言われただけです。
もう「はい」って言うしかないという感じで。
ピロン骨折の女性患者の話も教授の想いも、留学から帰ってきた後で伺いました。
今は、イリザロフをやれって言われて本当に良かったなと心から思っています。
── イリザロフを学ぶために国内留学をされているのですね。
島田先生は2007年に教授就任されて、2008年に私にイリザロフをやりなさいとおっしゃった。
その後、獨協医科大学埼玉医療センターの大関覚教授のところに国内留学させていただきました。
ところが、留学後に配属になった関連病院では、イリザロフは一個もありませんでした。
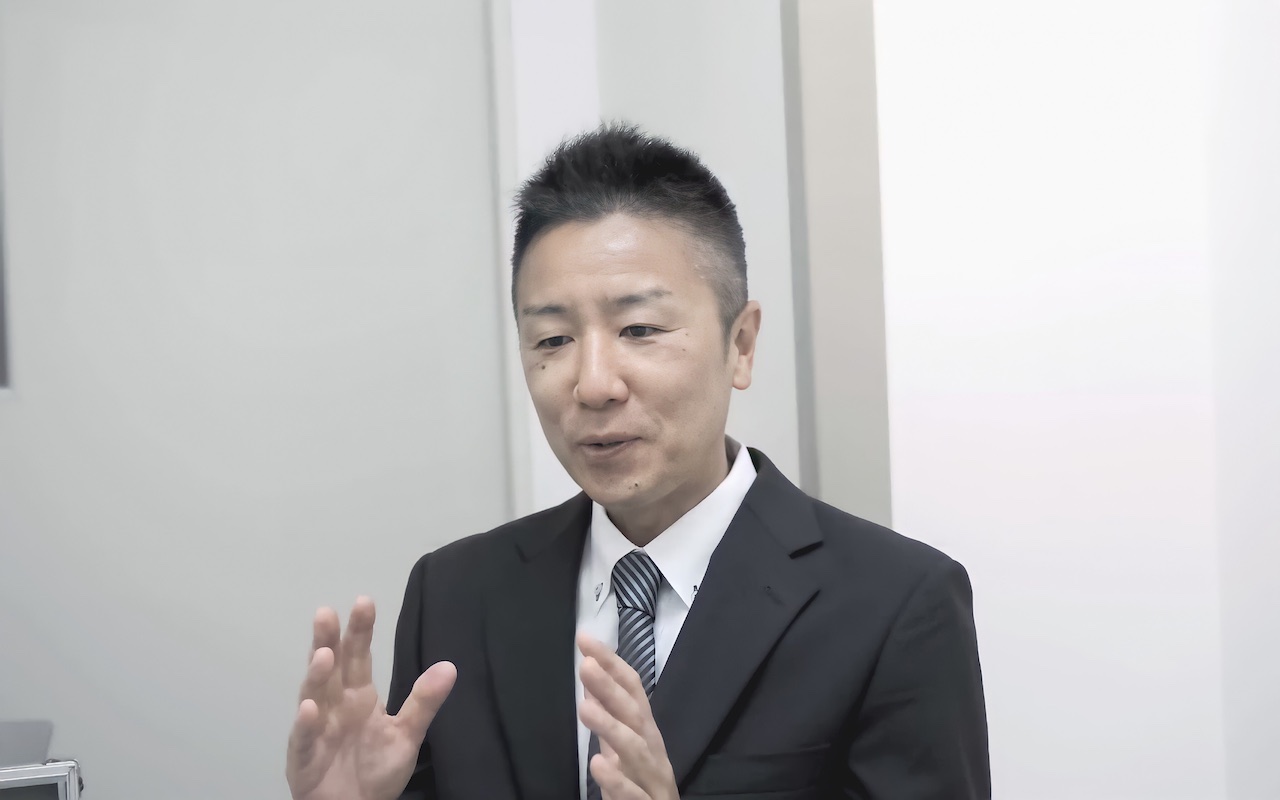
島田教授に「イリザロフがありません。どうしましょうか?」って言ったら、院長に直談判するからセッティングしろって言われて。。。
院長室に院長と島田教授と当時の部長と私と四人で座って、「うちの大事な医局員、これからもこの病院にお世話になるから、院長何とか買ってくれませんか?」という島田教授のお願いがあり、院長が「整形外科が困っているなら買いましょう」と言って、イリザロフを院長決済で買ってくれました、笑。
そこからは、もう死ぬ程イリザロフをやりましたね。
── どんな症例が多い病院だったのですか?
外傷はたくさん来ましたし、ややこしい難治性骨折や足部疾患も手つかずで多くおり、イリザロフを使って治したいと思っていました。
あとは秋田県が本当に高齢化社会なので、高齢者の骨脆弱性骨折患者さんの在院日数が長いという課題がありました。
もうずっと入院していてベッド稼働できませんし、患者さんも家に帰る頃には車椅子生活になっている。
そういう悪循環をずっと目の当たりにしていたのでイリザロフで解決したいと思っていました。
留学していた獨協医科大学埼玉医療センターでは、骨脆弱性骨折でもイリザロフを装着してすぐに荷重させているのを見ました。
また、感染性偽関節で骨が無くなっているような方にもイリザロフをつけて歩かせながらボーントランスポートをしていました。
特に、外来にイリザロフをつけた患者さんが通っている光景が、私の中でもの凄い驚きでした。
高齢者骨折が山ほどいる秋田県にも取り入れて、イリザロフをして術後早期荷重、そして早期社会復帰してもらおうと思ったのです。
── 高齢者の術後早期荷重に繋がるパラダイムシフトですね。
秋田県で取り入れる上で、大変だったことはありますか?
大変なことだらけでした。
イリザロフはやっぱりややこしい。
その管理も特殊なものがあって、最初の頃は病院スタッフもイリザロフ手術をたくさんやることに反対でしたし、患者さんも「こんなの着けて家に帰れない」とおっしゃる。
それが徐々に島田教授のリーダーシップの下、多くのスタッフの協力があってイリザロフチームが秋田県で上手く回るようになりました。
私が戻ってきた後にも留学に継続的に行っていて、イリザロフチームに医師が10名と増えました。
看護師さんたちもケアセミナーというイリザロフの勉強会を定期的にやる。
イリザロフをつけて歩いて家に帰ってもらうんだと、リハビリが専門でもある島田教授からリハビリスタッフにも檄がとぶ。
退院支援も秋田県全域で頑張ってやってくれています。
── 素晴らしいですね!
イリザロフやるぞ!って言っても一人ではなかなか難しいですよね。
関連病院で4年間、がむしゃらにイリザロフをやっていて、島田教授にそろそろ大学に戻ってこいと言われて2012年に戻りました。
本格的には大学にイリザロフはまだ導入されていなかったのですが、島田教授は2012年から大学を秋田県イリザロフセンターのような形にしてくれました。
大学だと遠慮なく秋田県全域、そして全国からも患者さんを紹介いただくことができます。
最初は正直なところ、もう少し外で一般外傷や普通の整形外科を続けたいなって気持ちはありましたが、島田教授から、大学で若手を育てながら働くことも一つの大事な仕事なんだ、と熱いメッセージを頂き、すぐに納得できました。
貴重な経験をさせていただき、もう本当に感謝しています。
── 秋田大学の外傷症例はほとんどイリザロフで治療していたのですか?
もちろん全てではないですが、かなり適応が広いと思います。
当時、私が国内で学会発表したりすると「イリザロフのオーバーインディケーションなんじゃないか」って言われ方をしていました。
納得いかない言われ方もありましたけど、なぜ観血的整復内固定術でも治せるものをあえてそんなに面倒くさいイリザロフを使うのか、というご意見は理解できます。
今はもう国内で学会発表してもそんなに攻撃されることはなくなりましたが、2010年頃の骨折治療学会や日本整形外科学会とかで発表すると「それはやりすぎだろう」というような御意見がありました。
その分、絶対失敗はしないように100パーセントの準備をして、「もし失敗しても人生背負って手術します」というぐらいの覚悟で、イリザロフチームみんなでやろうって話しています。
イリザロフをやるからには失敗しない。

── 2014年に留学されていて、Baylor University Medical Center, Foot and Ankle Section, Texas Scottish Rite Hospitalとなんですけど
どういった経緯で留学先が決まったのでしょうか?
大学に戻ってきたら留学の機会があると言われていて、幾つか候補先がありました。
ただ、島田教授は基礎研究の留学ではなくて、手術や臨床技術を学べる留学先を探しなさいと言われたんですね。
けれども、その頃のアメリカでは手洗いも手術に入るのもできないような状態でした。
基礎なら来てもいいけれども臨床留学は取っていませんという返事がほとんどでした。
そこで留学時代に大変お世話になった大関覚教授に相談させていただいたところ、Baylor University に親友がいる、と。
そのBrodsky教授という方が、毎回は手術に入れられないかもしれないけれどもSatoruの可愛い弟子ならば迎えてあげるよ、と仰っていただき、留学が決まりました。
ダラスの街はわりとアジアにも優しかった印象があります。
手術室で「only watching」っていつも言われて見学していました。
ところ、ある日のカンファレンスをきっかけに好転したんです。
自分の症例をプレゼンテーションする機会が何回かあったのですが、糖尿病性末梢神経障害に伴うシャルコー関節で破壊性足関節症になってしまった患者さんをイリザロフで治した症例をプレゼンテーションした時に、Brodsky教授はじめスタッフ陣が「Great!!」と凄く驚いて言ってくれました。
そこから、手洗いさせて頂けるようになりました。
── 厳しいアメリカなのに凄いですね!
そうなんです。
そこからはもうずっと手洗いさせてもらえて、筋鈎引きだったのですけど、少し腱移行の縫合をさせてもらったり徐々に任されるようになってきました。
大関教授とBrodsky教授にも感謝しかないです。
── 留学先はイリザロフが盛んな施設だったのですか?
Brodsky教授もイリザロフを使われる方でした。
実は、Baylor Universityから5kmくらい離れたところにあるTexas Scottish Rite Hospitalという小児病院があって、そこで物凄くイリザロフを多くやっていました。
留学前に、日本のイリザロフセミナーに、Samchukov先生というイリザロフでご高名な先生が講師としていらした際に知り合いになっていたので、そこに週に1度、手術見学に行かせてもらえるようになりました。
ですから、リングのイリザロフの勉強はTexas Scottish Rite Hospitalで、足の外科の基礎はBaylor University Medical CenterでBrodsky教授から学びました。
とても留学が充実していて帰国したくなかったくらいですが、秋田大学別グループの若い先生が留学するタイミングもあって、ここで学んだことを日本に還元しようという思いで帰りました。
── 凄い良い経験をされていますね。
難治症例に対しての治療経験があるんだってプレゼンテーションをしたのが良かったのですね。
そうかもしれないですね。
その後も何回か、「難治症例に対しての自慢の治療経験はないか?」みたいなフリがきて、私も得意気に発表すると「おー、いいじゃないか、いいじゃないか」という風な感じで皆と打ち解けることができるようになったのです。
Brodsky教授から「ソレはもっとこういう方法があったんじゃないか」というようなアドバイスも頂いて、なるほど、と思うことも多々ありました。
実は、留学前に島田教授から、日本での症例は何かあったらすぐプレゼンテーションできるように準備しておけ、と言われていたのです。
スライドを英語で作って持って行っていました。
会話のネタも何もないところでディスカッションするのは英語力に自信がないと難しいのですが、一つの症例に対してのディスカッションだと割とお互い聞き取りやすいし言いやすい、というメリットはありました。
── 今後に留学する先生にとっても役に立ちそうなアドバイスですね。

── 今回ご紹介いただきました論文は高齢者のTKA周囲骨折へのイリザロフ手術についてでした。
高齢者のTKA周囲骨折は、上手にプレートで内固定をできる先生でも、やっぱり難しいケースだと思うんですね
プレートをダブルでしっかり固定したけれども骨粗鬆症がひどくて全く固定できていない症例や、TKAのインプラントの中で骨折しているのでrevisionするしかないけれども耐術能がそんなに備わっていないので大きな手術ができない症例、、、そのような方々をご紹介いただくことがあります。
イリザロフであれば皮膚切開を置かない小さい侵襲で整復固定できる。「死にそうな患者さんに安全な手術をやってるんだ」ってよく島田教授はおっしゃってました。
皮膚外に露出した、あまり清潔じゃないワイヤーをインプラントの傍に刺すなんて、人工関節をよくやっている先生からは「とんでもない」って批判されることもありました。
でもギプスを巻いて寝たきりにするか、命がけで全身麻酔下にrevisionするか?
でも我々ならブロック麻酔だけで、手術時間1時間ぐらいでイリザロフで固定して、すぐに荷重して立ってもらいます。
私はもう、治療に前向きなご高齢の方々に「イリザロフを付けて貰っている」って思っているんですが、患者さんが生きる意欲とか頑張る意欲があるから辛い三か月の装着期間に耐えてくれます。頭はしっかりしていて、歩きたいのにTKAが折れちゃって歩けなくなっちゃった人って少なくないので、そういう人たちを、歩行能力を落とさずに救いたいと思っています。
── 珍しいケースシリーズなのでしょうか?
イリザロフをTKA周囲骨折に使用したケースレポートは結構あったんですよ。
まとまったケースシリーズは全然なくて。イリザロフの会ではTKA周囲骨折は超骨粗鬆症であればグッドインディケーションというのはイリザロフの研究会の中では常識。
ただ英文を誰も出しておらず、僕も批判されてばかりでしたので、みんなの風当たりも強くなくなるかなということで書きました。
── なるほど
イリザロフに関して一番先行している国はどこですか?
他の国で
ロシアですね。
イタリアもわりと盛んです。
しかし、TKA周囲骨折内固定の失敗症例に対してイリザロフを入れて上手く行ったというケースレポートがほとんどです。
最初から耐術能の低い高齢者にイリザロフをやったケースレポートはなかったですね。
── 専門的なグループの中ではイリザロフの良い適応と知られていた適応症例を世に認知してもらった論文ですね。
#03に続く
こちらの記事は2021年9月にQuotomyで掲載したものの転載です。