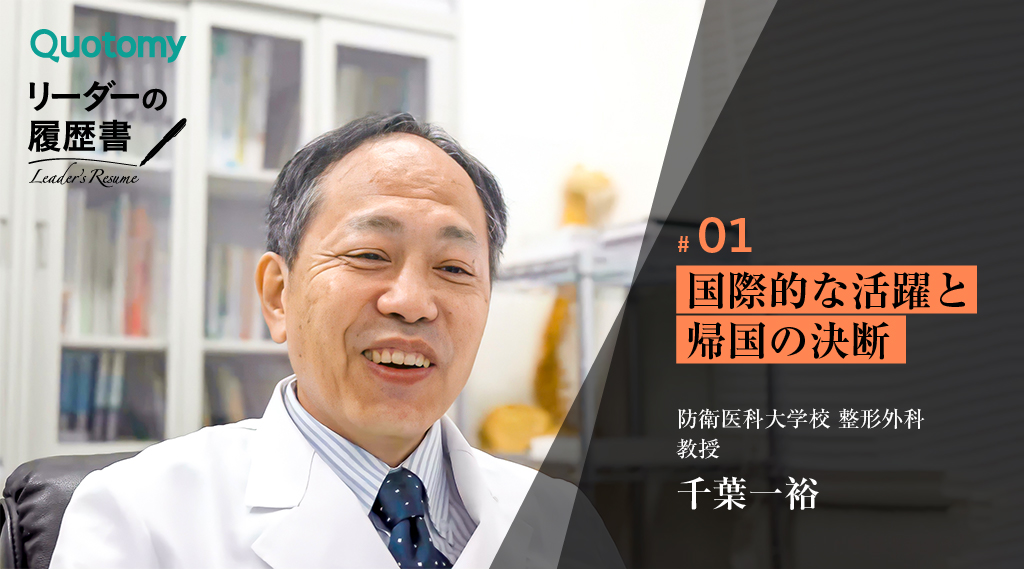
【#01 千葉一裕先生】国際的な活躍と帰国の決断
本編に登場する論文
Anterior screw fixation for odontoid fracture: clinical results in 45 cases
K Chiba, Y Fujimura, Y Toyama, T Takahata, T Nakanishi, K Hirabayashi
Eur Spine J. 1993 Aug;2(2):76-81. doi: 10.1007/BF00302707.
Metabolism of the extracellular matrix formed by intervertebral disc cells cultured in alginate
K Chiba, G B Andersson, K Masuda, E J Thonar
Spine (Phila Pa 1976). 1997 Dec 15;22(24):2885-93. doi: 10.1097/00007632-199712150-00011.
── よろしくお願いします。
まずは先生が整形外科医を志した理由から教えてください。
お恥ずかしいですけど、学生時代はあまり勉強好きじゃなくて、、、6年間ずっとスキー部だったので、冬はずっとスキー場に行って合宿や試合、夏休みも合宿という生活でした。
スキー場から夜行バスに乗って学校へ行って、試験を受けて、またその夜にスキー場に帰るような生活をしていました。
そんな学生でしてたので、たくさん勉強しなければならない内科系はとても無理だと感じていて、漠然と外科系がいいなと思っていたのです。
ただ一般外科は命に関わるし大変そう、あんまりマイナーな科も嫌だなって、、、色々こう消去していったら、整形外科がなんとなく残った。
それで整形外科医局に見学へ行ったら、医局長の先生が囲碁を打ちながら「楽しいよ」って言うので整形外科に決めました。
── 医局長が魅力的な先生というのも入局の決め手になりますよね。
私が入局した時の医局長は竹田毅先生という名物医局長で、あまり人に恨まれない人柄の良い先生でした。
慶應整形外科の医局長って割とそういう人が多くて、医局長に言われたら「まあしょうがないか」っていう雰囲気にさせられますね。
そもそも当時は医局の命令に逆らう人はいなくて、「〇〇病院に行け」って言われたら「はい」という返事をしますし、断るような文化はなかったですね。
── 入局後はどのような研修をされたのでしょうか?
卒業して10年間くらいは10箇所くらい関連病院をローテートしたと思います。
最初の年は5月に入局し、大学で2ヶ月は整形外科、その後の4ヶ月は麻酔科にローテートして、そのまま外病院に出ました。
整形外科医が3人の病院に派遣され、いきなり外来や手術の助手をやることになりました、、、、そこからは病院異動はほとんど一年ごとでしたね。
── いつごろに整形外科の専門領域を決められるのですか?
4-5年目くらいですかね。
私の場合、入局した時のオーベンの先生が脊椎班の斉藤正史先生でした。
手術も上手で何か格好良くて、「お前、脊椎向きだな」とか言ってくれて。
当時の慶應整形外科では、手の外科がエリート集団でした。
上下関係もしっかりしている感じで統制がとれていたのですが、ちょっと自分には向いてないなと。
一方で脊椎班は、平林洌先生という偉大なトップがいらっしゃったのですが、下にも藤村祥一先生、鈴木信正先生、戸山芳昭先生、持田譲治先生とかビッグネームがいて、上に物怖じせず意見を出す積極的な姿勢が格好良いなと思った記憶があります。
最終的には二つめの出張病院でオーベンだった戸山先生に誘って頂き、脊椎班に決めました。
── 今回ご紹介いただく論文は、歯突起骨折の手術治療についての論文です。
いくつかの病院をローテートした後に大学へ戻った時のお仕事でしょうか。
大学に戻ってチーフレジデントをやっていた頃、臨床テーマを貰って学会発表をするようになりました。
この論文は、平林先生にアテネでのCervical Spine Research Society European sectionに連れて行っていただき、初の国際発表をさせてもらった研究内容です。
初の英語でのオーラル発表で緊張しました。
発表の途中でダブルスライドの片方が動かなくなったりして結構焦りましたが、あんまり片側だけ調子悪いから、苦し紛れに聴衆に「片目つぶってください」と冗談を言ったんです。
そしたらバカ受けして、夜のレセプションの時にあちこちの先生から声かけられて、、、それで結構学会好きになりました。
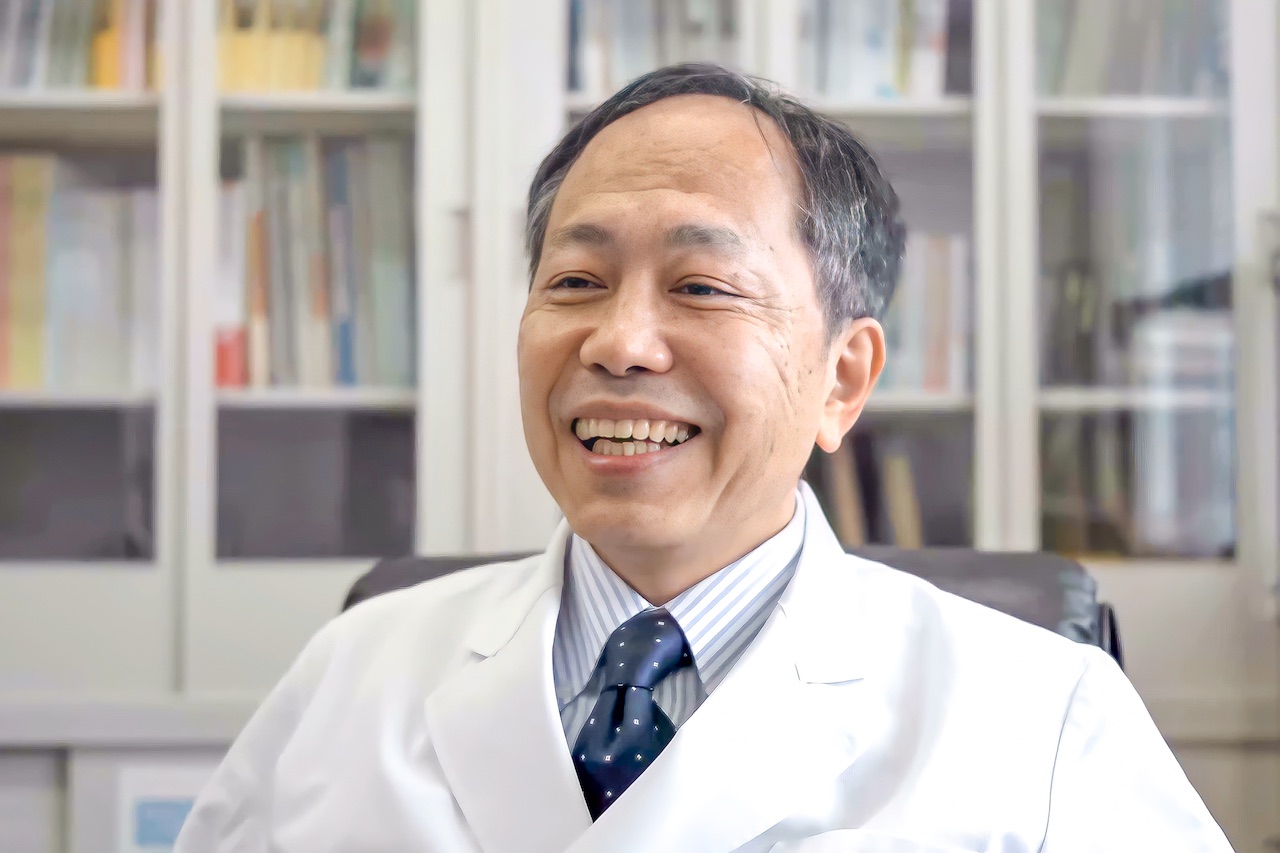
歯突起骨折に前方から螺子固定する手術方法を、同門の中西忠行先生が佐野厚生総合病院にいるときに考案されました。
その後、中西先生は関連病院で手術症例を増やされて、その成績をまとめさせてもらった内容です。
歯突起骨折2型は保存療法では偽関節が6-8割と高率に生じます。
それで結局、後方固定をするのですが、当時Magerl法もなくて治療選択肢が少なかった。
勇気のある先生はtransoralアプローチをやっていましたが、結局は「環軸関節固定術」なんですよね。
この中西先生の前方螺子固定が初めての歯突起骨折に対する骨接合術で、環軸関節は固定しないため回旋可動域が残せる画期的な方法です。
この中西先生の報告を聞いてかどうかは知りませんが、海外から前方裸子固定に関する英文論文が1982年ころにはすでに何編かでていました。
その前の1980年に中西先生は日本語でちゃんと論文にしていた(Internal fixation of odontoid fracture (in Japanese) Seikeisaigaigeka)のと、当時Orthopaedic transactionsという学会抄録集のような英文誌があって、それに中西先生の前方螺子固定の発表が載っていた(Internal fixation for the ododontoid fracture, Orthop Trans 6: 176)ので、オリジナリティーが中西先生にあると証明されたのです。
私は中西先生と臨床現場で御一緒はできなかったのですが、データをいただいたりと何かとご指導いただきました。
── 素晴らしいですね。
今度は千葉先生が佐野厚生総合病院に赴任し、その後の1994年に留学されます。
留学はどういう経緯だったでしょうか?
私が赴任した時には中西先生は別の病院に医長として異動されており、一緒に働くことはありませんでした。
なぜか、当時の慶應整形外科には留学してる人がそんなにいなかったのです。
大学よりも外病院にいる人が留学している印象で、歴代の教授もほとんど海外に留学していなかったと思います。
ですから、大学内にはあまり留学先のツテがなかったのですね。
私は必ず人生のどこかで留学しようとずっと思っていたので、ちょうど佐野厚生総合病院にいたときに学位論文が終わっていて留学先を探してたのですね。
そうしたら後輩の結婚式で、偶然当時防衛医科大学校の新名正由教授にお会いする機会がありました。
そこで「留学先を探しているんです」なんて相談したら、新名先生が「じゃ俺が紹介してやるよ」って。
新名先生は関節軟骨の基礎研究で国際的に有名だったので、その関係でRush University (以下Rush大学)に繋いでもらったのです。
シカゴにあるRush大学は当時軟骨研究の世界的に有名で、臨床面でも全米Best10に入るようなメディカルセンターでもありました。
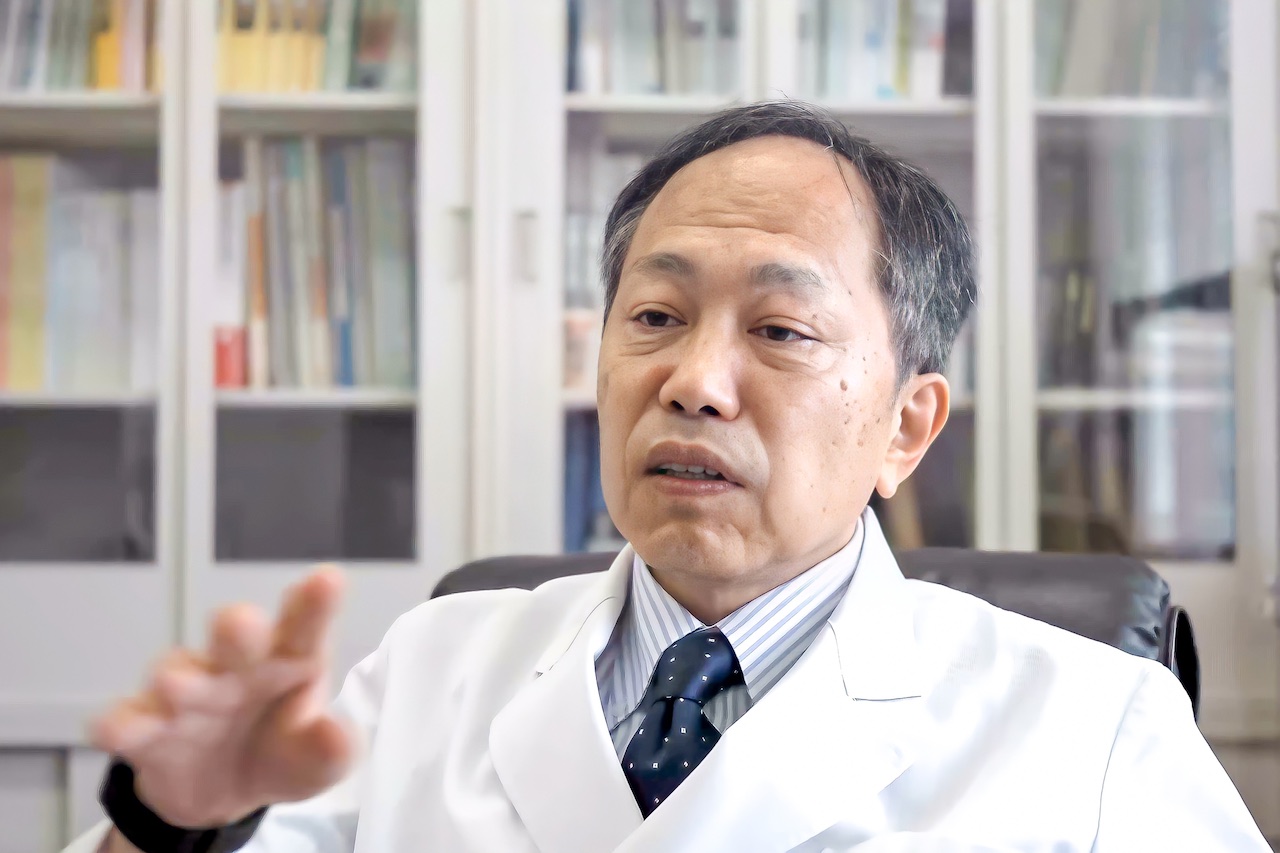
── 留学前も基礎研究をされていたのでしょうか?
私の基礎研究の師匠は東京電力病院の土方貞久先生です。
腰椎椎間板ヘルニアに対する経皮的髄核摘出術を開発されて、カニューラを椎間板に刺して髄核を低侵襲で切除されていました。
大学に戻る前に東京電力病院に一年半ぐらい勤務して、その時に土方先生の下で基礎研究をして慶應に一年間戻ってそれから佐野厚生総合病院に出たという経緯です。
東京電力病院に実験室があって電子顕微鏡を使った研究まで可能でしたので、異動後も通いながら研究を続けて学位論文を仕上げたのです。
色々な物質を椎間板に入れて変性を確認するような椎間板内治療の基礎研究をしていました。
── ご紹介いただく2つ目の論文はRush大学留学時代の椎間板研究の論文です。
軟骨研究で有名だったRush大学に先生が持ち込んだ研究テーマなのですか?
Rush大学は軟骨研究が凄く盛んなところでしたが、当時椎間板は誰もやってなかったのです。
Rush大学では、alginate beadsを使った新しい特殊な3 dimension culture(3次元培養法)を使って軟骨の研究が行われていました。
その培養法が世界的に有名で、私はボスに椎間板細胞でalginate beads培養法をやってみていいですか?って聞いて、ひとりで椎間板研究を開始することになりました。
皆が軟骨研究をやってるところで、ひとりだけウサギの椎間板を切り出して、、、何やってんの?とか言われながらひとり細々と実験をしていました。
実は、やっていたことは単に軟骨研究の応用です。
切り出した椎間板を酵素で消化して細胞を取り出して、そのalginate beadsの中に細胞に入れて培養して、、、alginate beadsによる椎間板培養は過去にMaldonadoって人が論文を発表した以外、どこもやっていなかったのです。
この手法を使って系統的に椎間板代謝を研究したのは私のラボが初めてだったのです。
── 素晴らしいですね。
論文中のlast authorの先生がボスでしょうか?
そのThonar先生が新名先生と仲良くて、この先生が私のことを引き受けてくれたのですよね。
同じラボに、防衛医科大学校から先にきていた舛田浩一先生が、軟骨でalginate beadsを使った研究をたくさんやられていたのです。
彼にいろいろ助けてもらい教えてもらいながら、椎間板の培養をやったのです。
実は、最初は生化学教室のポジションが空いてなくて、私は整形外科に無給で所属していました。
舛田先生はもともと基礎研究の実績があり、生化学教室の正式なポスドクとして給料も出ていたのですが、私は整形外科から生化学に通ってるという形になっていました。
けれど、研究が上手くようになって、Orthopaedic Research Society(ORS)で何回か発表したりグラントを取ったりしたら、急にVisiting assistant professorという役職をつけてくれて有給になりました。
給料がバーンと増えて、アメリカって凄いなぁと思いました。
こんなどこの馬の骨かも分からないポッと出の奴でも、成果を出したら、急にスタッフになって給料もちゃんと出るようになるとは、、、まあ驚きました。
── やっぱりアメリカは、研究資金獲得等、成果を出している人には適切なポジションも給料も出すのですね。
最初のうち実績が何もない時は大変ですけど、それなりに成果を出すと、日本みたいにずっと無給で働くとか、そういうことはまずないですね。
私は成果を出したというより、ただ応用しただけなのですけども、ORSを初め学会で3-4回発表をしたら、急に待遇が良くなりました。
── 留学期間は何年の予定だったのですか?
2年間という予定で行ったのですけど、自分の希望もあり、Rush大学からも是非ということで延長しました。
家族も馴染んできていて、最初アメリカに行った時は英語が通じないとか言ってシクシクしていた家内も、一年経つ頃から友達ができたりして「すごく楽しい」と言ってくれていた。
自宅アパートから少し北に行くとマイケルジョーダンの家があったりするような、治安の良い地域に住んでいたのも良かったです。
実は、マイケルジョーダンが観れると思って留学したら、バスケットボールを引退して野球をやっていました、笑。
残念に思っていたら1年で復帰して、シカゴブルズが2回目の3連覇をした時代の最初の2年は生ジョーダンを観ることができました。
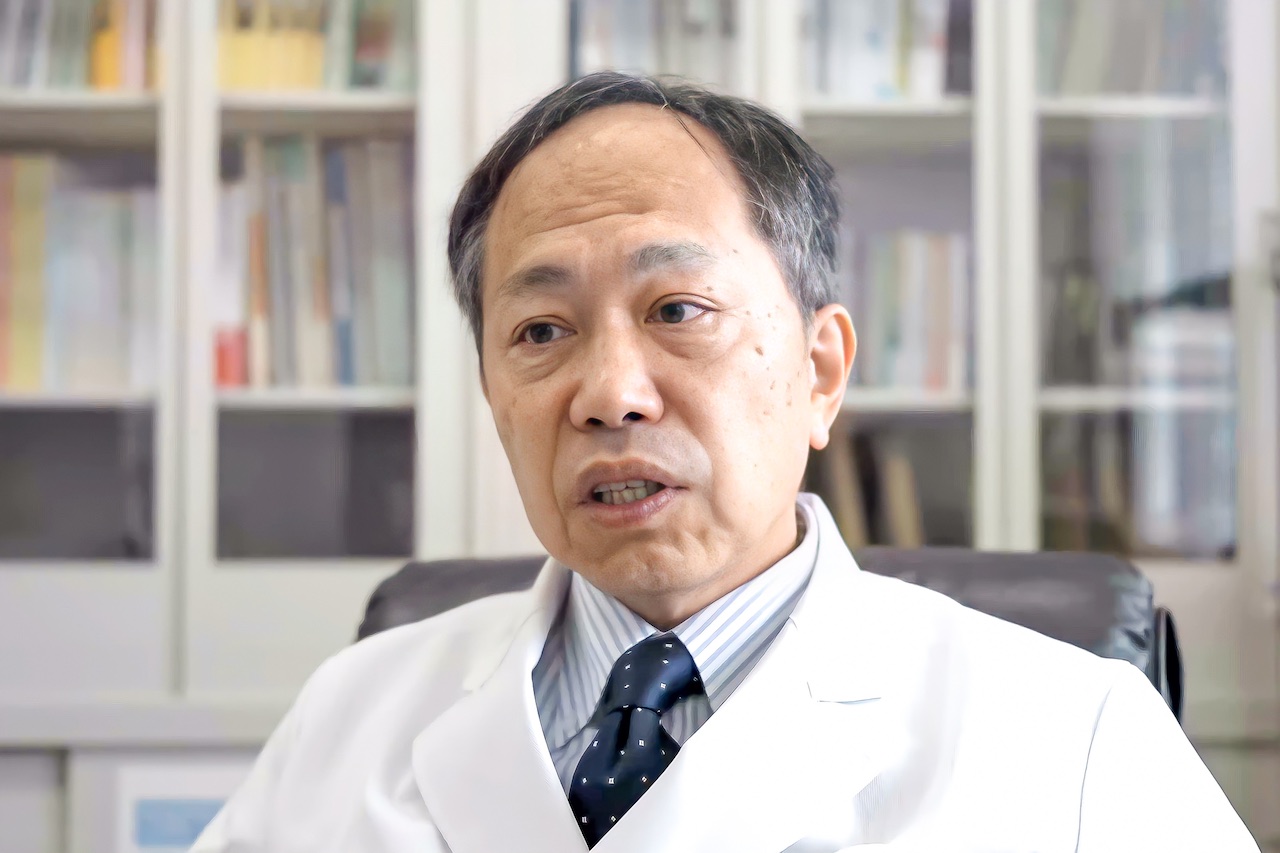
最後にはRush大学からは「ずっとスタッフでいても良いぞ」って言われて、その時には居心地も良くなって、給料も結構もらっていました。
3年目の時には年間7回くらい学会発表学していて、旅費・宿泊費から何まで全部出してくれるので、アメリカ各地を訪問できて楽しかったですね。
それで、慶應の医局長に「もう一回伸ばしたい」って相談したら「今帰らないならもう帰ってくるな」と言われてしまいました。
実はかなり迷ったのですけど、臨床を捨てきれず、結局帰国しました。
その後も舛田先生はずっと残っていて、UCSDの教授になって悠々自適の生活をされています。彼を見ているとそっちの方が良かったかなとか時々思うこともあるのですけど、厳しい世界なので成果が出なくなれば、いつクビになるかわからないですからね。
あの時は人生の分岐点でした。
── アメリカで成功されていて凄いです。
その分、決断は大変だったかと思います。
私が日本へ帰った後、Rush大学は椎間板研究を継続していて、今でもやってます。
Howard An先生が私の帰国後にRush大学に来て、舛田先生と椎間板研究を続けて盛り上げてくれました。
日本から何人も留学生が行って、Rush大学は軟骨とならび椎間板でも有名になったのです。
#02に続く
こちらの記事は2021年9月にQuotomyで掲載したものの転載です。