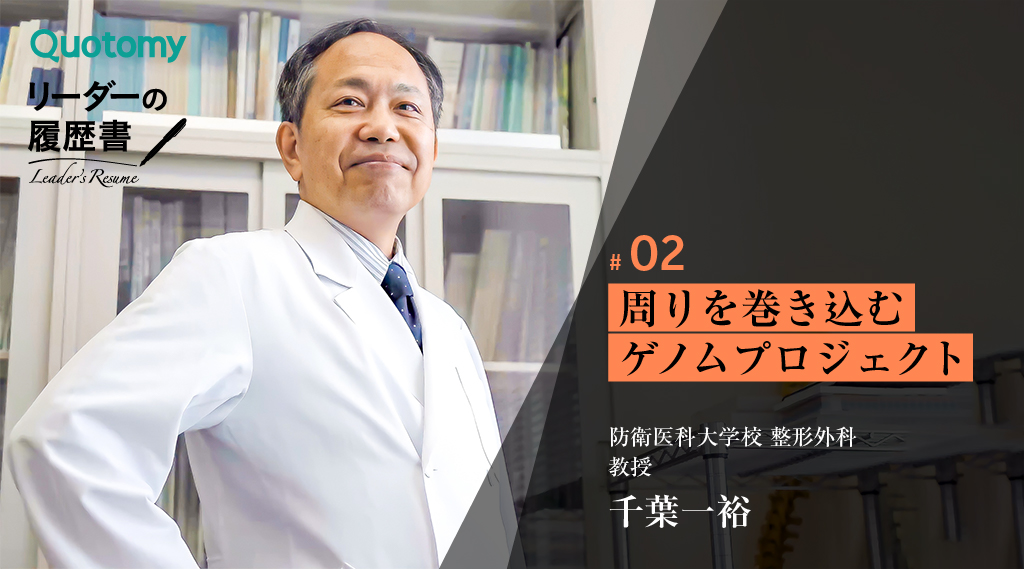
【#02 千葉一裕先生】周りを巻き込むゲノムプロジェクト
本編に登場する論文
A functional SNP in CILP, encoding cartilage intermediate layer protein, is associated with susceptibility to lumbar disc disease
Shoji Seki, Yoshiharu Kawaguchi, Kazuhiro Chiba, Yasuo Mikami, Hideki Kizawa, Takeshi Oya, Futoshi Mio, Masaki Mori, Yoshinari Miyamoto, Ikuko Masuda, Tatsuhiko Tsunoda, Michihiro Kamata, Toshikazu Kubo, Yoshiaki Toyama, Tomoatsu Kimura, Yusuke Nakamura, Shiro Ikegawa
Nat Genet. 2005 Jun;37(6):607-12. doi: 10.1038/ng1557. Epub 2005 May 1.
Long-term results of expansive open-door laminoplasty for cervical myelopathy--average 14-year follow-up study
Kazuhiro Chiba, Yuto Ogawa, Ken Ishii, Hironari Takaishi, Masaya Nakamura, Hirofumi Maruiwa, Morio Matsumoto, Yoshiaki Toyama
Spine (Phila Pa 1976). 2006 Dec 15;31(26):2998-3005. doi: 10.1097/01.brs.0000250307.78987.6b.
── 留学から帰国された千葉先生は慶應大学に帰ってこられたのでしょうか?
そうですね。
そこから15年間は慶應大学にいました。
── 今回ご紹介いただく論文は、理化学研究所・生命医科学研究センターの池川志郎先生との共同研究です。
どういった経緯で始まった共同研究なのでしょうか?
私が慶應に帰ったあと、1999年にある講演会で池川先生がSNPによる軟骨や変形性関節症の研究について話されていたのをたまたま拝聴する機会がありました。
本当に凄いなと思って、講演が終わった池川先生に駆け寄ったのです。
「先生、感動しました。私は椎間板の研究をやっているのですけど、腰痛や椎間板ヘルニアの研究にSNPの応用は可能でしょうか?」
すると「やってみようよ」と気軽にお返事をいただきました。
まずはサンプルを集めろと言われて、椎間板が変性してヘルニアになった人の血液サンプルを少しずつ集め出しました。
若い先生を池川先生のラボに国内留学させたりしているうちに、富山大学の川口善治先生や京都府立医科大学の三上靖夫先生など、だんだん仲間が増えていきました。
実は、SNPの研究には凄くたくさんのサンプルが必要なのです。
慶應整形外科の関連病院だけに声をかけてもすぐには何百症例って集まらないので、仲間が増えたのは本当にありがたかった。
ついにはサンプル数が4-500になって、それで良い結果が出てNature Geneticsに掲載された論文です。
── 池川先生は骨系統疾患の原因遺伝子を同定する研究をされていましたが、変形性関節症のようなcommon disease分野にも応用されていたのですね。
当時から変形性関節症などcommon diseaseの発表もされていて、椎間板も「とにかくやってみよう」と言ってくださいました。
サンプル数は最初は最低200!とか言ってたのに、いつの間にか「500必要だ」「1000必要だ」少しずつと増えてくるんですよ、笑。
でも、やっぱり数は力なんです。
当時、周りの研究ではせいぜいN=100ぐらいで出されている論文が多く、再現性がなかったのですが、我々の研究はサンプル数が多くて統計学的検定もかなり厳密にできた。
あとは、見つかった遺伝子の機能解析までしたのです。
従来の研究では「この遺伝子が怪しい!」で終わっていたところ、我々は「椎間板ヘルニア患者に多いSNPはどんな働きしてるだろう」という点まで追求し、見つかったCILP遺伝子によるCILPタンパクがTGF-β1の結合に関係していると機能解析までやったのですね。
こうした研究が続いて、慶應からも何人か国内留学で理化学研究所・生命医科学研究センターにいってもらって、それぞれが候補遺伝子を見つけるといった成果をきちんと出し、学位取得にも繋がっています。
── 千葉先生が、協力してくれる先生方を集めていったのですか?
それとも池川先生が?
我々が研究をやってるのを見て、仲間に入りたいって言ってきてくれた先生もいれば、池川先生の繋がりで入ってくださった先生もいましたね。
色々なメンバーだったのですけど、凄く良いチームでした。
結局この研究は国際共同研究になりました。
フィンランド、香港や中国とかと一緒になって、椎間板ヘルニアのサンプル数が2-3,000と、それからコントロールサンプルは30,000ぐらい集まったのです。
そのあとは、慶應大学整形外科現教授の松本守雄先生が当時側彎症の手術を数多くやっていたので池川先生に紹介して側彎症遺伝子プジェクトが始まったり、厚労省の班研究の活動繋がりからOPLL遺伝子プロジェクトが始まったり、どんどん脊椎分野の研究が広がって色々な成果がでるようになりました。
自分としてはすごく嬉しかったです。
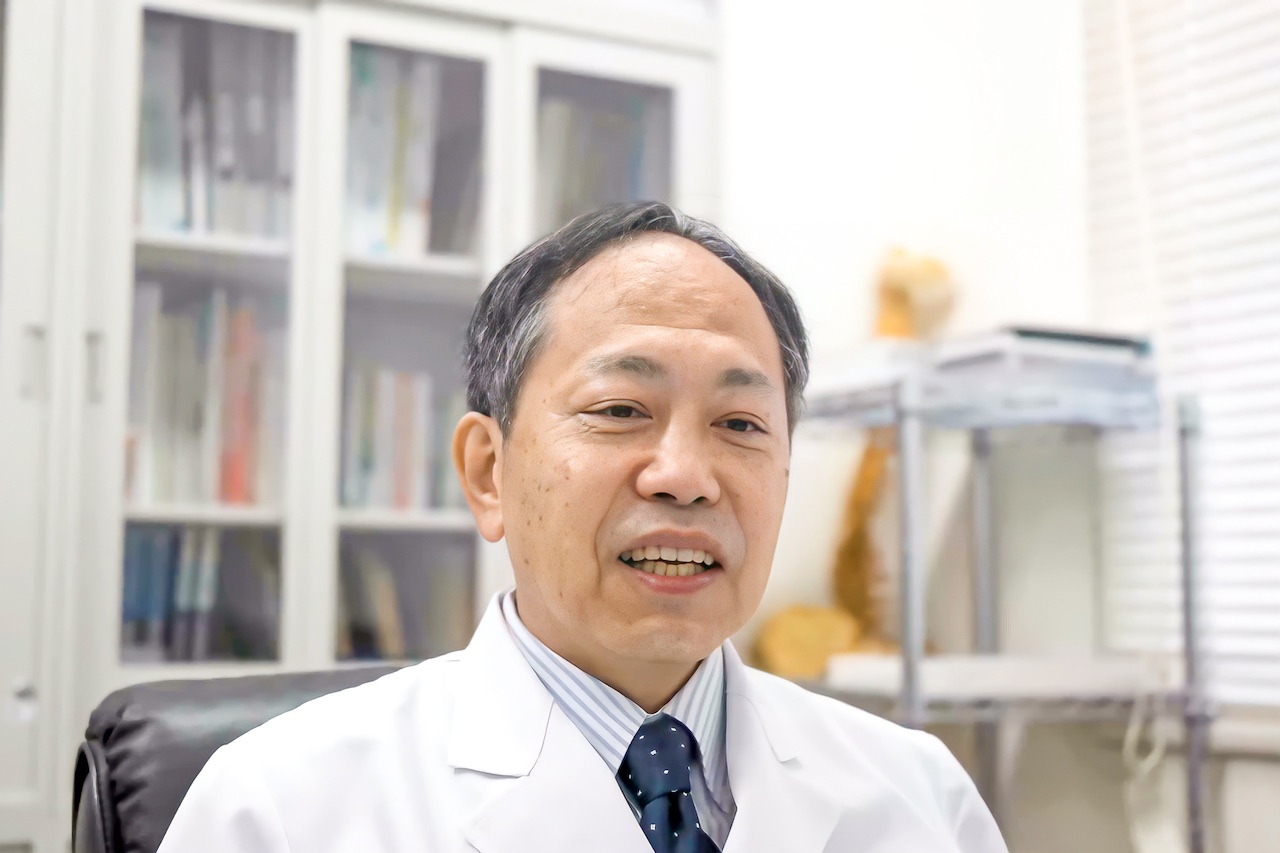
── 今回ご紹介いただく、もう1つの論文は頚椎拡大術の長期成績に関するものです。
はい、これは長年にわたり慶應大学整形外科が御家芸にしていた頚椎椎弓形成術、いわゆる片開き式脊柱管拡大術に関する臨床研究論文です。
1999年の第28回日本脊椎外科学会(当時、現日本脊椎脊髄病学会)で平林冽先生が会長をされて、出した主題が「脊椎手術の長期予後 -その問題点と対策-」でした。
その学会では、ラブ法とか頚椎前方手術とか、各大学が長期フォローを出し合ったのです。
慶應では色々な手術の10年フォローという長期経過観察を報告しようということになりました。
手術した患者さんを電話して呼び出して、診察をしてJOAスコアをつけたりと、通常の外来診療の後に長期フォローアップの患者さんの診察をやったので凄く大変だったんですね。
遅い時は23時頃までかかっていたと思います。
ちょうど教授が戸山芳昭先生に変わったばかりの頃で、世代交代が始まっていました。
戸山先生に「お前チーフやれ」とか言われて、私がまだ40歳くらいでしたがそれでも当時いた若手のなかではたまたま一番の年長だったため、慶大脊椎班のチーフをやるはめになったのです。
私の下には松本守雄先生、渡辺雅彦先生、中村雅也先生とかいて、今ではみんな偉くなったのですけど、その頃は皆で「ひえー」とか「どうしよう」とか言いながら、おっかなびっくり手術をして、術前後のデータ集めて、、、辛かったけど楽しい日々でした。
この頃、随分と十年フォローの論文を作り出しました。
私のこの論文は学会発表の際に集めたOPLLと頚椎症性脊髄症の術後10年フォロー両方のデータまとめてSpineに載せたのですね。
これは私の論文の中でも特に多く引用されるようになりました。
今となっては、頑張って論文にして出して本当に良かったな、と思います。
── 頚椎の後方から脊柱管狭窄を広げる拡大術が日本で発展した時代ですね。
日本には発育性脊柱管狭窄とOPLL患者さんが多かったので、それに対応するために拡大術が発展してきたのだと思います。
でも、私が慶應整形外科に入った1983年当時はまだ前方固定が主流でした。
私は4-5年目くらいまで、この片開き拡大術は見たことはあったのですけど、自分でやったことはなかったですね。
本当に前方固定ばかりやっていて、3椎間の狭窄とか連続型OPLLでも、できるだけ前方からアプローチしていました。
髄液漏になったり、術後呼吸困難や麻痺が起きたりして、結構大変でした。
平林先生が片開き式拡大術の最初の手術を1977年にやって、日本語の論文は1978年頃、それを英語論文として出したのは1980年です。
私は1983年に卒業して平林先生の拡大術も何例か見ていたのですけど、その頃はまだそんなにガンガン拡大術をやっていた訳ではなかったです。
ですから80年代後半から90年代頃から増えてきたのではないかと思います。
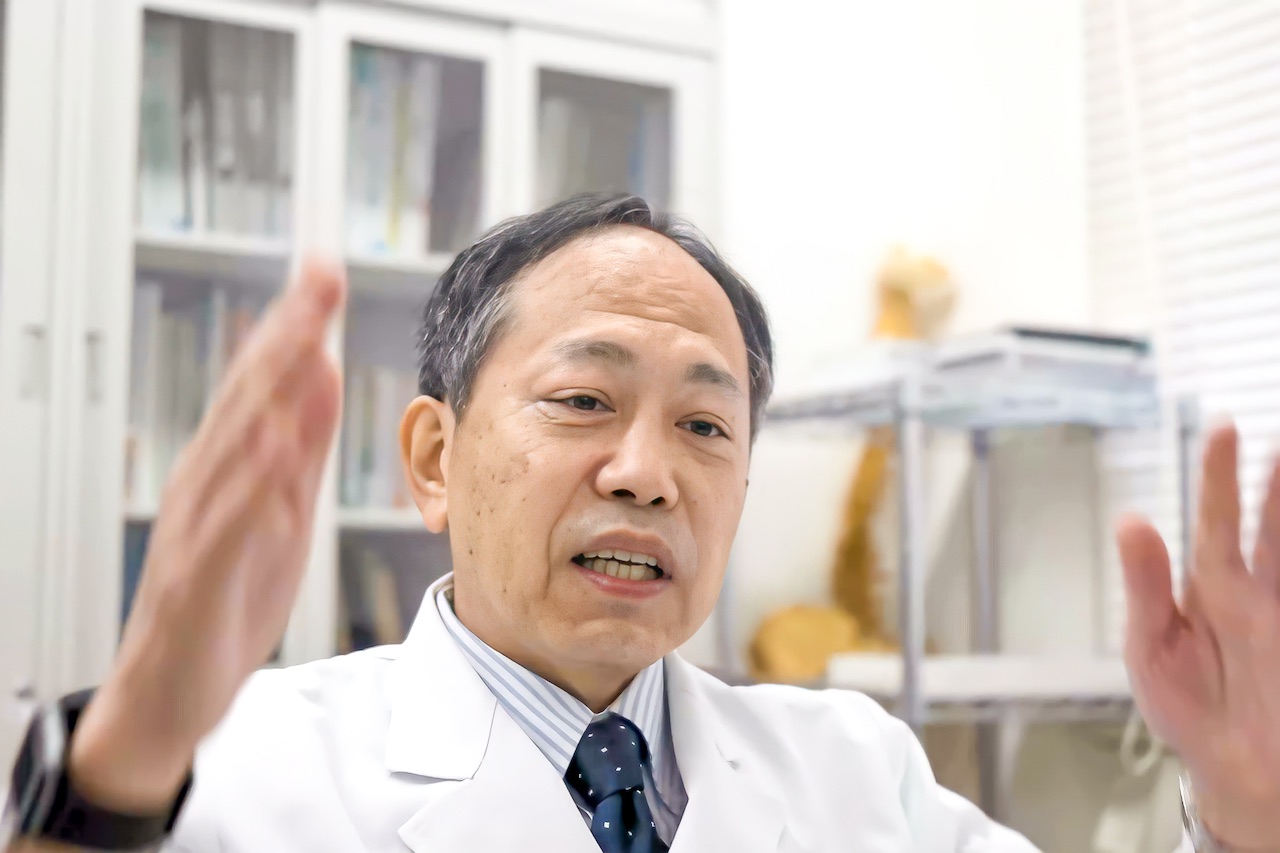
── 意外です。
凄く有名で明瞭なコンセプトの手術だから、発明されたらすぐに皆に広まったのかと思っていました。
手術の術式が広がっていくのには時間がかかるっていうことですね。
1982年には東京大学の黒川髙秀先生が縦割式拡大術の論文を出しています。
その頃から、黒川先生の正中縦割式と平林先生の片開き式の両方が、日本中にだんだん広がっていきました。
そんなに急にぱっと広がる訳ではないのですね。
海外は90年後半でもまだ前方が良いという論文・発表が多く、私は頚椎国際学会で頚椎拡大術の話をしてもアメリカの医師からは「前方の方が良いのに、なんで後方をやるんだ」みたいなことを良く言われました。
向こうの人はあまり発育性脊柱管狭窄はないですし、脊髄症状ではなく頚部痛に対しても積極的に手術する。
我々みたいに神経障害を治すというより、とにかく首が痛けりゃ固定しちゃおうみたいな発想です。
だから「頚椎拡大術なんかしたら、かえって首が痛くなるじゃん」とか言われました。
── 議論の前提として、対象が異なっているのですね。
そうですね。
日本人はOPLLあるいは脊柱管狭窄患者の脊髄症に対して手術する。
向こうは神経根症あるいはただの頚部痛に対して手術してしまう。
その辺の考え方が違うので最終的に議論はかみ合わなかったですね。
── 国際学会で議論といえば、先生は英語がとても堪能でいらっしゃるのですが、それだけでなく、なんというかコミュニケーションが本当にお上手だと思います。
その秘訣は何でしょうか?
私は今でいう帰国子女なんです。
父親が商社に勤めていたので、小学校と中学校の時にアメリカとイギリスに何年か住んでいました。
だから、英語に対して抵抗はないです。
皆さんに「先生、帰国子女だからいいですね」ってよく言われるんですよ。
「英語の発表も上手で、論文も英語で書くのが苦じゃなくていいですね」って。
ですから、嫌味って言われるかもしれないけど、「先生はいいですね。ずっと日本にいたから日本語の発表はいくらでも自由にできて、論文も苦もなくいくらでも書けますよね」って言い返すんです。
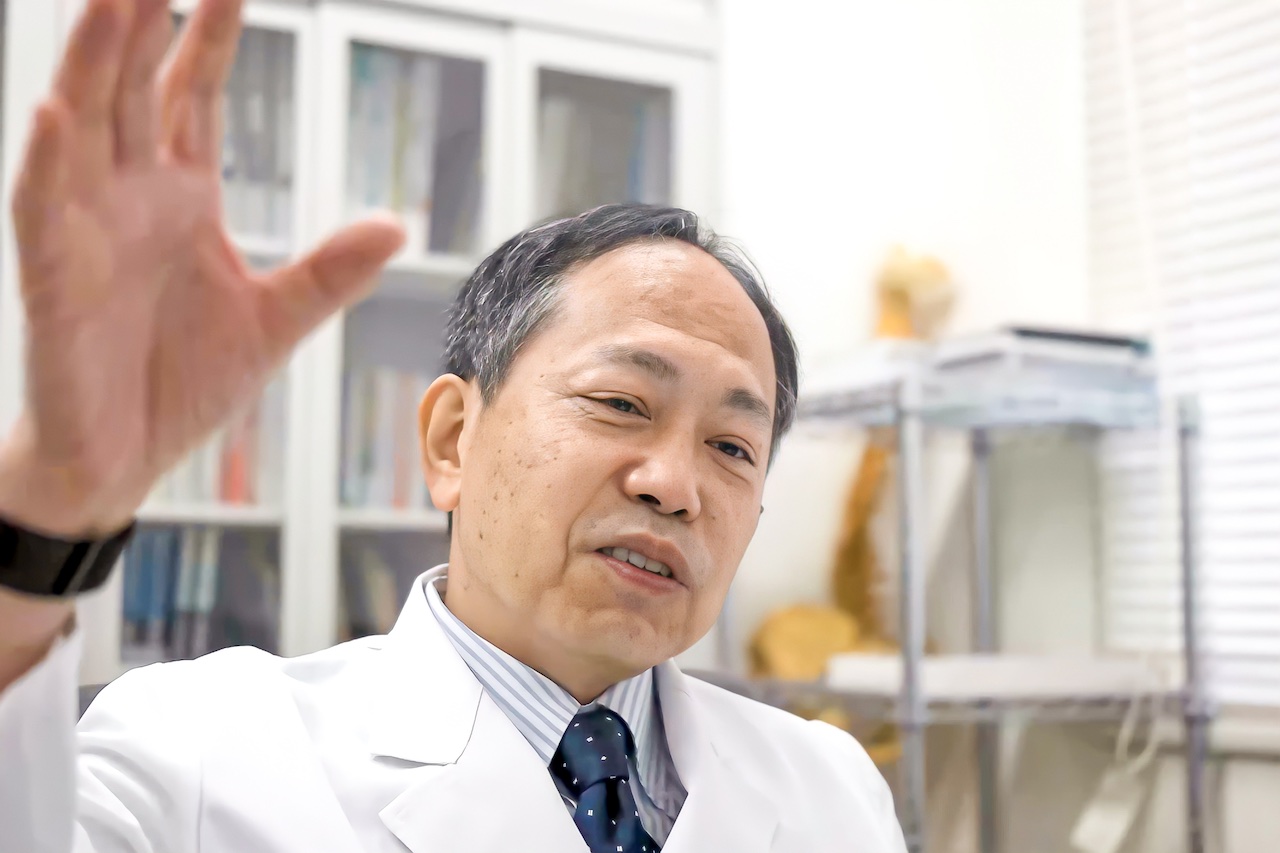
やっぱり英語論文や発表の準備はすごく大変です。
じゃあ、アメリカ人の医師が皆英語の論文をバンバン書いて、発表を流暢にできるか?って言ったらそんなことは絶対にないですから。
今でこそ、私より英語の発表が上手な先生や論文もどんどん書く先生がたくさんいますけど、同年代ぐらいでは私はまあまあ英語の発表をしてる方だと思います。
けれども、それは帰国子女だからだけではなく、誰よりも英語の勉強はしたと思います。
── 凄い努力された。
努力ってほどじゃないですけど、結構色々勉強はしました。
やっぱり正しい英語を話さないといけないので、文法とか冠詞とかね。
もしかしたら、前置詞とか冠詞などをあまり深く考えずに使えるのは、海外生活していたからかもしれないですけどね。
だけどかなり細かいところを勉強して、これはaとtheのどちらを付けたらいいのか、これは固有名詞だから冠詞はいらないなとか、前置詞はofとtoとforどれが一番いいかな?、これを言い替えるにはどうしたらいいかな、とか細かくちゃんと辞書をひいています。
逆に、後輩が「論文見てください!」って持ってきて、スペル間違いやめちゃくちゃな文法だったりすると、結構イラッとする時はありますね。
スペルチェックくらいしてから見せてくれ、本当に自分でこれ読んでわかるの?と文句の一つも言いたくなります。
── 論文投稿ですと、そういうミスが明暗を分けるかもしれないですよね。
本当に内容が良くてもスペル間違いがあったりで小学生みたいな扱いを受けてしまうと残念です。
そうですよ。
私がレビュアーだとtypoなどを見つけたら指摘して直すように言いますけど、レビュアーによっては一発rejectと厳しい判断もありうると思います。
細かい勉強や努力は語学習得には大切だと思います。
#03に続く
こちらの記事は2021年9月にQuotomyで掲載したものの転載です。