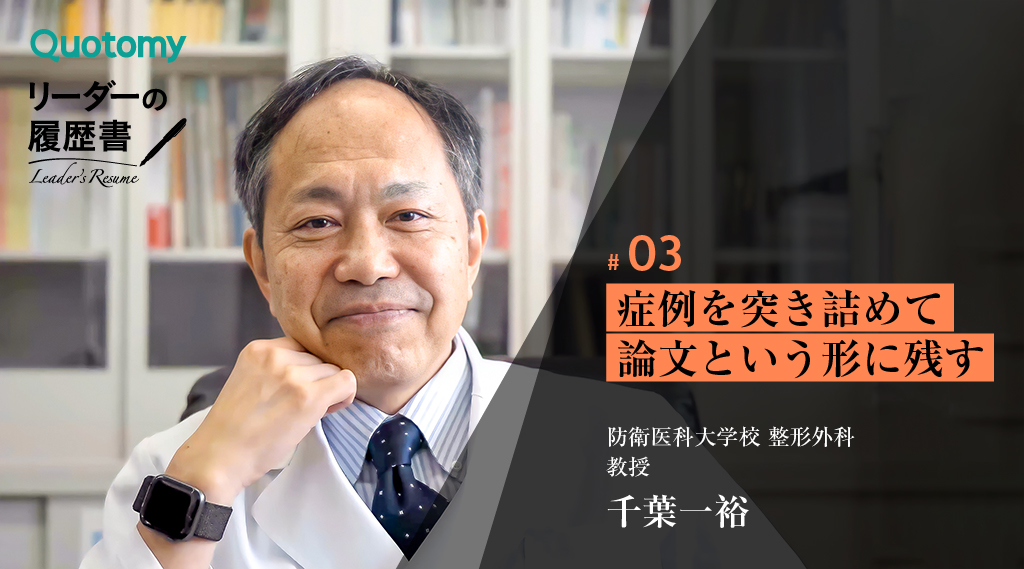
【#03 千葉一裕先生】症例を突き詰めて論文という形に残す
本編に登場する論文
Matrix replenishment by intervertebral disc cells after chemonucleolysis in vitro with chondroitinase ABC and chymopapain
Kazuhiro Chiba, Koichi Masuda, Gunnar B J Andersson, Shigeki Momohara, Eugene J Thonar
Spine J. 2007 Nov-Dec;7(6):694-700. doi: 10.1016/j.spinee.2006.09.005. Epub 2006 Dec 22.
Condoliase for the Treatment of Lumbar Disc Herniation: A Randomized Controlled Trial
Kazuhiro Chiba, Yukihiro Matsuyama, Takayuki Seo, Yoshiaki Toyama
Spine (Phila Pa 1976). 2018 Aug 1;43(15):E869-E876.
── 今回まずご紹介いただく論文は2007年のSpine Journalに掲載されたコンドリアーゼに関する研究です。
実はこれは留学中にやった仕事なのですよ。
私のデータとドラフトがThonar先生の机の上にずっと乗っていて、催促しても「もうじきやるから」と言われ放置されていたのです。
結局publishされたのが2007年になりましたから、たぶん10年くらいThonar先生の机の上にあったと思います、笑。
留学中にこの研究でコンドリアーゼと縁ができて、それからずっとコンドリアーゼに関わっています。
詳しくお話すると、コンドリアーゼを土壌菌プロテウス・ブルガリスから抽出したのは名古屋大学理学部化学教室鈴木旺教授研究室にいらした山形達也博士でした。
そこに当時大学院生だった岩田久先生(現名古屋大学名誉教授)が留学されて、コンドリアーゼを使って軟骨の基質を分解して、コンドロイチン硫酸異性体の組成を調べるという研究をしておられました。
岩田先生がコンドリアーゼを椎間板の中に入れたらいいじゃないかっていう発想を得たのが1968年くらいだったと聞いています。
当時は蛋白分解酵素であるキモパパインを椎間板に注入するという治療(Chemonucleolysis:化学的髄核融解術)があったのですが、神経障害やアナフィラキシーなどの合併症が多かったのです。多糖分解酵素であるコンドリアーゼを使えばより副作用が減らせると考えたのです。
私が留学していた頃は、既に岩田先生は名古屋大学整形外科の先生たちとコンドリアーゼの研究を始めて、生化学工業を巻き込んで、動物実験とか色々研究されてたんですね。
私はその一連の流れとは別に、当時流行ってたin vitroの細胞培養実験でコンドリアーゼの有効性・安全性を確認するという研究をやっていて、キモパパインと比べて、コンドリアーゼの方がずっと細胞にも優しいし、椎間板基質中のプロテオグリカンは壊すけどコラーゲンなどのタンパクとかは壊しませんよ、っていうのを定量的に示したのです。
コンドリアーゼが上市されたのは2018年で岩田先生がその着想を得てからもう50年以上経っています。
私はその半分ちょっと、1994年からコンドリアーゼ研究に関わって、日本に帰国してからも臨床治験に携わらせてもらいました。
松山幸弘先生(当時名古屋大学、現浜松医科大学整形外科教授)をはじめとした名古屋大学の先生たちが中心に臨床研究を始めていて、私も基礎研究に携わっていた関係でチームに入れてもらえたのです。
── 留学先のRush大学をはじめとしたアメリカでは、コンドリアーゼと椎間板に関する研究は誰もやっていなかったのですか?
当時、椎間板の研究をやっているのは私だけでした。
本当にひとりでチマチマと細胞を培養しては、コンドリアーゼとキモパパインを培養液に混ぜて、そのあとに椎間板基質合成能がどうなるかとか、DNA量が減った減らないとかと見ていました。
舛田先生や、慶應の後輩で膝軟骨や半月版の細胞培養研究をしていた桃原茂樹先生にも手伝ってもらったりしてました。
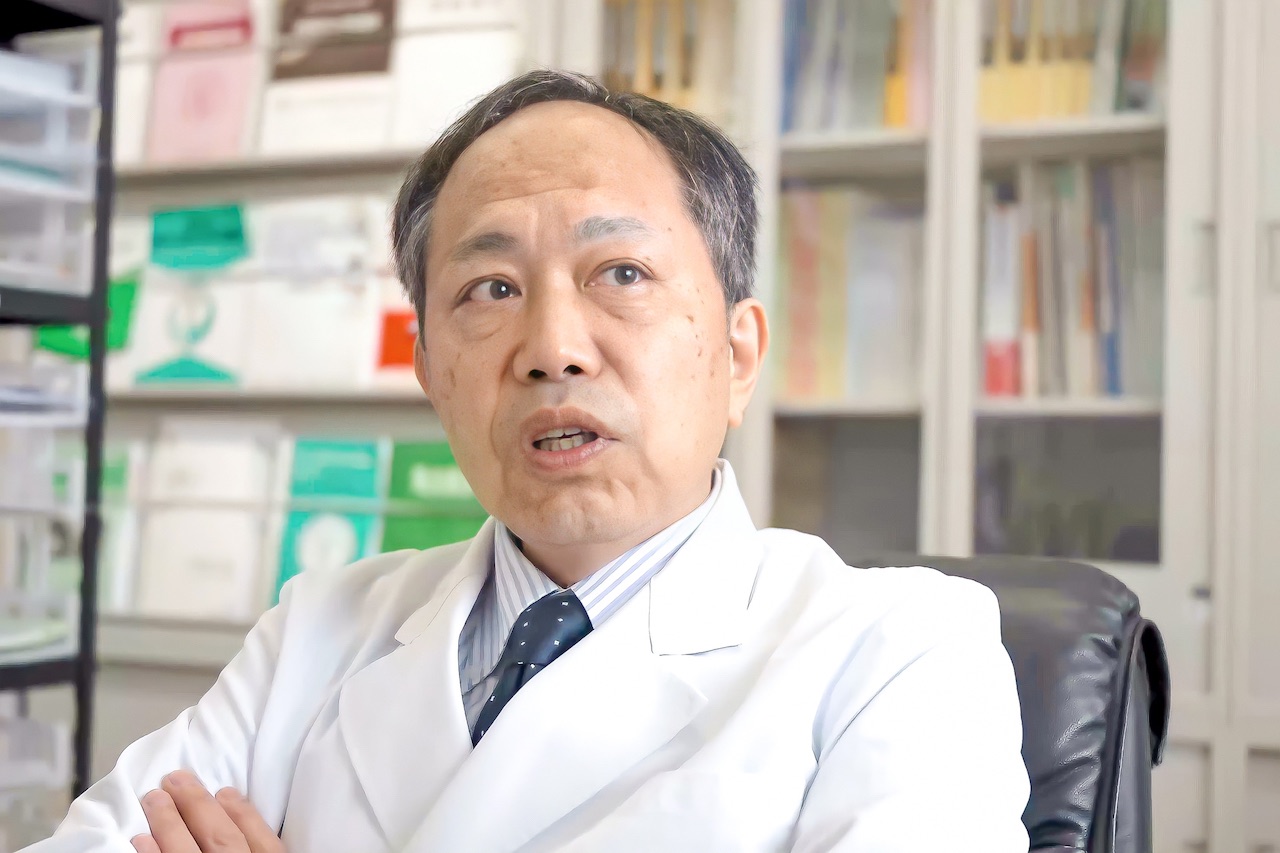
── 2009年から慶應大学整形外科の教室主任に就任されます。
どういう役職なのでしょうか?
その頃に戸山芳昭先生が慶應大学病院長になったのですね。
それで、本当は教授がやる役職の診療部長を私がやることになりました。
その後さらに戸山先生が慶應義塾の理事になって「教室主任、チェアマン役をお前がやれ」と。
全部そうですよ、脊椎班のチーフも「じゃ千葉先生よろしく」。
歴代の大先輩方のあとに僕でいいんですか?って思いましたけど「もう俺はできないからさ、お前がやるしかないんだよ」みたいな感じです。
そういう感じで、診療部長も教室主任も「よろしく」でした。
── 戸山先生からの信頼を感じますね。
戸山先生は私が2年目の時のオーベンで、椎間板研究を土方先生の下で始めるきっかけも頂いていた。
教授選でもし戸山先生が教授にならないで外へ出ることになったら私も一緒に出ようと思っていました。
ところが、自分が留学から戻った後程なく戸山先生が教授になったのですね。
脊椎チーフになるように言われた時に「やれるうちは精一杯頑張ります。その代わり一段落したら良い関連病院に出してください」というようなことを言いました。
あまり大学に長くいるつもりは無かったですし、その能力もありませんでした。
── ところが、教室主任を任されるようになり、脊椎班チーフとは異なり、脊椎以外もマネージメントしなくてはいけなくなります。
そうですね、整形外科全体ですね。
総回診もやっていましたし、学会前の予演会も脊椎班だけじゃなくて全部見ていましたよ。
でも、脊椎班のチーフになった時から後輩の先生に実務をやらせるスタンスでいたので、他の班の面倒をみるっていっても別にただやることが増えただけで、自分で脊椎の臨床ができなくなるとか、そういう気持ちはなかったですね。
脊椎班の後輩には松本守雄先生、中村雅也先生、渡辺雅彦先生など、凄く優秀で手術も上手い若手スタッフがいたので、自分が表立ってやるよりは彼らが少しでもやりやすいような環境を作った方が脊椎班としてはいいんじゃないかと考えました。
手術も彼らがメインで、私は助手でできるだけ入るようにして、松本先生は脊柱変形中心、中村先生は脊髄腫瘍中心でやってもらいました。
冗談で「両方の手術に入れるのは俺だけだ」とか言ってね。
自分でバリバリやるより、後輩で将来おそらく教室を背負って立つ人間が活躍する場所を与えて、伸びて貰った方が脊椎班のためになると思ったのですね。
私は上にも良い先生が多くて下の先生も優秀で、常に皆に助けて貰って今まで何とかやってきました。
その後、本当は東京電力病院に行きたいって言ったのですけどなかなかチャンスがなくて、結局2012年に北里研究所病院に出してもらいました。
── 北里研究所病院では脊椎センターを立ち上げてらっしゃいます。
久しぶりに臨床をメインでやって、自分で手術もたくさんできて楽しかったですね。
俺もまだできるぞって、若返ったような。
私が整形外科部長として赴任した当時は、どちらかというと内科がメインの病院だからか、どの科も外来をいっぱいやっていたのです。
外来をやらないと患者が来ない、と言って。
整形外科もみんな外来が忙しくて助手がいないため、手術できないとかいうこともありました。
そこで、整形外科は外来数を減らして手術を増やしますって病院長に言ったのです。
最初は嫌な顔されました。
でも1年で200件ぐらい手術件数を増やして売り上げが増えたら、急に病院長も認めてくれるようになって、脊椎センターを立ち上げてもらい、手術機械もいっぱい買ってもらいました。
でも、3年でいなくなることになって、病院長もきっと激怒してたと思います。
今ではちゃんと慶應脊椎班の後輩の日方智宏先生が一生懸命やってくれて脊椎の症例数も延ばしてくれているので助かりました。
── 防衛医科大学校に教授に就任されるのですね。
実は、新名正由先生に留学でお世話になった際に「帰国したら防衛医大だぞ」って言われたんですよ。
自分でもそう思ってたんですけど、留学中に新名先生がご病気で急にお亡くなりになってしまいました。
それで私は慶應に戻ることになったのですね。
その後の防衛医科大学校整形外科教授は、冨士川恭輔先生が跡を継がれて、その後は根本孝一先生が第四代教授と、教授は代々ずっと慶應出身だったのです。
でも、根本先生の退官される時期に、戸山先生が早く退官されたので慶應大学もちょうど教授選になっちゃったのですね。
それで慶應から防衛医科大学校の教授選に出る人がおらず、私にお誘いがあったのですけど、私は臨床が楽しい時期でしたし、ずいぶん教職から離れていましたので、今さらと思い、誘ってくれた先生に断りにいきました。
でも、その場でお前しかいないみたいなことを言われると、私もお調子者だから直ぐに翻意してお受けすることになってしまったのです。
どうせ落ちるんじゃないかなと思ったんですけど、運がいいのか悪いのか、教職に戻ることになりました。
── 防衛医科大学校での教職はいかがでしょうか?
それまで在籍していた慶應とか北里は私学でしたから自由に出来ましたが、国立は全く逆で色々制約もあるので慣れるまでは結構大変でした。
防衛医科大学校では、学会発表などの出張は、防衛大臣のハンコが必要な大臣決済なのですね。
気軽に行ったり止めたりはできません。
最初は目眩がしましたけど(笑)、でも若い人を教育できるってのは楽しいですね。
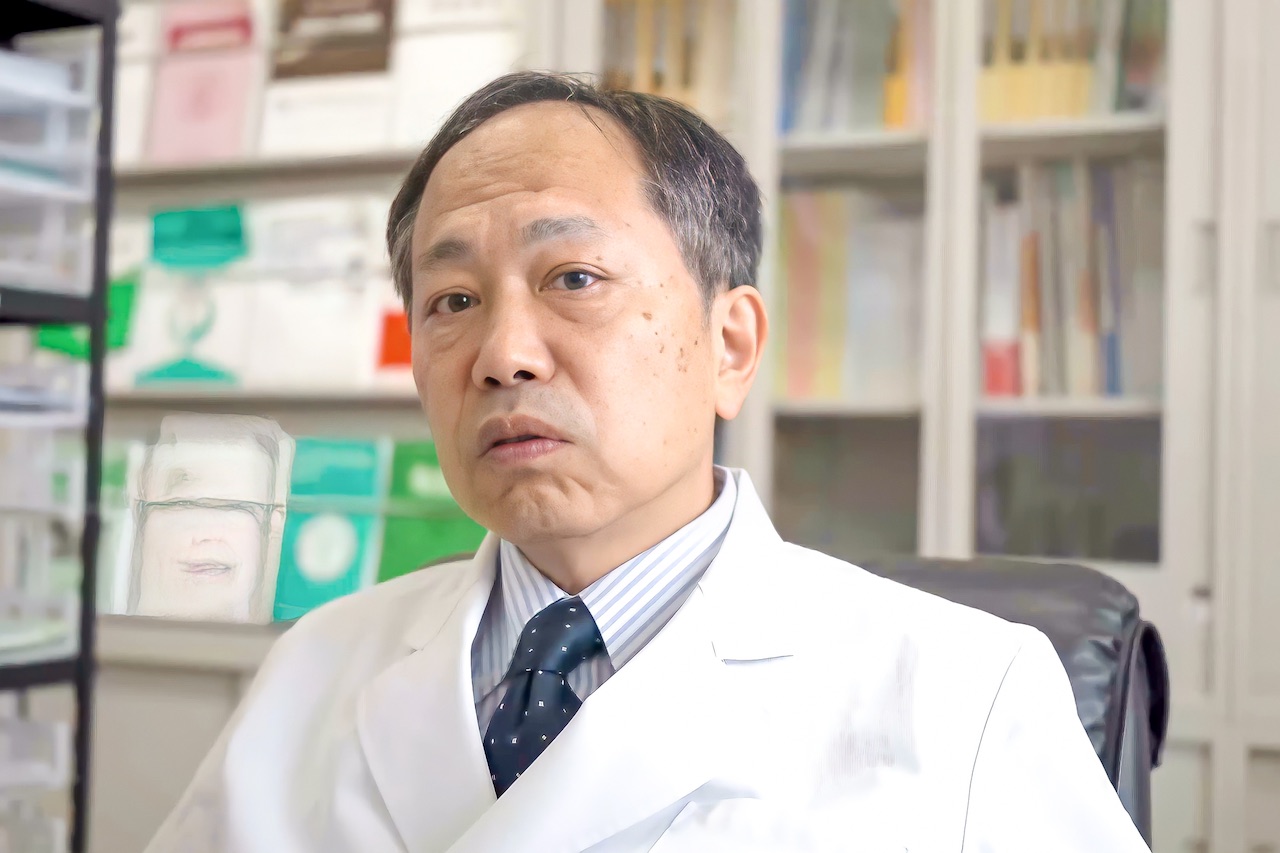
── 最後にご紹介いただく論文はコンドリアーゼのランダム化比較試験である第3相臨床試験の結果ですね。
これは始める前に練りに練ってプロトコールをしっかり決めて、全国の先生方にご協力いただいたてできた臨床研究です。
これは実はリベンジの試験で、この前に1度やっているのです。
第1・2相試験で良い成績がでていたので、第3相試験はプラセボとコンドリアーゼの容量別の3群、計4群にして計画したのです、
これは厚生労働省の承認とコンドリアーゼの容量決めの両方を同時に行おうという少し欲張った試験でした。
つまり1つの試験で、プラセボに対する優位性を示し、さらに1番効果のある容量まで決めるような前向きのランダム化比較試験であり、その結果をPMDAに提出したのですね。
そうしたら容量別の3群のうち、1つだけプラセボと有意差がでなかったのです。
そこを突かれて「駄目です」と。
層別解析したら、プラセボと有意差がでなかった群に、ランダム化したけれど長期経過例など条件の悪い症例がたまたま多かった事がわかったのです。
そういう理由も付けて「全体としては有意差がついてますので承認してください」って出したのですけど、「いやー、一番見たかった群に有意差がついてないから駄目です」って言われたんですよ。
お金も時間もかけていたのに、、、それはそれはがっかりしました。
私はもう日本ではコンドリアーゼは認められないな、と思って諦めかけたのです。
だけど、岩田先生、松山先生や生化学工業の人たちが諦めず、濃度を1つに絞って症例数を増やしてもう1回やりましょう、と頑張ってくれたんですね。
今回は、コンドリアーゼ投与群とプラセボをそれぞれ80症例ずつの前向き比較試験で有意差が完全について、どうだぁとばかりに結果をPMDAに持っていって、やっと認可された。
そういう経緯があるので、余計に感慨深いのです。
── そんなリベンジのストーリーがあったのですね。
岩田先生にお会いする度に「まだ承認おりないの〜、俺が生きてる間に頼むよ〜」とか言われて、、、その度に「我々の努力が足りなくてすみません、もうちょっとお待ちください」と言って謝っていました。
だから、承認された時はもう岩田先生は本当に喜んでおられましたね。
今回、この論文を何で紹介したかっていうと、とにかく諦めずに続けていれば必ず良いことがあると若い人に知って欲しいと思ったのです。
ランダム化比較試験なんていっぱいあるし、別に特別な研究じゃないって言えばそうなんですけど、こうやって患者さんを救える可能性のある薬を世の中に出せたっていうのは、やっぱり医者として科学者として凄く嬉しいことです。
自分が25年近く関わってきた、そういう研究を通してひとつの薬剤がついに日の目を見て、少しでもヒトの役に立つことができたので本当に続けてて良かった。
どこかで読んだ言葉で「成功とは成功するまでやり続けること」ってあるのですけど、正にそうだなと思いましたね。
1回パっとやって成功する才能ある人もいるでしょうけど、才能なくても続けていれば成功するかもしれない。
逆に続けてない限り絶対成功しない。
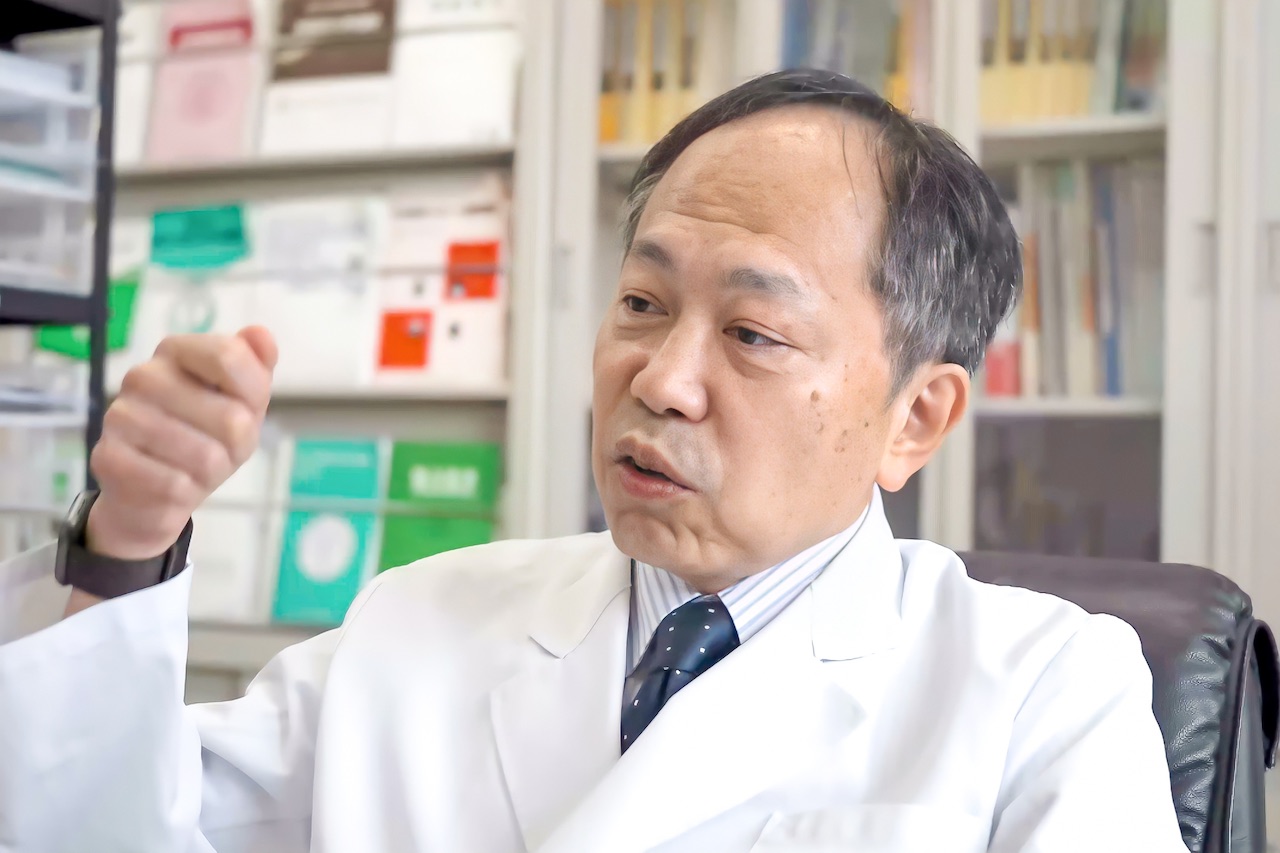
いつも若い先生にメッセージとして言っている、論文を何で書くのか?という、私なりの理由を最後に伝えさせてください。
よく「教授になりたいから」とか「出世のために」とか言われますけど、私は違うと思います。
学会発表だけで済ませちゃう人って本当にたくさんいるじゃないですか。
論文を書くというのは、1つ1つの症例を大切にして問題点を明らかにし、それを突き詰めてちゃんと調べたことを形に残すことに他なりません。
そういう地道な作業の積み重ねを何年も続けてる人と、それを途中でやめちゃった人とでは臨床能力にもの凄く差が出ると思います。
「俺は臨床医だから論文を書くために医者やってるんじゃない」とか、「忙しくて論文なんか書いてる暇はない、そんな時間があれば手術の腕を磨くんだ」って言う人もいると思います。
勿論それはそれで素晴らしいことだと思うのだけれども、それにプラスして、忙しくても文献を調べて教科書たくさん読んで、症例を突き詰めて、新しい診断法や手術法なり何らかの知見を形に残すということが凄く臨床能力の向上に繫がるのですよ。
だから、手術が上手くなりたいとか、臨床能力を身につけたいと思う人はむしろ論文を書いたらいいなと思います。
そうすると、その分野では自分が一番いろいろなことを知っていることになるじゃないですか。
論文書いてる暇があったら手術した方がいいとか言う人もいますが、決してそんなことはないので、ぜひ自分自身の臨床能力を高めるためにも論文を書いて欲しいです。
自分で治療できる患者さんの数は限りがありますけど、良い手術法や診断法を開発して論文という形に残して後世に伝えていければ、より多くの人のためになるかもしれないですよね。
これは私も尊敬する先輩に教わったことなのですけど、その影響もあって後輩に論文を書け書けって常に言うようにしてるんですよね。
── 千葉先生、素晴らしいメッセージをありがとうございました!
こちらの記事は2021年10月にQuotomyで掲載したものの転載です。