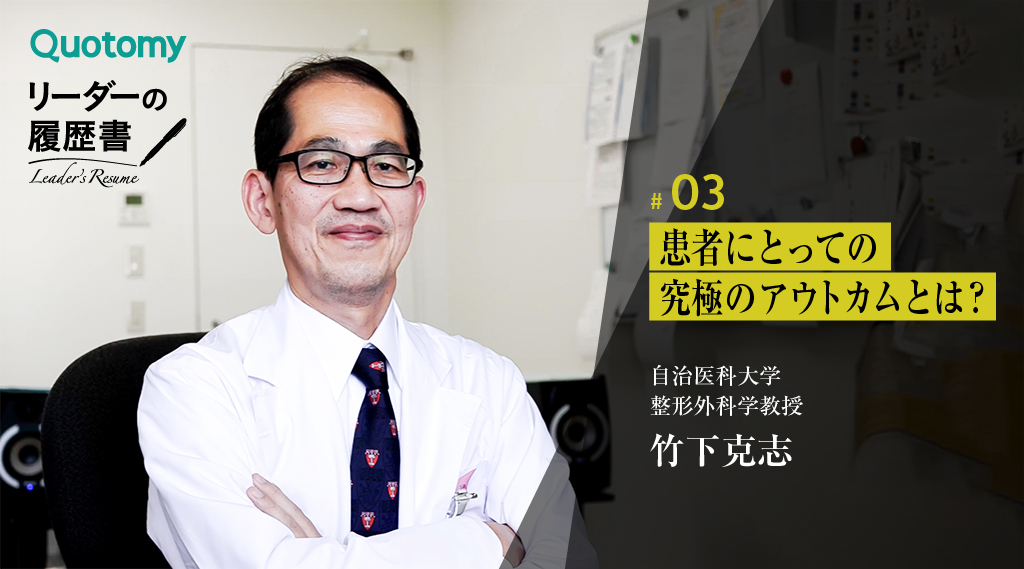
【#03 竹下克志先生】患者にとっての究極のアウトカムとは?
本編に登場する論文
Diameter, length, and direction of pedicle screws for scoliotic spine: analysis by multiplanar reconstruction of computed tomography
Katsushi Takeshita, Toru Maruyama, Hirotaka Chikuda, Naoki Shoda, Atsushi Seichi, Takashi Ono, Kozo Nakamura
Spine (Phila Pa 1976). 2009 Apr 15;34(8):798-803. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181895c36.
Satisfaction and the Correlative Outcomes in Cervical Laminoplasty
Takeshita K, Seichi A, Chikuda H, Koyama Y, Kawaguchi H, Nakamura K
J Jap Soc Spine Surg Rel Res 2009;20:631-636.
Validity and reliability of the Japanese version of the painDETECT questionnaire: a multicenter observational study
Yoshitaka Matsubayashi, Katsushi Takeshita, Masahiko Sumitani, Yasushi Oshima, Juichi Tonosu, So Kato, Junichi Ohya, Takeshi Oichi, Naoki Okamoto, Sakae Tanaka
PLoS One. 2013 Sep 30;8(9):e68013. doi: 10.1371/journal.pone.0068013. eCollection 2013.
── 先生はトラベリングフェローシップにも、The American Orthopaedic Association-Japanese Orthopaedic Association (AOA-JOA) traveling fellowship とThe Scoliosis Research Society (SRS) traveling fellowshipと2回も選出されています。
AOA-JOAの方はアメリカのどの地域を周るルートか決まっているんですよね?
AOAからここに行ってくれってスケジュールを出してくるのですけど、見てみたら全然脊椎に関連する病院がなかった。
「こんなところへは行けない」って文句言ったら、じゃ自分で勝手に行き先を考えろ!と言われてですね、、、。
西海岸2ヵ所と東海岸が3ヵ所だったかな、自分で選んで回ったんですよ。
── そんなことできるんですか?、笑。
他の先生と何人かで一緒に行くんですよね?
そんなことだから、私は一人で行ったんですよ。
現地では「日本からのトラベリングフェローだ」って言ったら色々面倒見てくれましたので、苦労はそんなに多くはなかったですけどね。
脊椎をたくさんやっている施設ばかり回れて良かったですよ。
でも、私がそんなことをしたせいか、候補者が好き勝手に施設を選べないようにトラベリングフェローの規定が変わってしまったと記憶しています。
── 規定を変えられたのですね、笑。
SRSのトラベリングフェローはいかがだったのでしょうか?
あの頃、SRSの中で名城病院の川上紀明先生が色々なメンバーに入られていまして、私が選ばれたのは川上先生にご尽力いただいたのではと思っていて、とても感謝しています。
アメリカに行く3人が各国から選ばれるのですけれど、その年のフェローは私の他に、韓国のJun-Young Yang先生とインドのS. Rajasekaran先生でした。
Rajasekaranと一緒に3週間アメリカを回らせてもらいましたけど、彼の常人を越えた優秀さには参りましたけどね
彼らと一緒に回れたことをいまだに名誉なことだなと思っています。
── 先生から見たRajasekaran先生の凄さは?
まず、プレゼンテーションやまとめ方が凄かったですよ。
普通の人がやるような、論文をまとめただけの発表とは全然違いました。
あと、私にとってインド人の英語は全く理解できない英語の代表なのですけど、
アメリカ人はRajasekaranの英語をほぼ百パーセント理解していて、それにも驚きました。
3-4ヵ所ほど施設を回って、最後はSRS annual meetingで発表してくるというスケジュールでした。
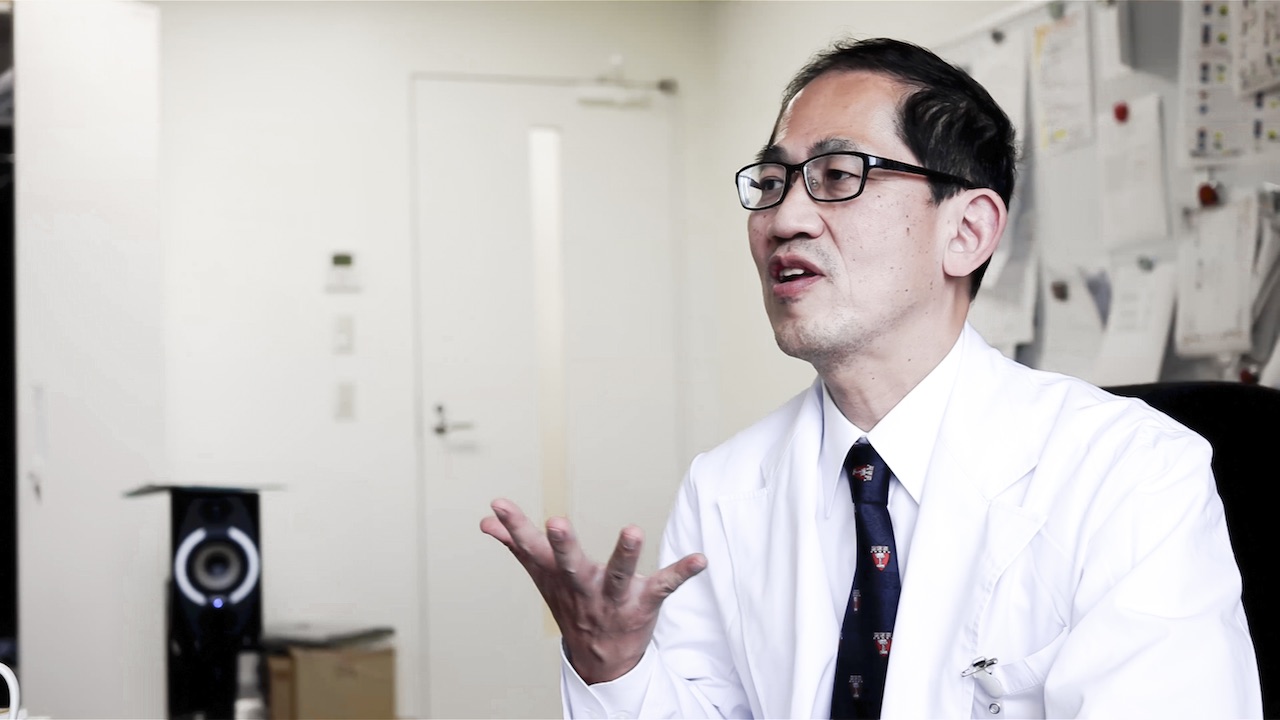
── 今回ご紹介いただく論文は、側弯症に椎弓根スクリューを打つときの長さだったり、凸側は椎弓根が細いということを明らかにした内容でした。
これは当時ナビゲーション支援下での脊椎手術が普及してきたことと関係していますか?
タイミング的には星地亜都司先生が東京大学へのナビゲーション導入に尽力されていた時期でした。
2000年前半って医療訴訟が凄く増えて、当時の中村耕三教授も医療トラブルに神経を使われていた頃でした。
その時に星地先生はかなり厳しい手術をなさっていたので、ナビゲーションは必須だと頑張って、大学にナビゲーションを持ってこられたわけです。
それでナビゲーション支援下脊椎手術の非常に良い仕事をなさってきたわけで、私はそれを側弯症に応用したということです。
ナビゲーションで画像をみていくうちに、もちろん上位頚椎とかも大変な手術ですけど、劣らず側弯症手術は難しいってことに気がつくわけですよ。
実は私が出す論文よりも前に丸山徹先生が側弯症患者の大動脈って結構危ないよっていう論文を出されていました。
前方手術でKeneda deviceやると、ちょうど反対側に大動脈がいるんだっていう内容を、非常に聡明な方でパっと見抜いて、すぐにスパインに出されたのですね。
その頃、ヨーロッパからもナビゲーションで調べてみると脊椎にいれるスクリューが危ないよという論文が出はじめていました。
私は、側弯症患者さんの椎弓根スクリューに関して、せっかくナビゲーションもあるのでより精度の高い研究しようということで始めた研究です。
── 実際ナビゲーションがない時代に側弯症手術のプランニングってどうやっていたのですか?
今でもナビゲーションを使わない施設もあると思いますよ。
特に経験症例も多くない先生の場合は、術中透視装置を側弯の回旋にあわせて傾けることで、各椎体の正面像を出したり工夫しますね。
あとは、マーカーを入れて術中写真で確認したり、そういうのでやってたんですね
そういえば、留学したときのサンフランシスコのUCSFチームとかは、ナビゲーションが3台持ってましたけど、使ってるのはレジデントだけでしたね。
彼らは出来高制なので、そんな時間がもったいないことはやっていない。
Lenke先生のように何十万本も椎弓根スクリューを打っていたり、もしくは名城病院ぐらいたくさんの側弯症手術をやっていれば、大抵の普通の特発性側弯症ではナビゲーションを見なくても眼をつぶっても入るくらい経験しているところもあるんです。
── 同じ時期に側弯症患者では椎体と大動脈の位置関係が動いているから気をつけようという内容の論文も出されています。
この頃は凄いナビゲーションを使って色々調べていたのですね。
ナビゲーションを中心に色々やっていましたね。
実はナビゲーションのソフトウェアって解析用には使えなくて、あれでは全くできないです。
あのデータを解析ソフトに入れてやらないと駄目で、解析にもっていくとなるとデータの数も10,000以上とか入力しないといけなくて、、、一生懸命データ入れてやってましたね。
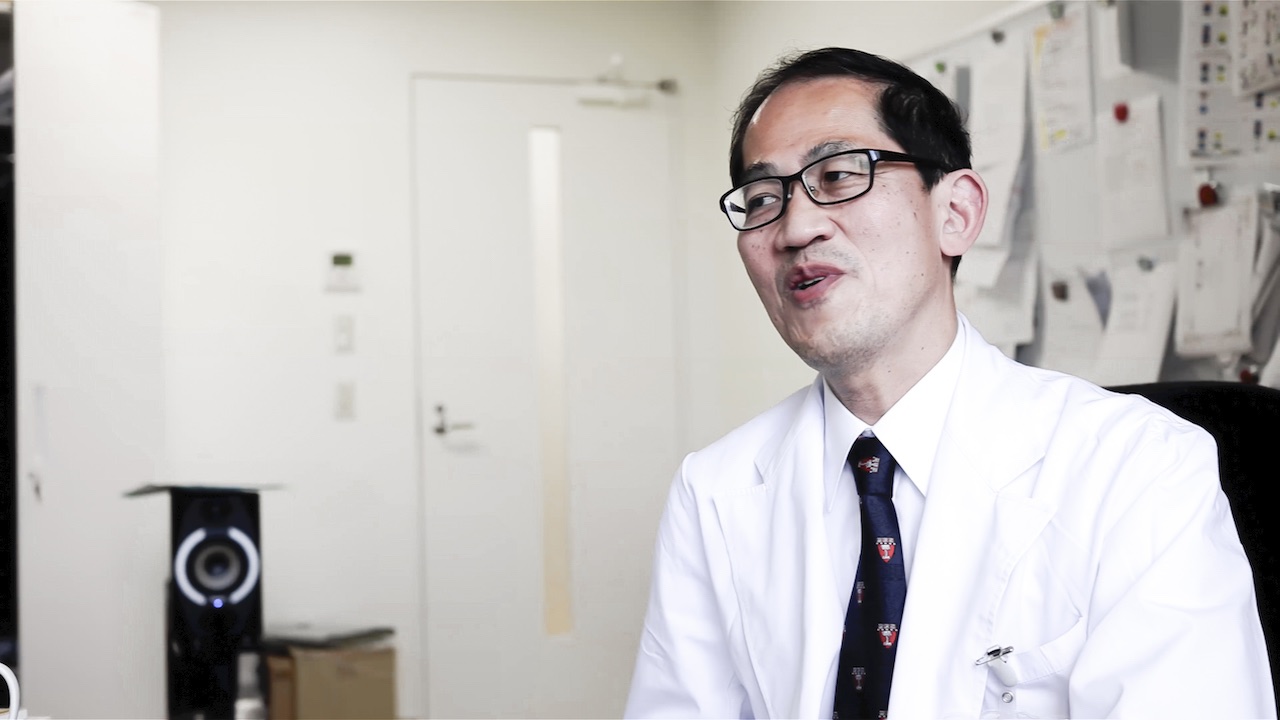
── もう1つ選んでいただいたのが満足度の研究です。
そうですね、この後に大谷先生も続けて論文にしてくれましたよね。
アウトカムの研究をしていくと、究極のアウトカムってやっぱり満足度だって気が付くわけです。
実は満足度の研究をみていくと、病院の駐車場が高かったっていうだけで不満になる人もいるのでなかなか難しい、笑。
ただ手術に限っての満足度をみていくと、最後は痛みと機能の話に行きつくのです。
最近はそういう見方をする先生も増えてきたような気がしますが、もともと整形外科医が大事にしていたのは機能外科です。
圧迫性脊髄疾患では神経を除圧して神経機能を上げることを目指していました。
でも、それだけだとだめで、痛みと神経機能の両方を気を付けることが大事です。
機能をよくしても痛みがよくならないと患者さんにとっては不満足で意味がない。
我々は2つを目標にしなくちゃいけないんだって自分に気がつかせてくれた論文でした。
── 先生は痛みに関する研究も多いですよね。
そうですね、松林嘉孝先生の論文は色んな意味で嬉しかったです。
痛みの世界の研究って良い基礎研究が山のようにあるのですが、整形外科で痛みの研究をするのは結構実は難しいです。
痛みの研究って奥が深くてですね。
当然やることがたくさんあるのですけど、整形外科医が何をやるかとなると一気に良いネタを見つけるのは難しくなる。
例えば、福島医科大学みたいにfunctional MRIを撮ったりとか、くらいですか。
私は運動器疼痛学会に入らせてもらって色んな先生の活動を見ていますけど、結構難しいです。
その中で、神経障害性疼痛を診断するpainDETECTに関する今回の論文は、整形外科医が出した数少ない役に立つ痛みの研究だと思っています。
The painDETECT questionnaireの日本語版をだしていた住谷昌彦先生に「これ非常に良いアウトカムだけど、妥当性やった方がいいんじゃないの?うちと一緒にやりませんか?」って言ったら、二つ返事で一緒にやりましょうって言ってくれました。
研究をデザイン組んでいく中で、若い先生を育てることが必要になってきていて、松林先生に声をかけた。
そしたら、彼もしっかりやってくれたので、そういう意味でも非常に嬉しかった。
── 素晴らしいですね。
ちょうど神経障害性疼痛の治療薬がでたころで、皆がすごく頼りにした論文だったと思います。

── 東京大学の准教授になられてから、自治医科大学の教授に就任されます。
この頃の想いを教えてください。
そうですね、異動先には私と一緒に仕事をしてくれる新しい仲間がいます。
その彼らとどうしていくかっていう、リーダーとして考えていく部分が凄く増えました。
ますます責任が重くなりましたね。
── 教授になった際に東京大学から誰か引き連れていくって考えはなかったのでしょうか?
東京大学整形外科のしきたりで、基本は誰も付いていかないと昔から決まってることなんですね。
最初から連れて行った例はないんじゃないかな。
もちろん途中どうしても必要があったら引っ張っていっても良いと思うのですけど、昔から東京大学はそういうことをあまりしないですね。
── 最初は大変だったと思うのですけど、ご苦労された点はありますか?
自治医科大学に星地先生がいらして際に、かなり多くのことを作り上げていらしたので、苦労はほとんどなかったですね。
自治医科大学の先生も非常に優秀なので、私の方が学習させてもらっています。
実は自治医科大学の医師は内科系の研修をしているので、普通の整形外科より視野を広めに持ってるという特徴があると思います。
そこは非常に今の時代に大切なことで、患者がフレイルだったり色んな内科疾患などの併存症をかかえているので、単に運動器評価だけでは済まなくなってきています。
私は、この時代の一番のポイントは認知症だと、この2-3年ずっと言ってきています。
そういう患者さんたちを診療するなかで、整形外科だけの修行でやってきている人よりも、内科全体の経過も診ることのできる医師の方が違いが出せるので、その辺りを自治医科大学の強みにできるんじゃないかなと思っていますね。
── 竹下先生が考えるリーダーシップとはなんでしょうか?
今回のインタビューでAOの授業とかCrawford先生の話なんかもありましたけど、理想はディスカッションで色んなことを決めていくスタイルだと思います。
けれども、決まるまでに時間がかかる可能性があるのと、やっぱり日本人がディスカッションに慣れていないので、難しさがあります。
きっと多くの医局で、教授が決めておしまいという物事の決まり方も多いのではないでしょうか。
医局員もどっちかって言うと、「教授どうします?」的な感覚で聞く姿勢も多い。
その点は変えていきたいなぁと思います。
リーダーシップと言っても引っ張っていくよりは、上手く調整したり、人の内面から出るような部分をいかに出させるか、そういうリーダーシップを目指していますね。
── リーダーが正解を教えるスタイルからの脱却ですね。
そういうことですね。
── 先生の今後の目標について教えてください!
今は病院とか学会の仕事が忙しくて、個人的にはなかなか微妙な難しい時期です。
外科医としてできることが限られてきている。
例えば、学会などの仕事が少なくなったら、また外科医の世界に戻るのかな。
それもありだけど、むしろ別の世界に行くのも良いのじゃないかな、って気が最近しています。
── 別の世界というのはどういう場所でしょうか?
大学や急性期病院ではないところで活躍する、という意味ですか?
もちろん医師本人の資質とか能力で全然変わると思うのですが、そういう選択肢も作らないといけないと思うのですよ。
日本は人口が減るので患者さんも減りますから、最初は病院淘汰から始まって、その後に医者の淘汰が始まるかもしれません。
今は、各病院で年配の先生がたくさん手術しているじゃないですか。
患者需要が多いうちは取り合いにはならないのだけど、今後5-10年で確実に患者が減ってきます。
そういう環境になっていくのに、あまり年配の人ばかり手術しているのはどうなのかなぁと最近思います。
手術自体はなるべく若い人にバトンタッチして、年配の方はいわゆる調整役になるとか別の世界へ入っていく方が、今後の整形外科医のライフコースとしては良いのではという気がしますね。
── 最後は視野の広がるお話でした。
竹下先生、ありがとうございました!
こちらの記事は2021年11月にQuotomyで掲載したものの転載です。