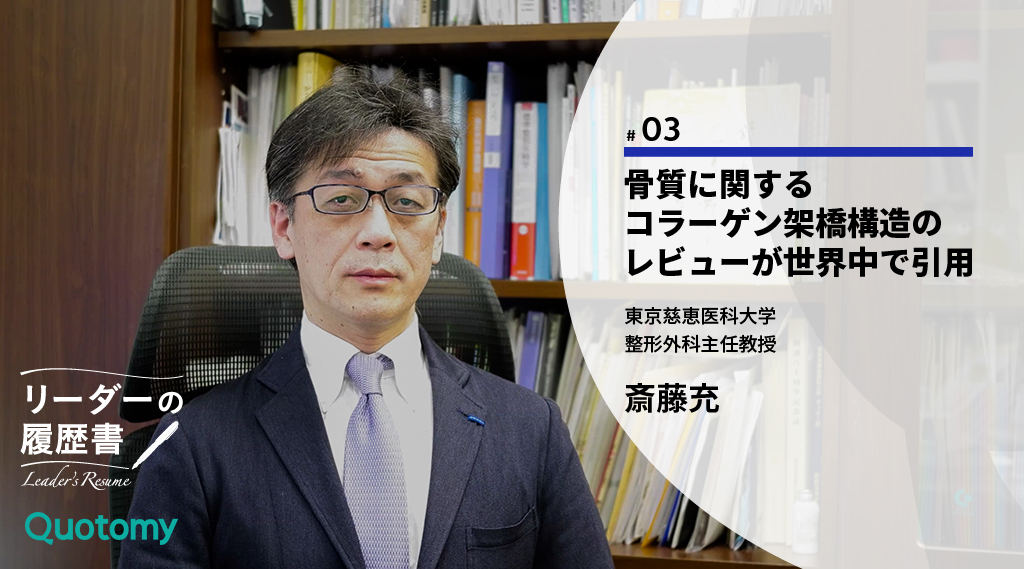
【斎藤充先生 #03】骨質に関するコラーゲン架橋構造のレビューが世界中で引用
本編に登場する論文
Collagen cross-links as a determinant of bone quality: a possible explanation for bone fragility in aging, osteoporosis, and diabetes mellitus
M Saito, K Marumo
Osteoporos Int. 2010 Feb;21(2):195-214.
── 今回ご紹介いただく論文は本当に凄いですね。
このOsteoporosis International (OI)のレビュー論文って、誰かから依頼が来るものなんでしょうか?
完全に人との巡り合わせです。
私がOIに人の骨の分析データを出した頃に日本で国際学会が開かれました。
その中のシンポジウムがあって、その座長がメルボルン大学のEgo Seeman先生という、IOF(国際骨粗鬆症財団)の大御所でした。
彼が私の発表を見て声をかけてくれたんです。
「お前、骨質,コラーゲンに関してレビュー書いたことあるか?」って。
「査読したことはあります」って言ったら「そのレビューじゃねえよ(笑)」と。
それからしばらくしてOIから依頼総説を書いてくれって連絡が来ました。
私はとにかく多くの自身のデータと共に、この領域の論文の殆どを読んでいたので、20年ぐらいの積年の思いがありました。
コラーゲンはこういう機能があって、本当はコラーゲンの翻訳後修飾の全てを評価しなきゃいけない。
コラーゲン架橋でも未熟・成熟架橋や老化架橋であるAGE、、、この全部を同時に評価しなきゃだめなのに、どうして皆それぞれお互いの得意な分野しかやらないのかなと思っていたので、私はその全てを分析する技術をもっていましたので、、それを全部余すところなく書いてやろうと思って。
結果、世界のそれぞれの分野の大御所専門家から「なまいきに」的な結構辛辣な査読結果がきました。
── インバイテッドレビューでも、ちゃんと査読が入ってくるんですね?
3,4人の先生がもの凄い数のコメントを書かれて、、、まあ、リジェクトにはされなかったんです。
それは、私の考えとポリシーを新しいトレンドとして受け入れてくれようとして、AGEとAGE以外のものをちゃんと評価して見ていく必要があるんじゃないかと感じてくれたのだと思います。
レビュアーから言われたコメントに対して、私が持ってる過去の論文やデータのストックから書き足していくと、どんどんページ数が増えていくんですね。
最終的に20ページぐらいの大作になったんですけど、まあ自分の積年の思いを全部そこで述べられたと思ってます。
Ego Seeman先生はメールの最後にEgo Seemanって書かず、Eしか書かない。
論文通りましたって言ったら、もう一言
「Well done, E.」 って書いてあって、それで終わりました。
この総説は、2010年にpublishされましたが、今日までに、776の国際ジャーナルの論文に引用されています。そして、アジア人として初めて、OIの全論文の中で最も世界で引用されたtop5論文賞を、のべ6年間で2回受賞しました。その他の英文原著もそれぞれ、250〜420の引用を受けており、相当数の追試もうけ妥当性が確かめられたと思っています。
それ以降も、国際シンポジウムで講演する機会が与えられ、Markus J Seibel先生,Pierre J Marie先生,Roland Baron先生とも交流が広がりました。
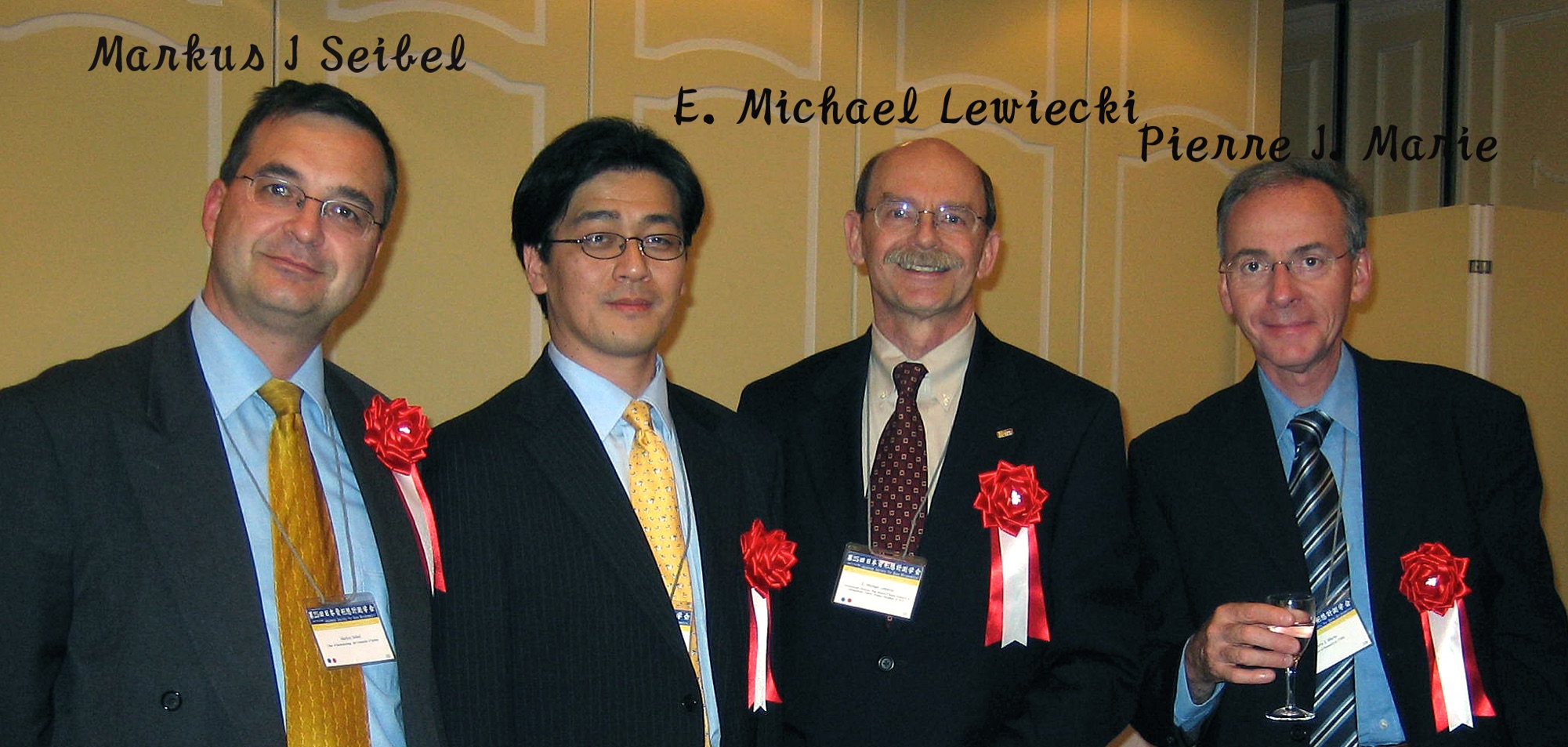
世界のフィールドに入るスパイクとユニフォーム
Seeman先生から、後日メールが来て「君はもう世界のフィールドに入るスパイクとユニフォームはそろえたんだから、これからはもうそのフィールドで戦いなさい」と,武者震いがするような言葉をかけて下さいました。
その後もよくメールをいただいたり、今でもやりとりをしています。
Seeman先生はもともとオーストラリアの出身なので彼自身も業界の中で認めてもらえるために相当苦労されたようです。
頑張ってるけどなかなか世に出てこない人たちを救い上げるのが大好きらしくて、私みたいにひとまず何か頑張ってるけど、論文も書いているけども、なかなか引き上げられない坊やがいるって、ちょっと気にかけてくれたんだと思います。
もう本当に出会いですね。
── 素晴らしいですね。
依頼総説を書いた後は色んな依頼が増えてくるわけですか?
そうですね、依頼総説が凄い増えました。
アメリカのDavid Burrっていう先生がいて、Orthopedic Research Society(ORS)の会長もやられておりましたけど、その方がライバルでありながら凄い先生で、やり取りをするようになりました。
論文を出した時、このレビュアー多分Davidだなって思うようなこともあったり。
その先生と仲良くなってから、また依頼総説をまわしてくれるようになったり。
海外の先生たちは出身校とかそんなことは全く気にしてなくて、何をやってるかに重きをおいています。
急にKarl Insogna先生みたいにメールが来たりとか、David Burrみたいにメールや学会で交流して、もうファーストネーム呼び合おう!みたいな事を言ってたり、ですね。
日本の学会はどうしても、先生はどこの先生のところで留学したんですか?って、そこを最初に気にしてきます。
論文書きだしてジワジワ認められるようになりましたけれども、そこは日本と海外の先生達との違いは大きく感じました。
── この頃はラボも大きくなっていたのですか?
この2010年の総説の時も、実は全部実験を私一人でやってました。
糖尿病ラット108匹のデータをOIに論文出した時も全部自分で解剖して、採血して、解析しての繰り返すですね、それが当たり前。
自分がやった分しか物事は進まないっていう状況だったのが、しばらくしてから少しテクニシャンが週に2回ぐらい来てくれる人を雇ったり、大学院生が少し増えていきました。
まあ当時は一人で全部だったので、ふつうに泊り込んで、寝袋でうなぎの寝床みたいなところにいつも寝てました。
最初、新聞紙で寝てたんですけど、若い先生が気にかけてくれて寝袋をプレゼントされたんです、笑
── ファーストオーサーでやっていたことで、総説の話も良くくるようになったということでしょうか?
最近やっと、論文を書いてなんぼ、という教育が行き届き、教室の中でも自分の分野だけではなく皆が論文を書いてくれるようになりました。
今の状態はすごくいいんですが。
当時はファーストオーサーであり、同時に指導者もいないのでコレスポンディングオーサーも自分でした。
やっぱりコレスポンディングオーサーがあると、世の中の人はそういう目で見てくれます。まあファーストオーサーが重要では今ないと思います。
基本はコレスポンディングオーサーが多いとその人が親分なんだな、と世の中見てくれるからそれが大事じゃないかと思います。

── すごい論文を読まれている斎藤教授ですけども論文知見をストックするのは難しいことはないのでしょうか?
そうですね、当時は私が英語がベラベラしゃべれるわけではないので、最初から最後まで息をするように読めることは無く、相当つらかったですね。
画面でPDFを見てると頭に入ってこない世代なので全部印刷してます。
それで論文の表紙にポストイットにNがいくつ、サンプリングは何、統計が云々、解析した項目は何々、って全部書きだして全部貼っておきます。
論文中の良い表現は、ポストイットと別に、ワードファイルで表現シリーズというファイルにしてます。
ちょっと主張したい時の言い回しとか、レビュアーなら来た時にこう答えようとか、そういう時に便利です。
── 先生の考える、医師にとって論文を書く意味って何でしょうか
ある人から言われたことですが、
目の前の患者さんを助けるのは当然できると思うのですが、自分がやってみて良いと思ったことを地球の反対側にいる先生は全く知らないし、そのアイデアを使ってくれる事は絶対ないわけですよね。
でも、何かおかしいと思った事を論文化して、それが追試されれば、ある程度の流れが変わって世界中で考え方が変わる。
そうすると自分の目の前の患者さんだけじゃなくて、全く知らない先生が目の前の患者さんに対してそれを救う一つの手だてとして自分のアイデアを使ってくれるようになるわけですよね。

研究が患者さんを救う。
その実現には、論文化するという、知らない先生がそれ知見を応用してくれる第一歩が必要です。
その結果が追試で確認されなければ、普遍性が無いことがたまたま論文になったということもあるでしょうし、普遍性があれば皆が再現してくれます。
それが英文論文にするってことの重要性だと思います。
学会発表だとか学会賞っていうのは何のエビデンスにもならないので、とにかくインパクトファクターなんてついてなくてもいいからpubmedに掲載される、ちゃんとしたジャーナルに載せなさいって。
それがあれば逆に学会発表なんかしなくてもいいぐらいだ、って私は思っています。
学会発表よりも論文化することが世界の患者さんのためには役に立つ。
自分がやってることが他人に引用された時の嬉しさも味わうことができます。
私のOIの論文は総説のなかで最も引用された、top5論文に2期連続6年間選んで頂いたのですが、今は約800件ぐらいの論文に引用されています。
OIのインパクトファクター上昇に貢献したと思います、笑
── ほんと、そうですよね。
世の中にちゃんと還元されていくための論文化の重要性は、自分でその景色は見てきましたので、皆さんに伝えたいです。
もう一つ、整形外科医だと医療機器メーカー等にチヤホヤされて講演とかに呼ばれたりしても講演スライドに自分の英文一つない状態で話してるのは、ただ医師免許を持ったメーカーの人と同じで、周りは冷ややかに見てるぞ、と。
論文書かずに技術だけ教えて、他人が勝手にどんどん論文化してって自分は追い抜かれてく。後で気づいたって遅いから、とにかくそれを論文化しなさい。
教授になった2020年4月に教室の若手にも伝えました。
やっぱり自分の名前の論文が講演スライド内にあると他人の見る目は変わるし、その後にシンポジストの席が用意されいたり、他人から信用してもらえます。
発表とか講演よばれてるのは利用されてるだけの可能性があるから、それに気づいてくださいという事ですね。
この世の中、形にした者、論文書いた者勝ちですから。

── 今回、研究でお忙しい斎藤教授がたくさん手術もされているので驚きました。
大学院の時は全く手術してなかったんですけど、その後、臨床にもどり、特に国立宇都宮に行った5年半で股関節と膝関節の外科の経験を積みました。現在は膝の人工関節術が主です。大学本院で行っている人工膝関節の総数は年間180から220膝ですが、その内、100から120膝を執刀しています。特に、両側人工膝関節手術を年間50症例ぐらいしています。
大学倫理員会を通して手術でとれたサンプルも基礎研究のデータとして分析しています。
── 将来の医療につながる事だから患者さんも喜ぶと思います。
最初にスポーツドクターになるという目標があって今はスポーツにあまり関係ないことをやられていることについてエピソードありますか?
暁星中学高校の林監督からスポーツ医学はどうなっちゃったんだ?お前!?って毎回電話がくるんですけど、、、笑
東京慈恵医科大学整形外科教室の中でちゃんとしたスポーツの先生がいるし、鹿島アントラーズのドクターやっている東京医大の山藤崇くんとかはみんな暁星サッカー部の仲間ですから。
あと、ついこの間まで、5,6年間湘南ベルマーレのチームドクターをうちの大学がやっていたんですね。
それも暁星の縁が元でした。
私が高3の時に、高1で一緒に全国大会に出たフォワードの大倉智君が湘南ベルマーレの社長になっていて、ですね。
東京慈恵医科大学にそのドクターの仕事を頼んできてくれて、ベルマーレのチームドクターをやる事になったのです。
それはもう暁星でつちかった繋がりで、まあやっと少しは、林監督の思いに貢献できたかなと思いました。
こちらの記事は2020年12月にQuotomyで掲載したものの転載です。