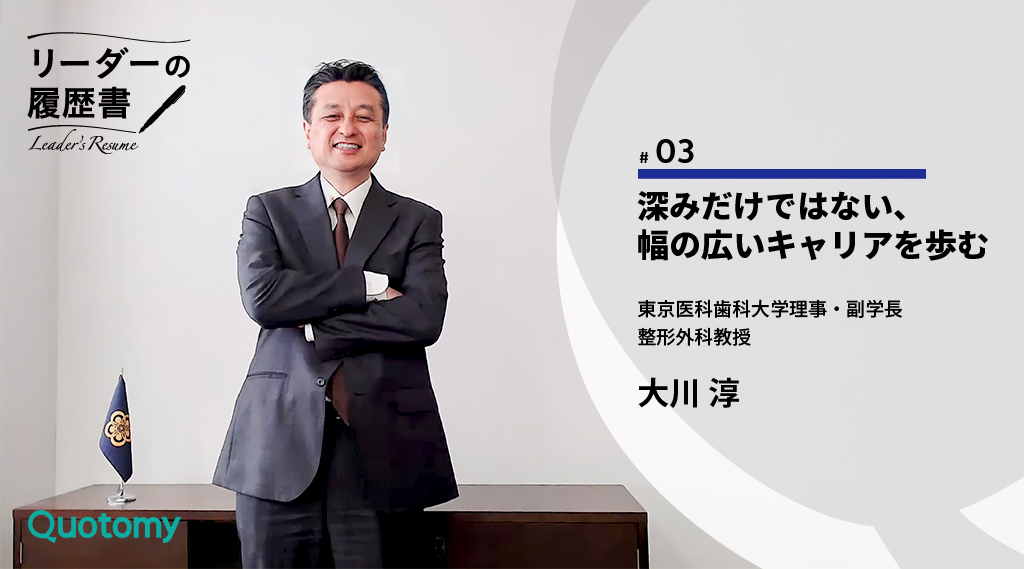
【#03 大川淳先生】深みだけではない、幅の広いキャリアを歩む
本編に登場する論文
Risk Factors of Nonunion After Acute Osteoporotic Vertebral Fractures: A Prospective Multicenter Cohort Study
Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoichi Ichimura, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa
Spine (Phila Pa 1976). 2020 Jul 1;45(13):895-902. doi: 10.1097/BRS.0000000000003413.
── 今回ご紹介いただく論文は骨脆弱性椎体骨折(以下OVF)に関する論文ですね。
OVFの保存治療ってどうやればいいか?って決まってないじゃないですか。
以前、日本整形外科学会のプロジェクト研究で、永田見生先生がOVF初期にどのコルセットを付けるべきかっていうのをランダム化比較試験でやったのです。
研究デザインをみてみると、1群が15例ぐらいで3群に振り分けているのです。
前回の後縦靭帯骨化症の話と一緒で、15例では何か分かるのか?
やはりもう少しハッキリものが言えるエビデンスを出させなきゃいけないですよね。
そう思っていたところで、当医局の加藤剛先生(青梅市立総合病院整形外科部長)のOVFに対して初期固定は何をするべきかという研究がAMEDプロジェクトで採択されましたので、13大学が参加する多施設共同試験を立ち上げました。
大学病院に新鮮なOVFは来ませんので、関連病院の先生方にご協力いただきました。
65から85歳までの女性で、Th10-L2レベルの初回OVF、というかなり厳格な基準で症例を集めて検討しました。
── 前回の後縦靭帯骨化症と異なり研究班があるわけではありません。
参加施設を集めるのはどうやったのでしょうか?
学会の中で声を掛けたりするのでしょうか?
そうですね、参加して頂くには、とにかく教授に納得していただかなければいけない。
こういうことを進めるには、本当に教授同士のパーソナルコミュニケーションが大きい。
個別にお願いしてみると、皆さんモヤモヤと同じ思いを持ってるんですよ。
誰かが声をかけてやらなくてはいけなくて、それをやらせて頂いたってことになりますね。
あと、多施設研究を可能にしたのは、ちょうどその頃、ランダム化比較試験の割付けがインターネット上で可能となるシステムができました。
昔であれば封筒でやるとか、サイコロ動かすとか、いろんなことがありましたけど、ようやくインターネット上で瞬時にランダム化割り付けが出来るようになった。
そういう時代性にも合ったのですよね。
── 気運も高まっていたし、テクノロジーの進化にもタイミングが合ったのですね。

── 2020年には東京医科歯科大学の理事・副学長となられます。
COVID-19で大変な局面に突入した頃だと思います。
新型コロナウィルスが騒がれ始めた2020年4-5月に、学長の判断で、東京医科歯科大学では重症患者を引き受けるということを決めました。
その頃、大きな問題だったのは清掃です。
コロナは凄く怖い病気で、感染すると命に関わるっていう情報が先行してしまっていました。
すると、清掃業者がレッドゾーンに入りたがらなくなってしまったのです。
ICUに重症患者が入った時にどうやって環境を整えるのか、、、
看護師さんたちは非常に一生懸命に患者さんを診てくれていたので、看護師さんたちが環境整備するというのは少し厳しい。
そういう状況の中で、では誰か清掃をするか。
実は当時、手術も止めてしまっていたので、外科系医師は少し時間に余裕ができていたのです。
そこで、うちの医局長に「ちょっと掃除やってくれないか」って頼んだところ、そういう背景をよく理解してくれて、すぐに組織化してくれた。
まずは自分たちでPPEの着脱から学んで、それを教材にして研修医まで巻き込んでICUの清掃を始めてくれた。
非常にありがたかったですね。
これは実際にICUをキレイにするという実質的な問題解決以上に、組織として医師が清掃を請け負うということ自体にインパクトがありました。
その姿を見た看護師さんはやっぱり自分たちも頑張らなきゃって思いも当然でてきて、周りの医療職へ多大な影響がありました。
「なんで私たちだけが、、、」というような雰囲気は、その頃に無くなったような気がしています。
── 素晴らしいエピソードですね。

── 医療者においても働き方改革が進んでいくことが求められています。
また、多様性のある生き方が認識されていたりします。
先生のような教育的立場の方から見て、医師のキャリアはこれからどのような形になっていくでしょうか?
昔から「医師はこうあるべきだ」とか「自分はこれを目指してる」っていう考え方がありますよね。
私自身は、そのような教授を目指してキャリアを歩むという考え方とは全く違う生き方をしてきました。
研究面で高みに登った方もいらっしゃれば、私みたいに幅だけは負けないって言う医師もいて良いと思うんですよ。
私は高みとか深みはもう全然なくて、研究にしても臨床にしても全て中途半端で、つまみ食いした、みたいな形になってます。
けれども、幅に関しては、ここまでやってきた脊椎外科医は多分なかなかいない。
医療安全もそうですし、医学教育もそう。
結果的にそのキャリアから、いま日本専門医機構の理事にさせていただいています。
最近は、私みたいな人間が生きていけるような、少し広がりを持った医学界になったのではないかな。
私が若かった時代は、自分がヘテロな存在だったと思います。
今は、こういうインタビュー記事を医師が立ち上げているのも、あまり違和感がないですよね。
以前はそういう雰囲気がなくて、あいつ外科医としてどうなの?とか思われていたと思う。
広がりをもった医師も生きていける、そして評価される時代になったと思いますよ。

もう一つ、若い先生に言いたいことがあります。
私は運命論者だと言い続けていますけど、与えられた仕事をしっかりやっていく、それが大事だと思っています。
若い先生方は、ともすると、「自分の目標と違う」とか「やりたいことと違う」と考えてしまうことが多く、そういう議論が時々出てきます。
少し前だと、たとえば配膳や採血は研修医がやる仕事じゃない、とか。
私自身は、それは少し違うだろう、って思ってるんですよ。
採血だって点滴だって、看護師さんたちができなければ最後に頼まれるのは医者なんです。
医者であれば最終的に何でもできないと困るのでは?とずっと思ってるのですね。
その辺りのことを若い先生方が十分にわかってくれていないと感じる場面がまだあります。
別に病棟だけじゃなくて、手術室だったり研究のデータ集めだったり、色々な場面でも同様です。
目の前のことを淡々とこなしていくことで、自分の力がついていきます。
上の人間は、嫌がらせしているわけでもなんでもなくて、必要だからお願いしているし、その人にとっても将来的に役に立つと分かっていてお願いしていると理解して欲しいと思います。
── 与えられたことをキチンとこなせないと評価もあがらず、良いチャンスも巡ってこないかもしれません。
実際、その人の力になるんです。
発想だったり、活躍する場だったりっていうのは、他の人から与えられた機会を全部否定してたら辿りつかないことだと思います。
先生だって嫌々ながら論文を読んでいたから、こういうサイトを思いついているわけでしょう?
ですから、与えられたものをキチンとこなさないと、せっかくのチャンスを失ってるじゃないかな?と思います。
── 大川先生のキャリアのお話、とても勉強になりました。
ありがとうございました!
こちらの記事は2021年7月にQuotomyで掲載したものの転載です。