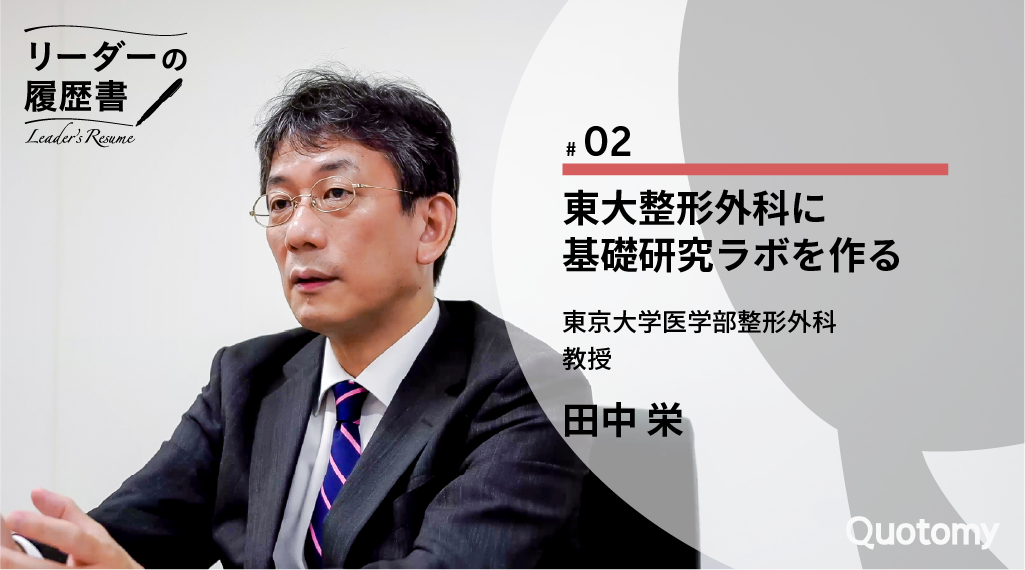
【田中栄先生 #02】東大整形外科に基礎研究ラボを作る
本編に登場する論文
Involvement of receptor activator of nuclear factor kappaB ligand/osteoclast differentiation factor in osteoclastogenesis from synoviocytes in rheumatoid arthritis
H Takayanagi, H Iizuka, T Juji, T Nakagawa, A Yamamoto, T Miyazaki, Y Koshihara, H Oda, K Nakamura, S Tanaka
Arthritis Rheum. 2000 Feb;43(2):259-69.
東大整形外科に帰ってきて
── 東大病院へは関節グループの整形外科医として戻ってきたのですか?
いえ、前回お話ししたように膝診だったので、膝診として大学に戻ったのです。
けれど、関節診(注:東大整形外科教室の炎症性関節疾患診療グループ)の織田弘美先生から、「アメリカで基礎研究やっていたなら関節リウマチの研究もしてみたら?膝と半分半分でいいから!」と上手いこと騙されて(笑)、最終的には関節診に属するようになりました。
その後、黒川高秀教授より「大学院生の面倒をみてほしい、東大整形外科に基礎研究のラボをつくってくれ」というお話をいただき、3名の大学院生と研究を始めることになったんです。
── 唐突な話で、頼まれた方は大変そうです笑
そうですね。けど、私も基礎研究はやりたかったので、「わかりました」と快諾しました。
たまたま大きなグラントも取れて、いろいろ設備を整えることができました。
ラボの方向性としては、アメリカ時代のsrc遺伝子の研究からは離れ、違う切り口で基礎研究を始めたいと思っていました。
そこで、血液内科教室で分子生物学やウイルスベクター作成の指導を受けながら、3人の大学院生と一緒に基礎研究のラボを立ち上げていきました。論文の抄読会にも参加させていただくなど、当時の血液内科のチーフであった平井久丸先生(故人)には大変お世話になりました。

── それまで東大整形外科教室が基礎研究をやっていなかったことを知りませんでした。
それまで大学院生が基礎研究をするときは、私のように他の研究室に委託されていました。
けれど、黒川教授は東大整形外科教室の中に自前で基礎研究ができるラボを作りたいという思いが強かったようです。
── 今回ご紹介していただく論文は、大学院生だった高柳広先生が1st authorの論文ですね。
破骨細胞の分化に重要な分子を探そうと思っていたのですが、残念ながら自分たちでは見つけることができなかったんです。その分子が今でいうRANKLだということがわかったのが1997年から1998年にかけてのことです。
そこで、RANKLが病的な骨吸収・骨破壊にも関係しているのではないかと考えて、関節リウマチ滑膜組織におけるRANKLの発現を調べてみた。実際関節リウマチの炎症滑膜にはRANKLが強く発現しており、破骨細胞の誘導にも関与していた。
簡単にいうとそういう論文です。
同じようなことを考えているグループも多かったので、非常にcompetitiveなテーマでしたけれど、高柳先生たちが頑張ってくれて論文にすることができました。

── これまでの基礎研究から、臨床に繋がるような論文が出たわけですね!
たしかに、それまではマウスを使った基礎研究が多かったです。
基礎研究で明らかになったことが、関節リウマチ患者さんの中で実際に生じているのだということがわかった。
そういう意味で、自分にとっても思い出深い論文です。
その後抗RANKL抗体は関節リウマチの骨破壊治療薬として保険適応になるのですが、その元になった論文だと思います。
── 昭和大学時代、アメリカ留学時代と基礎研究をやってきて、東大整形外科で立ち上げたラボでは臨床に結び付けようという方向性だったのですね
いえ、実際は臨床に直結するようなことをしようとは思っていませんでした(笑)。
── えぇ!?
臨床の役に立たないことをしよう!
臨床の役に立たないことをしましょう!と大学院生にも指導してました(笑)。
もちろん、臨床の役に立つことがだめだと言っているわけではないです。
ただ臨床につなげようと考えると、どうしても視野が狭くなるし、逆に真実を見失うということが多々ある。
例えば、前十字靭帯損傷の研究をしようと思った時に、「じゃ、まずは動物の前十字靭帯を切ってみよう」という研究を始めても、それでは何もわからないと思います。ヒトと動物モデルでは病態も違うし。
例えば「靱帯とは何ぞや?」というような、もっとベーシックなところから真実を見つける方が、基礎研究としては面白いし、長い目で見れば臨床にも役立つ重要な結果が得られる。
そういう意味で、「臨床の役に立たないことをしよう!」と掲げて基礎研究ラボを立ち上げたのです。
とはいえ結果的にそのような研究が臨床と繋がったというのは感慨深いことでした。

── 骨代謝分野は臨床に直結するような薬がたくさんでている分野だと思います。治療薬がたくさん出てくるので医師としてはキャッチアップが難しい、とも感じます。
私が研究を始めたのはちょうど骨代謝研究が盛んになった時期で、基礎的な研究が治療薬開発につながるようになった時代でした。ビスホスホネート、抗RANKL抗体、生物学的製剤などといった新しい治療薬がどんどんと開発されました。
多くの薬がたくさん市場にでていますが、本質を理解すれば同じような作用機序の薬剤が多いので、全体像を把握するのはそれほど難しいことではありません。皆さんにはあまり薬剤の数に惑わされないで欲しいですね。
#03に続く
こちらの記事は2020年11月にQuotomyで掲載したものの転載です。