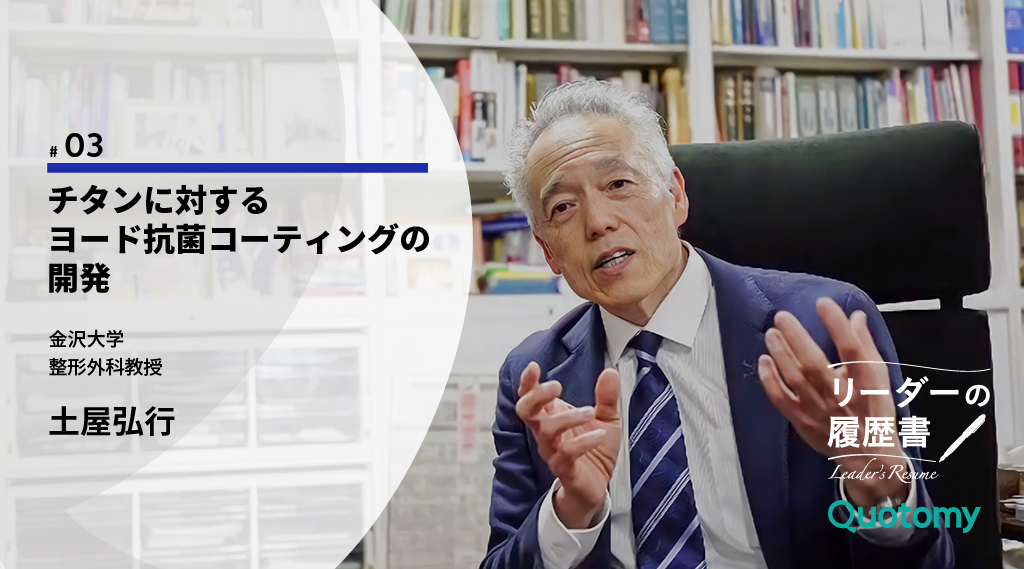
【土屋弘行先生 #03】チタンに対するヨード抗菌コーティングの開発
本編に登場する論文
Innovative antimicrobial coating of titanium implants with iodine
Hiroyuki Tsuchiya, Toshiharu Shirai, Hideji Nishida, Hideki Murakami, Tamon Kabata, Norio Yamamoto, Koji Watanabe, Junsuke Nakase
J Orthop Sci. 2012 Sep;17(5):595-604.
── 最後の論文はヨードでコーティングしたインプラントを使えばいいんじゃないかっていうそういう論文ですね
腫瘍の手術をやってると、すごく感染率が高いわけです。
あとは創外固定やっていてワイヤーやピンを刺していると凄く感染率が高い。
他の整形外科領域をみても、脊椎にしても人工関節にしても一度でも深部感染を起こすとなかなか治らないので、抗菌インプラントは必要だと。
既に銀のコーティングは色々やられてて、骨軟部腫瘍の領域でもドイツのグループが一生懸命やっていました。
われわれも金・銀・銅に注目しました。
ハーフピンで金・銀・銅のメッキをして、抗菌作用があることを確認したんです。
けれども、いずれも毒性が出てしまい、軟部組織の障害を起こすし、骨の細胞にもよろしくない。
そこで、一気に表面の銅とか銀が流出するのでダメだということで、チタンと銅の合金を作成したんですね。
銅とチタンの比率を決めて、、そしたら抗菌作用はあるんですよ。
抗菌作用はあるけど、たった1%銅を混ぜるだけで力学的強度が2-30%落ちちゃうんですよ。研究としては成り立つ。
けれども、実用化することを考えると、柔らかいチタンが更に2-30%力学的強度が落ちちゃうとまずい。
ちょっと諦めムードで次は何をやろうかなって思いましたら、また他の分野からヒントがあったのです。

千葉工業大学機械サイエンス学科の高谷 松文教授が、アルミニウムの表面をヨウ素処理して抗菌性を持たせてるという研究をしてました。
ただ、研究のための研究のような感じで実用化にはかなり道のりが遠く、犬の首輪の抗菌作用にでもしようかっていう話になってたんですね。
それで話をしに行ったんです
「先生、これチタンでできないんですか?」
「整形外科医はチタンをインプラントとして人体に埋め込むんですけど、感染を抑えたいです。ヨウ素をチタンの表面に加工できれば抗菌仕様になるのですよね」と。
共同研究が始まり、チタンの表面をヨウ素加工することができるようになったのです。
そこから、基礎研究して臨床応用して、という同じようなパターンで前進していったわけです。
また他の分野からヒントを得ていましたね、今回は工学部の先生からでした。
まあ、犬の首輪はちょっともったいないかなと思いましてね、笑

── コーティングには凄く技術が必要と伺ったことがあります。
それも金沢大学でやられてるんですか?
メッキと言われる技術の一つです。
英語で言うとコーティングではなくプレーティングあるいはサポーティングっていうらしいです。
これは自分たちには絶対できない技術でした。
北陸地方にあるメッキ工場にお願いして、色んな加工パターンを研究してもらってるという形にしています。
── 巻き込む力がやっぱりすごいですね。
金沢大学発のベンチャー企業も参画していると伺いました。
話してみて目的に賛同を得た方々に協力して頂いているということです。
金沢大学発のベンチャー企業にもお願いして、そこが特許を持って製品化を目指すということにしました。
確実に特許をおさえて実用化に向けて色々行動してるところです。
あと2年ぐらいしたら実用化できるんじゃないかな、という事ですね。
── 色んな人を巻き込んで実用化に向けて多くの課題を乗り越えてらっしゃる!!
アイデアを実用化させるために大切な3つのこと
実用化するためには何をしたらいいのか気づいたのは、教授になったぐらいからですよ。
これまで研究をずっとやってきて、皆さんがあったら良いなと思うアイデアは沢山あるわけですよね。
けれども、大学の研究室だけでやってたら研究でしかない。
本当に良いアイデアと思ったら、やっぱり患者さんのためですから、皆さんがちゃんと使えるようにしないといけない。
それが実用化です。
その実用化のために何が必要か、どんなシステムになってるのか、っていうのは50歳くらいになってから知ったわけです。
なかなか大変ですけども、医療機器であればこういうルート、薬であればこういうルートってのがありますよ。
いろいろなノウハウっていうのは大分わかって来ましたけどね。
── アイデアが凄いって思われがちなんですけど、結局それを実用化できるかって方が大事なのですね。
独創的なものを最終的に実用化するために何が必要かと、ある本で読んだのですが、、、
ひとつは情熱。
あとは、とことん過去を徹底して調べる。
それを理解すると過去にやってないことがわかる。
そして、3番目が一番大事でネットワーク。
色んなネットワークを使って、それが世の中に出せるようにしないといけない。
── なるほど。金沢大学の先生方では厚生労働省に進んでいる先生もいますよね。医局員のキャリアとして官僚って珍しいと思っていました今のお話を聞いて、とても納得しました。
はい、厚生労働省の中の仕組みとかはわかってないと絶対ダメなんですよ。
このルートは勉強しておかなければならない。
結局、ネットワークは大事ですね。
研究とかもそうですが、どなたか認めてくれる人が出てくると一気に道が開けますよね。
自分でアプローチすることもあるでしょうけど、向こう側から近づいてきてくれることもあるでしょうし。
色々なことがありますが、そういうチャンスを無駄にしないという事が大事なんじゃないですかね。
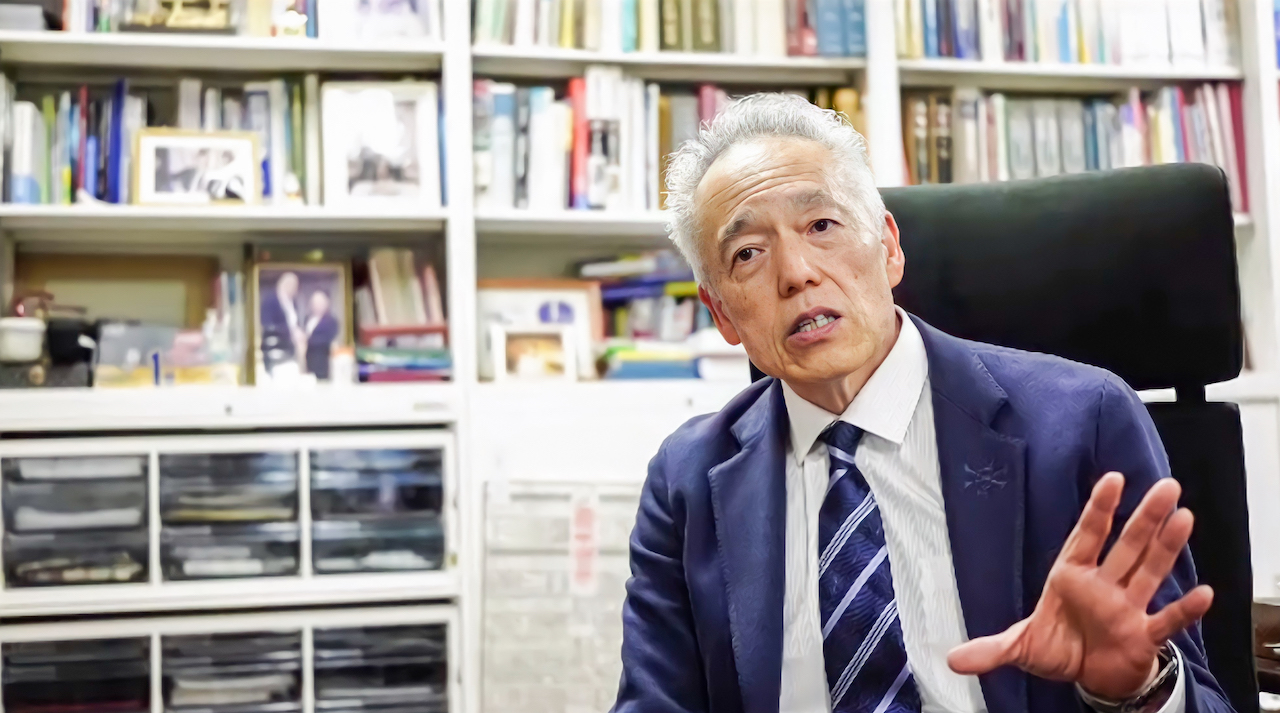
── 金沢大学整形外科の先生方は国際学会で活躍されている印象があります。
特に毎年American Academy of Orthopaedic Surgeons(AAOS)ではたくさんの演題が採択されていますね。
はい、ここ5年間はずっと26-27演題ほどの数がAAOSに採択されています。
凄い数ですよね。
年中行事という感じで、国内の日本整形外科学会には3-40演題、AAOSには20演題以上は採択されるように頑張るぞ、と。
あとは各専門グループの国際学会があったりするので、国際学会への出席回数はかなり多いんじゃないですかね。
AAOSはその中でも一番メインの学会に据えているので、とにかく全員出すように指導しています。
── 新型コロナウィルスの影響で準備は相当大変だと思いますが、主催される2021年の日本整形外科学会も楽しみにしています。
はい、今年の日本整形外科学会はハイブリッド開催と決定しています。
ですが、現地に来れる人は是非来てください。テーマは、“伝統と創造―夢・挑戦・実現”です。
オンサイトでこそ味わえる部分がいっぱいあります。
やっぱり人と人との交流っていうのも大事な学会の要素ですので、5月の東京で新型コロナウィルスが鎮静化されていることを期待してます。
── 土屋教授、ありがとうございました。
こちらの記事は2021年2月にQuotomyで掲載したものの転載です。