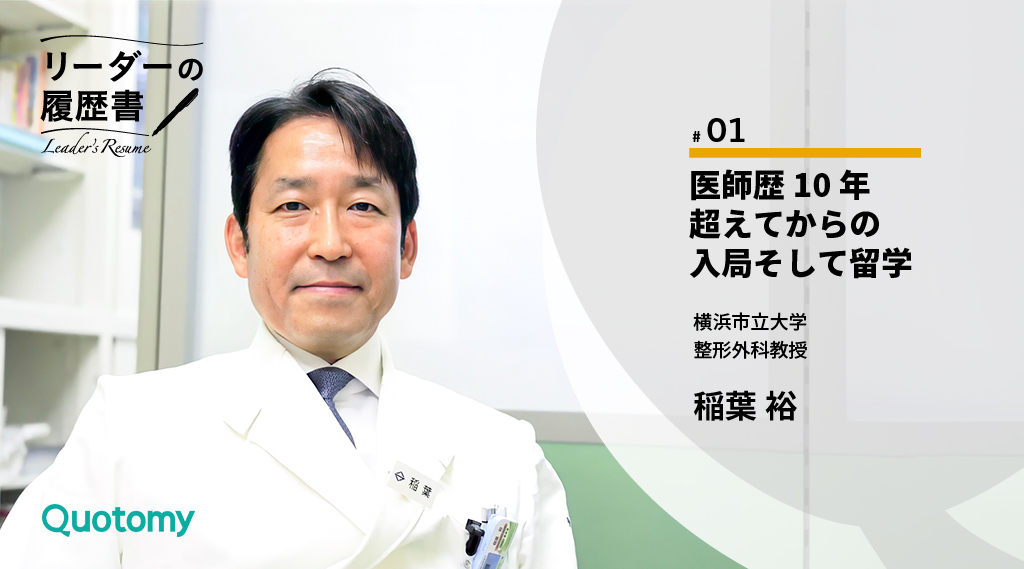
【稲葉裕先生 #01】医師歴10年超えてからの入局そして留学
本編に登場する論文
Operative and patient care techniques for posterior mini-incision total hip arthroplasty
Yutaka Inaba, Lawrence D Dorr, Zhinian Wan, Leighellen Sirianni, Myriam Boutary
Clin Orthop Relat Res. 2005 Dec;441:104-14. doi: 10.1097/01.blo.0000193811.23706.3a.
── まず先生が整形外科を志した理由を教えてください。
私は自治医科大学の卒業ですので、卒業後の義務年限という仕組みがありました。
卒後9年間は所属都道府県の地域医療業務を行う義務があります。
実は、最初は外科に行くつもりだったんですね。
初期研修病院の外科は東京慈恵会医科大学の出張病院だったので、慈恵医大の外科教授に推薦状を書いてもらい消化器外科学会にも入らせていただいたり。
ただ、自治医大卒のため事務年限のローテーションもある中で、自分が外科を選んでスペシャリストに慣れるのか?という点で凄く不安を感じたんですね。
若くしてキャリアに悩んでいたのです。
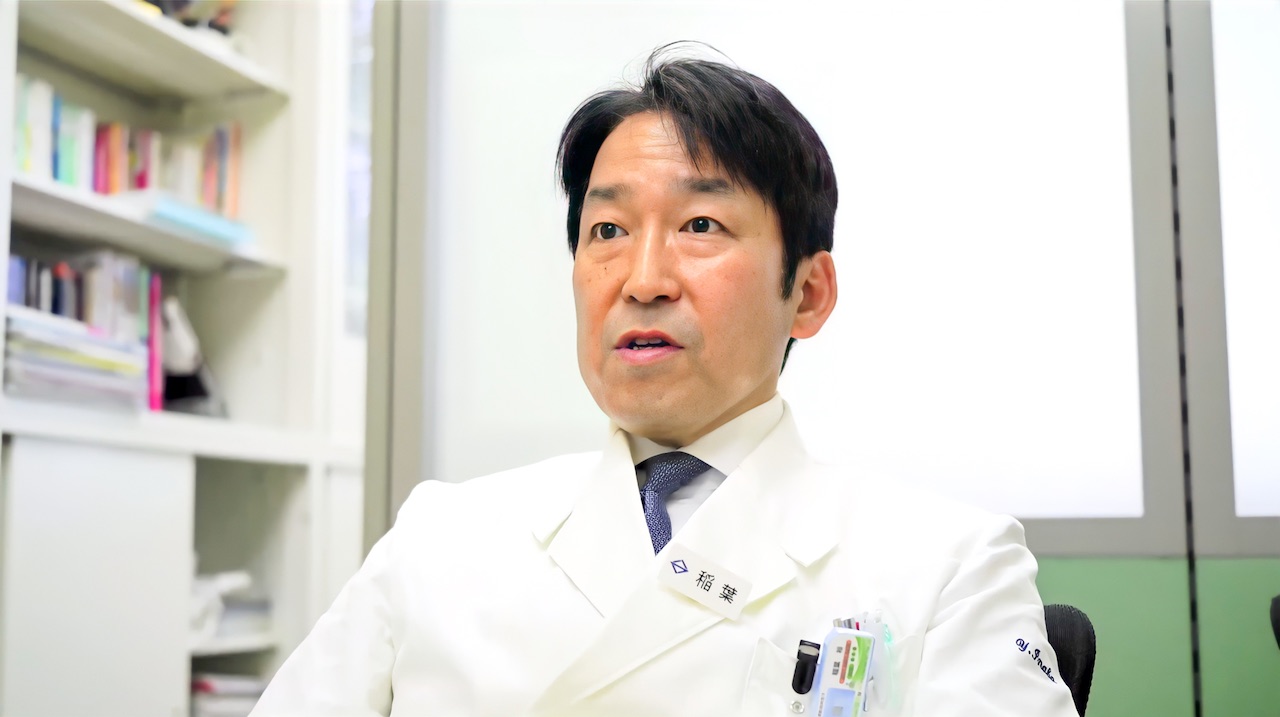
研修2年目の12月に整形外科を5週間ローテートしている時に、ちょうど自治医科大学卒の5年上の先輩の方が厚木病院に戻ってきていたのです。
その方が恩人の吉川一郎先生で、自分の悩みを打ち明けたら「稲葉、何バカなこと言ってるんだよ。」とおっしゃる。
「神奈川県には素晴らしい多くの整形外科の研修病院がある。自治医科大学卒でも、こども医療センターで小児整形外科も、がんセンターで腫瘍も学べて、スペシャリストにもなれる。そうやっていけば、一人前になれるんだよ」って言われて。
もう最後の最後に外科から整形外科に進路を変えたっていう感じなんですね。
── そんな素敵な先輩が身近にいると、心変わりしちゃいますね。
それまで、「それは、しょうがないんだよ」とか「諦めた方が良い」などのネガティブな意見ばかりを聞いていたので、道を示してくれる先輩がいたのは凄くありがたかったです。
その後は義務年限があって、横浜市立大学に入局したのはかなり遅く、卒業後11年目です。
── そうだったのですね。
その後、割とすぐに留学されます。
留学が決まったエピソードはありますでしょうか?
若い頃の無い物ねだりかもしれませんが、、、
自治医大の卒後ローテーションっていうのは診療所行ったり、いろいろな臨床経験を積めるのですが、結局できないのは基礎研究と留学です。
その中で私は留学に興味があって、単純に行ってみたかったのです。
横浜市大に来た時には11年目で先々代の腰野富久教授の頃で、留学するにはちょっと年齢的に少し上になってきていたのは自覚していました。
私が13年目の時に、先代の齋藤知行教授に変わられて、その際に医局長を務めないかと打診いただきました。
その際に、「わかりました。その代わり、医局長のあとには留学したいです」と交換条件というわけではないですけど、お願いしたのですね。
実は、その前から留学先を検討していて、数年後に来ていいよという話を先方からもらっていたのです。
── いろいろ凄いです!
なぜ齋藤教授は入局して間もない稲葉先生に医局長を任せると思ったのでしょうか?
これは推測ですけど、2つあります。
医師11年目で大学に来たということで比較的遅かったのですが、それまでの自治医大のローテーションで勤務先から教わったことを礎にして、横浜市大でも自分なりにできることをやっていました。
それが今までの横浜市大にはない技術や考えだったので、そういう点を買って頂いたのかな、というのが1つ。
もう一つは、教室として変革の時期で、人事面での力があった医師の会と医局との統合が当時の医局長の務めでした。そういう時には、過去のしがらみがある人よりも真っ白な昔のことを全然知らない者がやった方がいいと考えたのかな、と思っています。

特に若い人へのメッセージとして、時々医局員にも伝えていることがあります。
評価っていうのは自分が決めるのではなく、他人が全部決めるものだよ、と。
そういう意味で、他人からどう評価されてるのか敏感になった方がいい。
私は自治医大出身でしたので、医局から派遣されていない立場で、いろんな病院で働きました。
その際に周りから見て、少なくとも同じ学年とか1つ2つ上の学年の医師よりも、しっかりできるようにしよう、と心がけていました。
例えば、同じ手術を同じ学年の人間にやらそうとか思った時には、やっぱり医局の仲間にやらせたいっていう意識が働くと思うんです。
私は自治医大のローテーションで来ていましたから「稲葉にやらせるとしっかり終わるな」と周りから見てもらう必要がある。
俺はこんなにできるんだよっていくら自分でアピールしても、そんなものは全然しょうがなくて大事なのは周りからの評価です。
当時は、今の働き方とは合いませんが、一番遅くまで病院にいました。
当直の先生と夜中まで一緒にいれば、何か救急患者さんが来た時に「じゃ稲葉やるか」という話になって、より多くの症例を経験できる。
留年したから、1つ上の学年には負けない!という気持ちが強かったのかもしれません。
正直言うと、ずっと背伸びしてる感覚はあります。
周りから良く評価されるように意識していたのだと思います。
── 医局長になる前から自分で留学先を探してアプライしていた、というエピソードも行動的で驚きました。
そうですね。
先ほど申し上げた通り。年齢的に焦りがあったので、なるべく早いうちに留学したいという気持ちがあり、医局長になる話がある頃からアプライをしていました。
── 留学先を自分で決められたということで。その時はもう股関節を専門にしようと思っていたのですか?
横浜市大の整形外科って歴史的に3つの専門グループに入るのですよ。
頚、腰、股関節、膝関節、上肢、腫瘍、リウマチ、あと小児整形と、いくつかグループがあり、そのうち3つです。
大学に来るにあたり、こども医療センターにいたので小児整形グループには入ってもらいたと言われました。
それで、あとの2つはどうしようかとなった時に、自分としては股関節か脊椎をやりたかったのですね。
厚木病院で整形外科になると決めた時の部長が股関節の専門で素晴らしかったのですね。
それで若い頃から股関節を見てて、整形外科では股関節を制する者は整形外科を制する、というような感じで育っていました。
股関節か脊椎のどちらかいれてもらえませんか?と医局にお願いをしたら、股関節と小児整形と腫瘍のグループに入ることになったのです。
そういうことで股関節グループに入って大学で働いてみると、今までにない新しいアカデミックなことにとても興味を惹かれていったのです。
それで留学をアプライする時には人工関節に関係するところに出そうと決めてました。
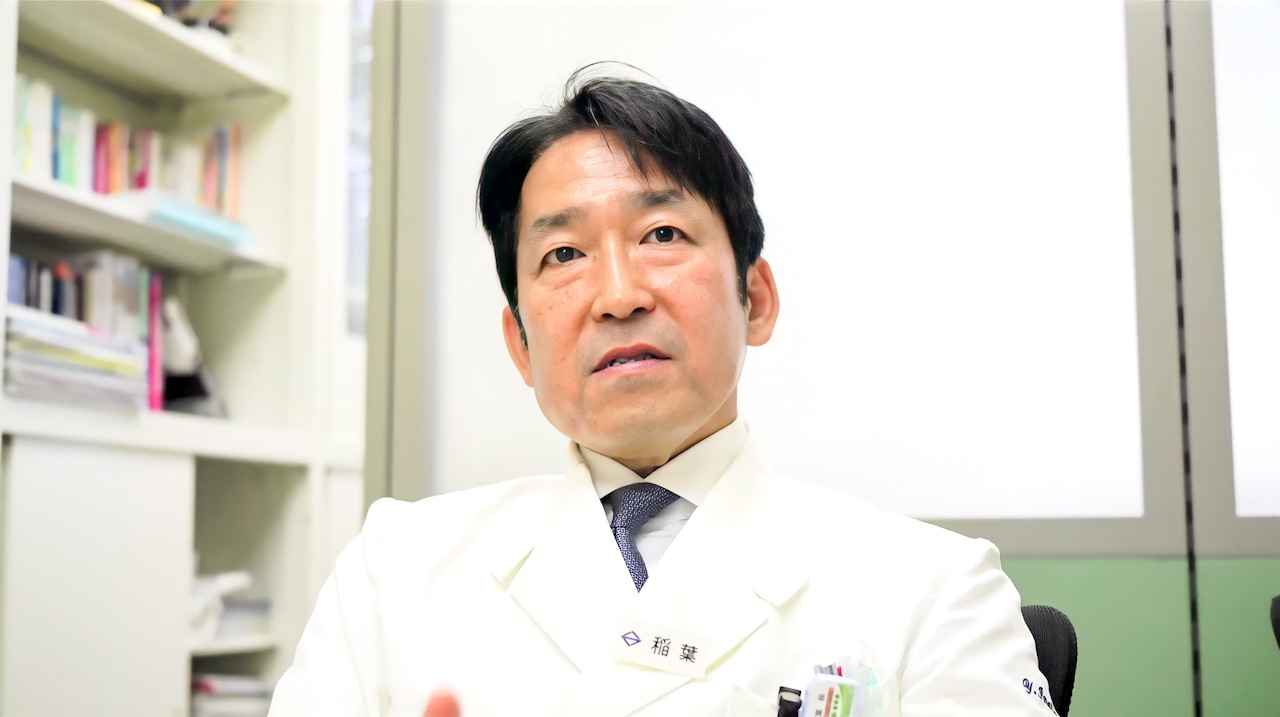
3つアプライしていて、1つ目は無給だったらいつでもいいよ、と。
2つ目はニューヨークで人工関節を発明した先生のところでした。
まず英語ができるかどうか話したいっていうことで、国際電話で一時間ぐらい話したら、是非来て欲しいっていう話になりました。
そしたら先方から、「給料は15,000ドルくらいしか出せないが大丈夫か心配だ。
年間15,000ドルではニューヨークで生活できる訳ないけど、それでホントに大丈夫なのか?」って。
そこで、あとは自分で用意していきますから大丈夫です、という返事をして進めてたのですけど、そこに他大学の無給で良いのでお願いしますという人が現れて、そのポストに入っちゃったんですよ!
そして、最後が、カルフォルニアのDorr Institute for Arthritis ResearchのLawrence Dorr先生という凄い有名な先生のところでした。
アプライしてからずっと返事が来なかったのに、半年ぐらいたったら急に返事が来て。
「今は海外からフェローがいるけど、2年後からだったら受けられる。25,000ドルの給料ならだせるけど、それでいいか?」って。
じゃあ是非お願いします、と返事をして留学先が決まったのですね。
── なるほど。Dorr先生のところに行かれる前にAnderson Orthopaedic Research Instituteにも留学されていますね。
留学先が決まって医局長をやってる途中に、Anderson Orthopaedic Research Instituteで3か月だけ短期間日本のフェローを受け入れるという案内がきていたようです。
齋藤教授が教えてくださり、行ってみたらっと言ってくださったのですね。
── 齋藤前教授、優しいですね!
私の考えでは、留学は行き方も難しいですけど、けっこう難しいのは帰り方かな、と。
行く時には凄く熱意が強く、なんとかなります。。
帰りは、綺麗に日本に帰ってくることができればいいですけども、なかなか帰り先が見つからないようなことも耳にします。
私の場合も、Dorr先生のところに行った際に、仕事も面白くて、カリフォルニアで過ごしやすい環境の中、「もう1年いないか?給料も35,000ドルだすよ」と言われたことがありました。
本当に光栄なことで正直残りたかったです。
ですが、齋藤教授に電話で相談した際の話してる感覚で厳しそうだなと感じ、帰国しました。
時々、そこで医局と無理したり、もう1年いますとか言って延ばしてしまうパターンもあるかと思うんですけども、私はそこまで無理しない方がよいかなと思っています。
── 今回御紹介いただく論文はDorr先生との論文で、人工股関節の低侵襲手術(MIS)に関するテクニカルノートです。
留学時代のお話しを聞かせてください。
ちょうど私が留学した頃は、MISが日本で流行り出した頃で、アメリカでは既にたくさん行われていました。
一方で、Dorr先生が人工関節に対するコンピューターナビゲーションシステムを開発していた時期でもあったのです。
そういうタイミングで留学に行けたので、MISに関する研究と一緒にコンピューターナビゲーションの開発にも精度評価などで関わっていました。
そういう経験をさせてもらえたので、日本に帰ってきてMISを続けたり、コンピューターナビゲーションをするきっかけになった。
これは、その臨床面をまとめたような論文です。
── 凄く大事な論文で、先生がこれを筆頭著者で書かせてもらえたっていうのは、凄く信頼されていたのだろうと推測します。
そうですね。
Corresponding authorがDorr先生なので、アメリカ人ならこの論文を見て私の論文というよりDorr先生の論文だと意識すると思いますが、筆頭著者で書かせてもらえてありがたかったです。
Dorr先生の哲学もあるので、そういう意味でかなり修正もあったりしました。
Dorr先生のことは凄く尊敬していますし、一緒にいて最初はカルチャーショックでした。
まず最初に、こんなに頭の良い先生がいるんだ、と。
外から見ると気性も荒く見えたり、見た目も怖いような先生なのですけれども、笑
私が2-3言を話すとDorr先生は、膨大な経験があるからでしょうか、だいたい全部わかっちゃう。
あとは、食事会などで飲む機会があると、人工関節の歴史と未来を語ってくれることがありました。
例えば、1970年代はセメントの10年間だった。
その後にcement diseaseって言われ、セメントレス時代が10年続いた。
その後、クロスリンクポリエチレンの時代がきて、インストゥルメントが注目される10年になった。
これから10年はMISとかナビゲーションとかテクニカルな時代なんだ、と。
そういう話をされると、凄いなって思いますよね。

臨床研究として色んなことを常に考えている先生でもありました。
いつも新しいトピックスや臨床的疑問を持っていて、それを解決するためにこういう臨床研究をするのだ、と。
あとは色んな医療機器開発ですね。
いまロボット支援手術が出てきていますけど、人工股関節のロボットを最初に開発に取り掛かったのはDorr先生なんです。
そういう新しいことに取り組む姿勢もすごく勉強になりましたね。
#02に続く
こちらの記事は2021年5月にQuotomyで掲載したものの転載です。