
【#03 竹田晋浩先生】常に変革者であり続けるために
本編に登場する論文
Extracorporeal membrane oxygenation for 2009 influenza A(H1N1) severe respiratory failure in Japan
Shinhiro Takeda, Toru Kotani, Satoshi Nakagawa, Shingo Ichiba, Toshiyuki Aokage, Ryoichi Ochiai, Nobuyuki Taenaka, Kaneyuki Kawamae, Masaji Nishimura, Yoshihito Ujike, Kimitaka Tajimi; Committee of Crisis Control, the Japanese Society of Respiratory Care Medicine and Committee of Pandemic H1N1 Surveillance, the Japanese Society of Intensive Care Medicine
J Anesth. 2012 Oct;26(5):650-7. doi: 10.1007/s00540-012-1402-x. Epub 2012 May 23.
── 2009年の新型インフルエンザ(H1N1)パンデミックでは、日本呼吸療法医学会新型インフルエンザ対策委員会の委員長を勤められたのですね。
2009年に新型インフルエンザ(H1N1)の大流行が起こったとき、ヨーロッパではイギリスで最初にアウトブレイクが起こりました。
当時イギリス政府は当初情報を隠していたのですが、ある週の月曜日にBBCがすっぱ抜いたのをきっかけに感染拡大が明らかになったのです。
その時、すでにイギリスのECMOセンターには患者が溢れていたようです。
イギリスで治療できなくなった患者をカロリンスカのECMOセンターへ運ぶとのことで、すぐにカロリンスカへ連絡して様子を聞きました。
── 1996年に留学されていたときにはカロリンスカのECMOセンターへは出入りされていたのですか?
ほとんど行きませんでしたね。
その当時は呼吸不全へのECMOは世界的にも効果が疑問視されていて、そんなものがあるのか、くらいにしか思っていませんでした。
実は当時中学生の娘がイギリスに留学しておりとても心配だったのもあり、カロリンスカと密に連絡を取り始めました。
また同時に現地から伝え聞いたことをもとに、日本で新型インフルエンザについて情報発信をはじめました。
日本呼吸療法医学会と厚生労働省の職員を交えた新型インフルエンザのシンポジウムで、日本での感染拡大に備える委員会を立ち上げるという話になり、情報発信をしていた私に委員長を任せたいといわれました。

こうした経緯で半ば仕方なく委員長となった訳ですが、色々と調べてみると日本での呼吸不全に対するECMOの成績があまり良くないということが分かったんです。
当時は世界的に呼吸ECMOのエビデンスは全くなく、カロリンスカのECMOセンターを含めて世界のごく一部の施設だけが扱っていました。
日本ではECMOをE-CPR(Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation)で使っていましたが、呼吸ECMOはこれとは全く治療戦略が異なります。
エキスパート不在のなかで、日本での新型インフルエンザに対する治療成績は燦々たるものでした。
日本での呼吸ECMOの予後改善のため、カロリンスカから情報を集めてきて日本へ導入するといったようなことに取り組みました。
── 日本とカロリンスカのECMOセンターを見て感じた違いはありましたか?
日本でECMOによる治療を受けている人は様々な合併症を起こして、最期はボロボロになって亡くなってしまうことも少なくありませんでした。
患者も家族も主治医もみんな本当に疲れ果てているような状況でした。
一方で、カロリンスカのECMOセンターを初めて訪れた時にその様子が全く違うのに心底驚きました。
カロリンスカではECMOを使用されている患者がコーヒーを楽しんだり、フェイスパックをしてもらっていたりしており、ECMOに繋がっている以外はまるで普段通りに生活しているかのようでした。
日本で自分たちが見てきた世界とは全く違うものが目前に広がっていることに大変驚くとともに、日本の現状をなんとかしなければならないと感じました。
現地で10日間かけて集中特訓をしてもらい、必死で勉強しました。
帰国してからは、この技術を日本全国に広めなければならないと考えて、学んだことを報告書にして全国のECMOに関連する病院へ送りました。
さらに、日本から医師をカロリンスカECMOセンターへ研修に送り始めました。
同施設は新型インフルエンザのパンデミック時にも非常に良好な治療成績を挙げたこともあって世界中から非常に多くの見学生が殺到していたのですが、スタッフの負担が大きくて、しばらくして見学受け入れをやめていました。
それでも、私からの紹介だけは特別に受け入れてくれていました。

── 2009年の新型インフルエンザにおける日本でのECMOの治療成績に関する論文も出されていますね。
こちらは12施設での治療成績をまとめたもので、現在の呼吸不全へのECMO治療を劇的に向上させることになる論文となりました。
2009年の新型インフルエンザでの重症患者に対する我が国のECMOは、他の先進国に比べて半分の救命率だったことを確認し、問題点を提示しました。
この後から日本の状況を改善させるために様々な対応を行った結果、現在COVID-19に対する日本のECMO成績は世界ナンバーワンとなっています。
── この論文に込めた思いをお聞かせ下さいますか?
当時の日本での呼吸ECMOの現状を伝えるために書きました。
どうにか皆の意識を変えなければならない、という一心でした。
そのためには医師だけでなく、ECMOの装置を製造している企業にも考え方を変えてもらう必要がありました。
というのも、日本で製造されていたECMOはE-CPRに特化して作られたものであり、呼吸ECMOには適さないものでした。
通常E-CPRの場合は数日で使用が終わる場合が多いですが、呼吸不全に対するECMOはより長期に及びます。
装置がコンパクトで取り回しがよく、準備も簡単なため、何よりもスピード感が求められるE-CPRにおいては効果的でしたが、数週間あるいは月単位の長期戦となる呼吸ECMOでは性能が劣ってしまいます。特に長期間の管理では血栓症などの合併症が高頻度で起こっていました。
海外のメーカーは呼吸不全に対応するECMO装置の開発にも力を入れていましたが、当時日本の企業は遅れをとっていました。国内メーカーとしてもE-CPR用のECMOが売れに売れていたので、わざわざ呼吸ECMOの開発に資金を投じることはしなかったのでしょう。
この状況は絶対に変えなければいけない。ネガティブとも受け取られるとは思いましたが、日本のECMOメーカーも含めてECMOに関係する全ての人に現状を知ってほしいという想いで論文化しました。
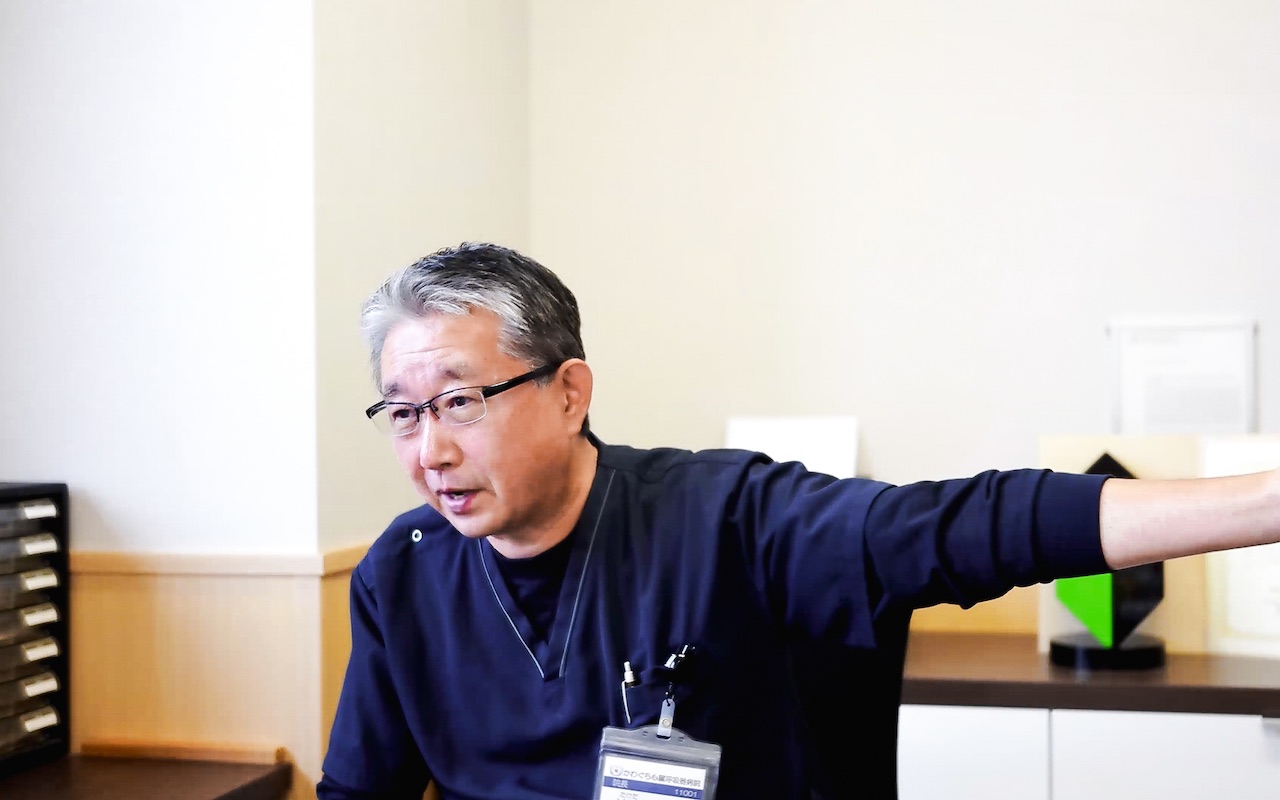
また、日本の呼吸不全に対するECMOをなんとか変えなければいけないという一心で、厚生労働省にも働きかけて、日本にもECMOセンターを作れないかとお願いを始めました。
ECMOセンターの要望は通らなかったのですが、3年間の特別研究班を作ってくれて、研究費を出してくれました。
そして、私が委員長を務めた新型インフルエンザ対策委員会が、2012年にECMOプロジェクトと名称変更して、現在のECMO netのもとになっています。
── その後、2015年に埼玉県川口市にかわぐち心臓呼吸器病院を設立されます。
新病院を理事長・院長として設立されるに至った経緯を教えて頂けますか?
2012年に当時の上司が退官し、自分が日本医科大学付属病院ICUのトップになりました。
その翌年に新病院が完成し、循環器系ICUと麻酔科が管理する外科系ICUに分かれました。
私は外科系ICUの長となり、麻酔科学教室のナンバー2かつICU診療科の教授になりました。
しかしながら、院内のいわゆる政治的なことなどで、なかなか自分の思う通りにできないことが多くフラストレーションになっていました。
そこで、自分がずっとやってきた循環器・呼吸器系疾患だけに絞った病院を作ってみようと思ったのです。
かわぐち心臓呼吸器病院はICU7床、HC U4床に加えてハイブリッド手術室・ECMOセンターなど先進的な設備を備えた全108床の心臓と呼吸器に特化した病院です。
24時間365日「断らない」循環器・呼吸器の超急性期病院で、地域の医療を支えています。
── 新たなチャレンジに不安はなかったですか?
当然ながら不安もありましたよ。
しかしながら、50歳代前半でこのまま大学に残っていても働ける時間は10年弱でした。
65歳すぎてからは自分では何もできなくなってしまうわけです。
一方で、健康でさえあれば、80歳くらいまでは医師として活躍できると思っていましたから、残りの医者人生は自分の思った通りにやっていきたいと考えて決断に至りました。
どこで聞いたか定かではないのですが、ちょうど迷っているときに耳にした「行動を起こさなかったことが人生の最大の後悔となる」という言葉にも後押しされましたね。
病院を作るとなると経営も非常に大切になってきますが、これまで色々な方にお世話になりつつ進めてきました。
スタッフの皆様にも多大なる協力をして頂きながらやっと軌道に乗ってきた、というところです。
── 竹田先生、ありがとうございました!
こちらの記事は2021年8月にQuotomyで掲載したものの転載です。