
【康永秀生先生 #01】権威主義への警鐘
本編に登場する論文
Risk of authoritarianism: fibrinogen-transmitted hepatitis C in Japan
Hideo Yasunaga
Lancet. 2007 Dec 15;370(9604):2063-7.
── まず、先生は元々外科医だったと伺っております。
そこから今の臨床疫学経済学へキャリア転換された経緯をおしえてください。
もともと疫学統計には興味がありました。
しかし、せっかく医師免許を取得して医者をやることなく疫学統計にいきなり進むのもちょっとどうかなと思っていたのです。
外科医を目指したのは、外科の方が外科的治療もできるし内科的治療もできる。
そして、いろいろな手技を学べるんじゃないかと思ったからです。
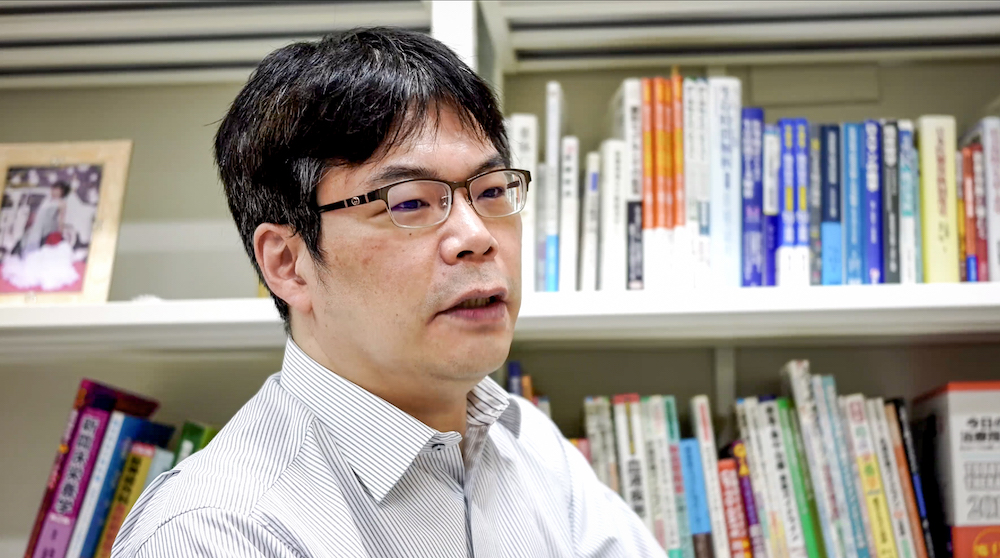
── 臨床現場がお好きだったんですね。
まず最初に行った先は福島県会津若松にある竹田綜合病院っていう1000床ぐらいの非常に大きな病院。
その後、千葉県の旭中央病院へ心臓外科医として行きました。
そんな感じで色々やっていくうちに6年間臨床医をずっとやってました。
当時はちょうど卒後6年ぐらいたつと大学院に行くケースが多く、博士号をとるコースに行くわけですけど、私は臨床の大学院には進まずに公衆衛生大学院に進んだんです。
そこで本格的に疫学統計の勉強をして、結局そのまま今日に至るという感じですね。
── 当時、外科医が公衆衛生の大学院に行く方は多かったのですか?
非常に珍しかったと思います。
当時は日本にようやくEBMという言葉が輸入されてきた頃でした。
今でこそEBMってよく聞く言葉なんですけども、当時はそれまで本当に全くEBMの概念が無かったのです。
でも、私は臨床にもきちんと効果を判定して科学的な評価をすることが必要だっていう風に学生のころから思っていました。
そのためには疫学的・統計学的手法が必要なんだろうな、と思ってたわけです。
今から考えれば、その点は他人と違ってたのかなと思います。
まあもともと数学が好きだったこともあると思います。
── 6年間も外科医をやってると自分でいろいろできることも増え、一番楽しくなってきた時期だと思います。
公衆衛生を勉強した後、また外科医に戻る方が自然な気がしますが?
全くおっしゃる通りで、僕も非常に悩みました。
ずっと外科医続けてもいいかなと、少し揺らいでいる時期もあったんですけど、、、
ただ、外科医という仕事は私の代わりは沢山いますよね。
実際、私よりずっと外科医の才能がありそうな方もいっぱいいました。
外科の仕事もすごく好きだし、すごく刺激的な診療科だと思います。
けど、やっぱりどこかで公衆衛生の道に進みたい自分の気持ちがありました。
タイミングを6年間探し続けてたような感じだったですね。
で、当時の高本眞一教授に相談に行ったんです。
外科やめて疫学統計の方に進みたいと言ったら、腰抜かすぐらい驚かれていました。
結局は快く送り出してもらった。そんな感じですね。
── 公衆衛生大学院の中には医師免許を持ってる人たちは多かったのですか?
当時は臨床疫学という教室がなかったので、公衆衛生学ってすごく幅広い領域をあつかっていました。
臨床疫学だけじゃなくて、予防であったりとか、産業保健とかね。
非常にバラエティーに富んでましたね。
医師の方もいますけど、まあ基本的には内科出身の先生が多くて、外科出身は私だけでしたね。
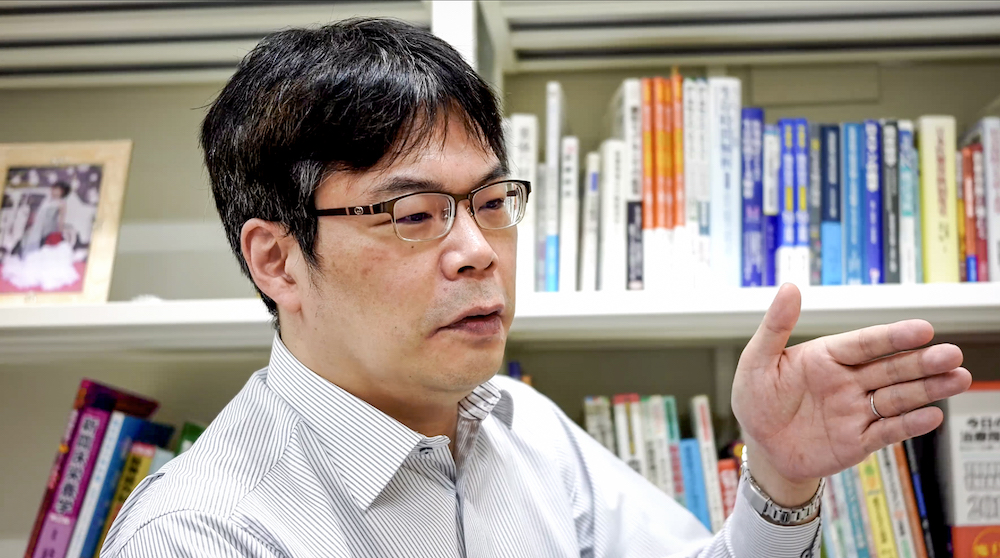
── 最初の論文はデビュー作と伺いましたが、いきなりLancetですね!?
このLancetの論文は薬害肝炎をテーマにしてます。
2002年くらいに日本で薬害C型肝炎の訴訟が起きて、その被害者の方っていうのは、だいたい1970年代とか80年代に出産時の出血でフィブリノゲン製剤を使った患者さんなんですよ。
当時の血液製剤のフィブリノゲン製剤がC型肝炎に汚染されていたんですね。
どうしてかっていうと、輸血でC型肝炎ウイルスのスクリーニングができるようになったのは1989年の事なので、それより前の輸血製剤には肝炎ウイルスに汚染されているリスクがあった。
結局、1万人ぐらいの患者さんが薬害C型肝炎の被害にあい、社会問題になっていました。
それに着目した時に、多くのメディアや社会の受け止め方は、「製薬会社の利益至上主義」とか「官僚行政の問題である」とかまあそういった論調でした。
けれども、この問題の本当の原因は一体何なんだろうかと考えたときに、エビデンスのない治療を漫然とやっている医療の仕組みに原因があるんじゃないか、と私は考えたわけです。
それで、当時「フィブリノゲンに関してのエビデンスがどれぐらいあったか」という事や「C型肝炎の危険性について臨床医たちが危険性を認識していたか」という風なことを、様々な資料をレビューして調査しました。
文献だけでなく今日の治療薬とか産科の教科書とかも読みました。
── 凄いです。
いつの時点ではどのぐらいのリスクの認識があってということを1970年代ぐらいから1990年終わりぐらいまで全部調べ上げて、それを一本の論文にまとめたんです。
結論としてはですね、効果に関するエビデンスが全く無かったんですね。
フィブリノゲンは産科的出血に対して止血効果というのは、ほとんど認められない。
リスクに関しては1970年代〜1980年代初頭に認識がはっきりあったんですね。
一度は1980年代に厚生労働省がフィブリノゲンの適応から産科的出血を除外しようとしたんですけど、産婦人科学会がそれを非常に強く反対したんです。
既にその治療が一般的に広く普及しているからという理由で学会が反対したという背景があるんですね。
当時は、エビデンスを重視しない、それからリスクを軽視して慣用的に使われている治療がずっと再検証されることなく続けられているような医療環境でした。
その医療をとりまく環境が薬害C型肝炎を生み出したんだ、と私はLancetに書いたんです。
アクセプトしてもらって、反響はかなり大きかったですよ。
Lancetに掲載されるときにも、editorial officeから「Lesson for us all」というコメントをいただきました。
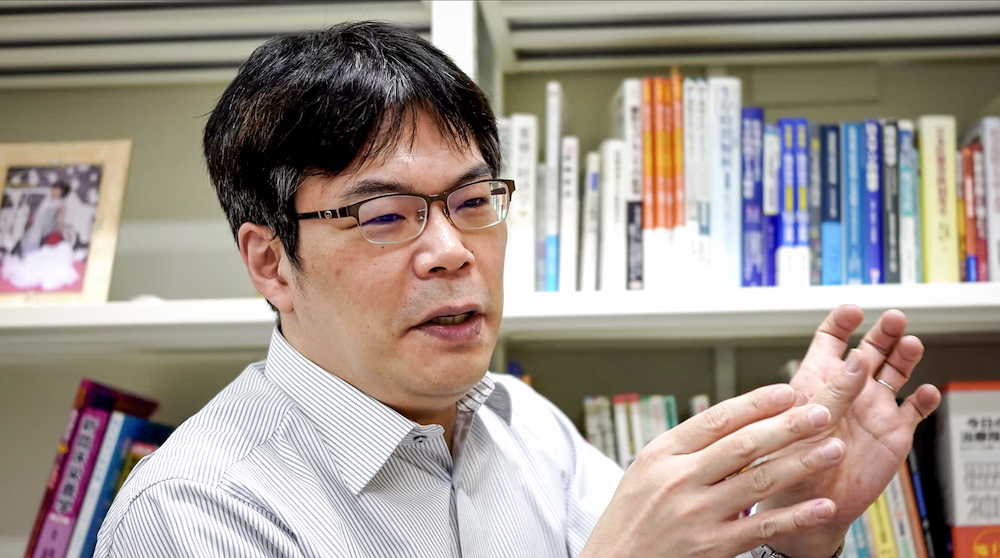
この悲劇というのはただ日本だけの問題じゃなくて、どこの国でもいつでも起こりうるんだ、と論文を締めています。
科学者は既存のエビデンスをどんどん塗り替えるようなエビデンスを作り出していかなければならないし、医療政策に関わる人はエビデンスを医療政策に反映させなければいけない、という風な事を論文に書きました。
ずいぶん変わった論文なんですが、大学院生時代にひとつやり遂げた、という感じは致しました。
── 書きにくい話題ですし、偉い人からお叱りを受ける材料になっちゃいそうな論文ですが、、、
著者を先生お一人の名前にしたのはそういう理由かなと勝手に愚考しました。
内容的には若干刺激的ではあるので、誰も共著者になってくれなかったってのもありますね(笑)
現在もまさに新型コロナ禍の中で、エキスパートオピニオンや政治との絡みで物事が決まっちゃう側面がありますよね。
本論文のタイトルであるRisk of authoritarianism(権威主義の危険)は依然として存在すると思うんです。
薬害C型肝炎という事件を通して権威主義の危険を明らかにし、一般化して警鐘をならした、という論文です。
#02に続く
こちらの記事は2020年11月にQuotomyで掲載したものの転載です。