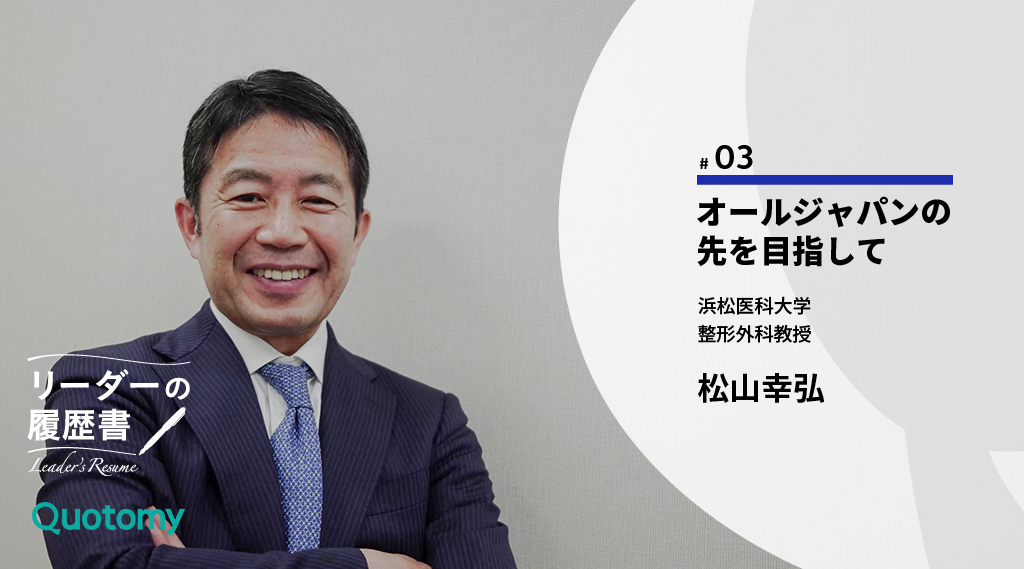
【松山幸弘先生 #03】 オールジャパンの先を目指して
本編に登場する論文
A multicenter, randomized, double-blind, dose-finding study of condoliase in patients with lumbar disc herniation
Yukihiro Matsuyama, Kazuhiro Chiba, Hisashi Iwata, Takayuki Seo, Yoshiaki Toyama
J Neurosurg Spine. 2018 May;28(5):499-511.
── 最後の論文は、先生の難しいお仕事の一つだったんじゃないかと思います。
椎間板ヘルニアに対してのコンドリアーゼ治療のランダム化比較試験(RCT)ですね。
実は、2000年からですから、かなり長期間やっていた仕事です。
コンドリアーゼは、土壌菌のプロテウスブルガリスから抽出した多糖分解酵素で,椎間板髄核の主要構成成分であるグリコサミノグリカン(glycosaminoglycan:GAG)を特異的に分解します。
これは実50年前に名古屋大学理学部の鈴木旺教授、山形達也博士が抽出した酵素で、岩田久先生(現名誉教授)が研究生として教室にいっていて椎間板に応用できないかと研究していた、という歴史があってですね。
私は、2000年に始まった治験Phase1,2からずっと統率してやってきました。
その後、当時慶應大学病院の千葉先生にもPhase3から入っていただいて、約20年かかりましたね。
── 驚きました、2000年からの話だったんですか!?
はい、ものすごく長い道のりでした。
Phase1,2の結果は、とても良い結果で次のPhase2,3も順調に終了できました。
ところがPhase2,3で得られた結果から再度Phase3 を組み直して治験をすることになり、時間もお金も相当費やしてきました。なぜ治験結果が良いにもかかわらずこのように何度も治験が行われたか?その理由は明らかではありませんが、あの頃は首相が短期間に数人変わりました。そうすると厚生労働大臣が変わって、それに付随してPMDAの理事長も変わっていくのですね。申し送りが十分ではなく、もう1回、やり直しっていうのが何回もあった。
── 臨床家としては勘弁して欲しいですね。やめたくなりますね。
やめたくなりますよ、本当に。
とても臨床では考えられないような質問や要求とかされたりして。。。
大丈夫かな、無理かもな、っていうそんなような状況になりましたけど、何とか踏ん張りました。
2018年3月に部会審査が通ったという連絡がきて、一番最初に電話したのが岩田久先生です。
泣いて喜ばれて、、、本当に思い入れが強かった酵素でした。
── 凄いお仕事です。
この論文では多くの施設のデータを使っています
はい、椎間板ヘルニア症例が多く、診断治療能力に信頼がおける施設の先生にご協力をお願いしました。
RCTですのでinclusion criteriaが大事ですから、診断が不確実だと困るわけです。
まとめるのには大変苦労しました。
この酵素が腰椎椎間板ヘルニアの治療に有効であることをいち早く世界へ発信したいとの思いが強く、結果をまとめて論文してあったのですが、PMDAに認可される前に見た提出することによって問題が生じたり、また特許関係のことでトラブルが生じたりすることを回避するために提出できなかったくやしさがありました。
── そういう難しさもあったのですね。

院長になっても現場を知っていることが大切
── 教授会議には出ませんよって言ってた松山先生(第2話参照)が、2016年には病院長になられます。
どういう経緯なのでしょうか?
手術で教授会議には出席できません、2年間は堪忍してくださいと言って、手術室にどっぷり浸かっていました。
そのうち、あいつが一番手術していて危険なこともやっているので、医療安全担当の副院長にさせろっていう指令が下ったみたいで、、、。
当時病院長であった今野弘之先生からお願いされました。
その後、今野先生が学長になられて、僕に病院長になってくれっていわれて。
今野先生は消化器外科学教授でしたので、私と考え方が良く似ていてウマがあったのでしょうね。
それで快諾して、2年間病院長をやらして頂いたということです。
── 整形外科って売り上げは良い診療科ですが、手術で忙しくて会議に出れず、病院内で声が大きな存在になれない印象があります。
そうですね。
でも、いくら忙しくてもできる限り会議には出た方が良いと思います。
手術室から飛んで行ったりして、とにかく意見を言う。これは整形外科の病院内の立ち位置を少しでも上げるためには必要なことなんですね。いくらスタッフみんなで頑張っても、その存在感を見せて行かないと整形外科スタッフは報われませんから。
病院長になって感じたのは、経営的にも特定機能病院において手術はやはり大事だなということです。
そして、医療安全が最も大事で、そこの部分がくずれたら終わりだなと思ってます。
ただ、現場の状況を良く知らないと問題点が何かってわからない。
だから、院長になっても臨床を離れることなくやっていきたい。
── でも先生もお忙しくなって難治症例の脊椎手術はどうされているのですか?
今は大和先生、長谷川先生、そして吉田先生にチーフになってもらって、それぞれの下に若手がいて、っていうチームを作ってましてね。
チームごとに手術をやってくようにしてます。
PSOやVCRをやるような脊柱変形や脊髄髄内腫瘍など難治性で大変な手術では、私も手術に入りますよ。

── 病院長職のみならず、学会でもお忙しいと思います。
2020年に会長職を務められた脊椎脊髄病学会では新型コロナで大変な状況の中での開催となってしまいました。
本当に残念でした。
一度目の緊急事態宣言が発令された2020年4月の開催でした。
予定では外国から150人も脊椎外科医が来る予定だったのです。
学会の半分のプレゼンテーションが英語でおこなわれ、午前中のシンポジウムは全部英語でディスカッション、という予定を組んでました。
学会から招聘した海外のドクターもいますけど、向こうから参加応募してきた人も結構たくさんいました。100人以上は参加応募で海外から来る予定だったのですよ。
けれども、新型コロナで、もう学会どころではなくなってですね。
苦肉の策で9月にハイブリッドという形式で開催させてもらいました。
── 本当に悔しいですね。
「All Japanからグローバリゼーションへ」っていうスローガンを掲げていました。
アジアの国って日本からすごく近いですし、科学的な評価もできるようになっています。またSPINE、JNSなどしっかりした論文にも多く投稿されてきています。
もうアメリカばかり見てる時代じゃない。
マレーシア、シンガポール、香港、そして韓国。
そういった国々の医師と自由にコミニュケーションして、ディスカッションして、そしてお互いを高めあっていく。
オールジャパンで研究を進めていくのは当然のこと。
1つの施設に留まるんじゃなくて、症例をシェアして良い研究をして、そしてその結果を世界へ発信してゆく。学会が主体となって研究を立案し、そしてオールジャパンで結果を形にしてどんどん排出する。皆でやっていく意識、それが大事かなと思ってます。
今度は2021年の11月に側彎症学会を担当させて頂くので、また海外から集めたいですね。
あとAsia Pacific Spine Societyも2021年6月に神戸で開催します。
おそらくハイブリッドでしょうけど盛り上げたいと思っています。

── 先生のモットーである「KKSKI」について教えてください
例えばどういう教育方針でやるのかとか、人生の進むべき方向性を考える時に自分の心に決めた言葉です。
苦しんだ時や、悩んだ時にどういう方向に進んでいったら良いのか、そんな時に強い決心があると良い方向にいけるんです。
KKSKIの最初のKは「困難に立ち向かえ」のKです。
皆が嫌がってやらないこと、大変だと尻込みするようなことを率先してやろうという事です。
臨床もしかりで、皆が目を背けるような難しい症例も率先してやろうということ。
2つ目のKは「断るな」ですね。
上司が頼んでくれた、あるいは友達が頼んでくれた事。なぜ自分に依頼されたか、考えて見てください。能力とか信頼があったからこそ頼んでくれるわけなので、それは断ってはだめなんです。ものを頼まれたら喜んで受けるべきだと思います。
どうしても受けられない時はその旨お伝えすること。できる限り受けて断るのは最終段階。
自分の損得だけを考えて断ったりしたらだめだということです。
3つ目のSは、なんでも受け入れたら「精一杯やる」のSです。
失敗しようが成功しようが一生懸命やれば悔いはないんですよ。
手術でもそうで、適当にやると後で後悔します。
とにかく自分の持てる知識そして技術すべてのものを全投入して精一杯やる。
4つ目のKは「感謝」のKです。
色んな人の協力のおかげで皆生きているわけで、一人では生きていけないですから。
だから必ず何があっても感謝の意を表すべきだ。
今回もこういった機会を設けてくれて本当にありがたいなと感謝しています。
最後のIは「いつも笑って」のIです。
いつも笑ってると辛いことも忘れていくんですよ。
笑うと色んなサイトカインが身体中で出て脳の血流もよくなりますね!
眉間に皺を作って生活していると何かギスギスしたような感じになる。
とにかく、いつも笑顔をたやさず生きることが大切ですね。
皆で前向いて超ポジティブ思考で頑張れば何とか乗り切っていけるんじゃないかなと。
最善感ですよね。
あと松下幸之助さんの「一陽来復」がすごく大好きな言葉の一つです。
本当に辛い様々な困難がきてピンチに立ってる時、それは貴重な体験を与えてくれるチャンスなんだと考えれば勇気が出る、元気が出る。
もがいて一生懸命に前向いて精一杯頑張れば必ず光が見えてくるんだ、どんよりした冬の寒く辛い時から一筋の陽がさしこんで再び春を迎えることができる。
そういうようなイメージの言葉です。
とにかく明るく頑張ってやれば何とかなる、解決する、いつもそう思います。
前を向いて、そして皆に感謝しながら生きていく。
新型コロナに関しても同じだと思います。
医療者に対する感謝の気持ちを色んな方から手紙でもらったりする。
本当にありがたい。
そういう感謝の気持ちは皆さんどなたも持ってるし、我々も持たなくてはいけない。
思いやりの気持ちがすごく大事ですね。
そういう風に考えて生きていければいいかな。
こちらの記事は2021年1月にQuotomyで掲載したものの転載です。