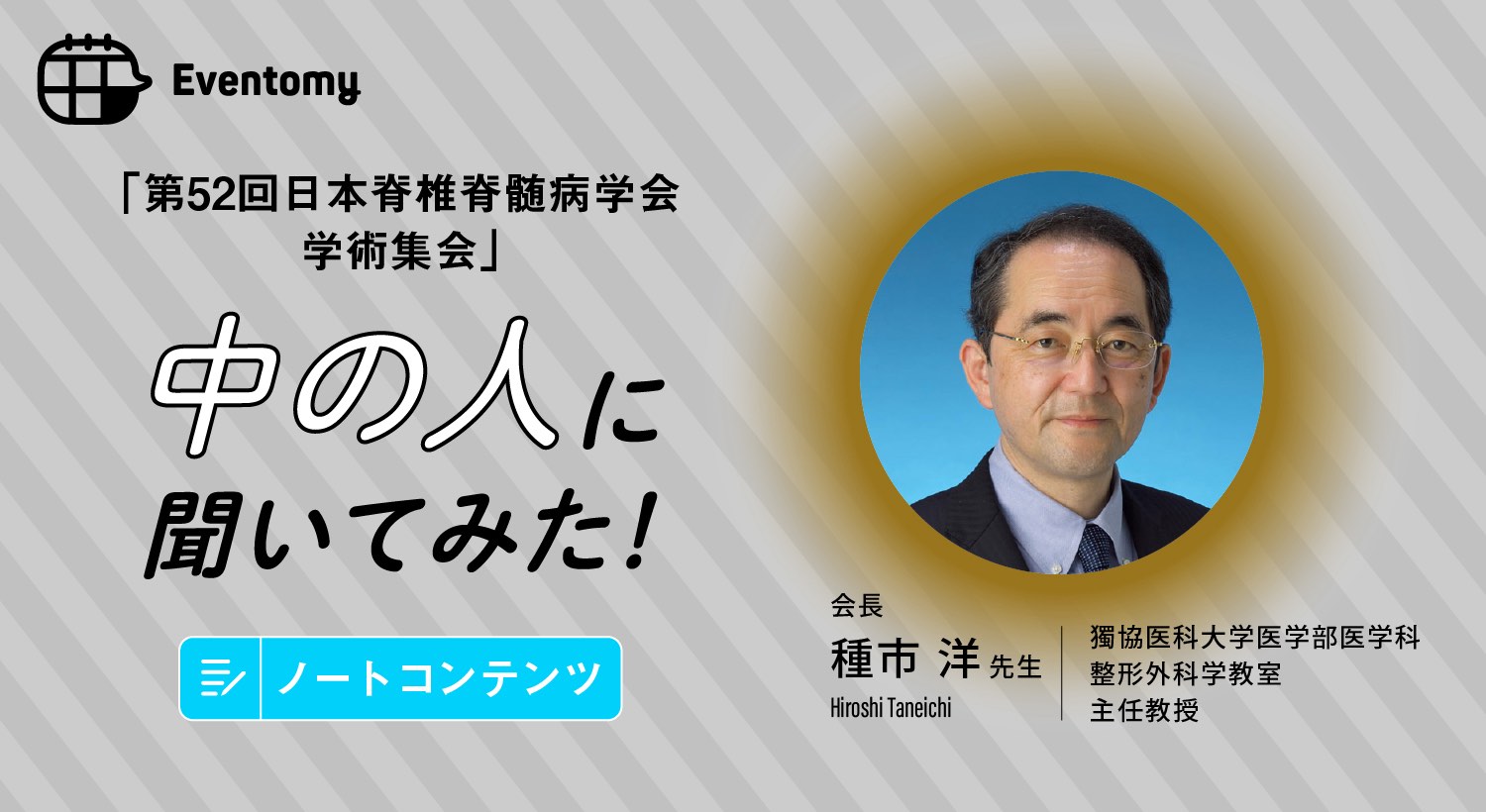
第52回日本脊椎脊髄病学会学術集会 会長 種市 洋先生
興味深い学会やイベントを特集し、運営している「中の人」にいろいろ伺っていく、「中の人に聞いてみた!」です。
今回は日本時間2023年4月13日(木)~4月15日(土)に開催される『第52回日本脊椎脊髄病学会学術集会』についてご紹介。
会長の種市 洋先生(獨協医科大学医学部医学科整形外科学教室 主任教授)にテーマである「格物致知」を中心に、学会への想いを語っていただきました。
── 本日は大変お忙しい中、第52回日本脊椎脊髄病学会学術集会会長でおられる獨協医科大学医学部医学科整形外科学教室主任教授の種市洋先生にお越しいただきました。種市先生、よろしくお願いします!
どうも獨協医大の種市です。よろしくお願いします。
── 本日は、まさに学会直前になってしまっているのですが、学会の「中の人」に話を聞こうということで、先生にお時間を取っていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
── 今回の学会のテーマ「格到日新」について、先生から教えていただけますでしょうか。
はい、今回のテーマは「格到日新」としました。
格物致知という昔から中国で伝えられている言葉がありまして、南宋時代の朱熹(しゅき)っていう儒学者が決めた朱子学の中で定義が定まったという風に言われています。
どういう意味かを平たく言うと「事物をしっかり観察する」「それによって物事の本質を見極め、真理を掴む」ということです。
南宋時代だから随分昔の中国なんですけど、格物到知っていうのは事物をしっかり自分の目や耳で観察することによって物事の本質にも近づいていくと言う意味です。格到とも略されて、日々進歩するって意味の日新と合わさったこの格到日新っていう言葉は、私の大好きな言葉なのです。
実は日整会広報室ニュースの新教授の紹介記事でも紹介させて頂きました。
── 温めていた大切な言葉なんですね。
はい、私の座右の銘です。自然科学の基本は、格物致知に尽きるんだと思うんですね。物をしっかり観察して、真実を明らかにすると。これは実は外科の修練も同じです。外科技術は、しっかり自分の目で見て、その本質を捉えることが大切です。手術手技書なんかで見ても全然大したことは伝わらない。手術っていうのは3次元的に空間として捉えることが非常に重要だと思うんですね。理屈は本でも分かるんだけども、じゃあ実際にどうやるの?っていう時に、先輩医師のやってる手術を自分で目の前で見るのが1番いいですね。前立ちして見る。場合によっては外から見る。そうすることで、3次元的な空間として理解する必要があると思うんですよ。今回の私の会長講演でも、この話をしようと思ってるんですね。手術見学トレーニングを獨協医大では非常に多くやっていて、この間数えてみたら、新型コロナ禍前の5年間で手術見学に来た人は153名いる。
── 凄いですね。医局外からもですか?
全て医局外からの参加ですよ。いろんな手術や術式の成績を学会で発表しますけれども、これでは格物致知には程遠い状況です。まずはしっかり自分の目で手術手技を確認して、そして、本質がなんなのかってことを理解して、そして、自分の技としていくというところが極めて重要なんですね。この最たるものは昔は手術トレーニングです。昔からOn the Job Trainingが基本だったんだけども、最近では全てがOJTではできなくなってる。それから、内視鏡手術やダビンチ、ロボティクスにしても、なかなか直接見れないような場所も部分も多いので、いわゆるキャダバーサージカルトレーニングが極めて重要となってきてる。
例えば、ボーンモデルもただ形だけ似てるというだけでクオリティは全くダメなら役に立ちません。海綿骨もないボーンモデルにスクリューを打っても、実際の骨に打つのとは全く違うんですね。
僕らがボーンモデルを使ってるものは、新しいボーンモデルで、ある患者さんのペイシェント・スペシフィック・モデルにできるんですよ。構造も皮質骨と海綿骨があって、しかも、骨皮質はレントゲンに映るような加工がしてあり、透視を見ながらスクリューを入れたり、スクリューを入れる時の感覚も非常に本物の骨に近づいています。
今回の学術集会でも、そういった医師の卒後トレーニングを1つのテーマにしています。
── 硬くて実際の手応えとは異なるボーンモデルが多いですよね。
それから、研究も机上の空論にならないように、なんでも現実に即したものでなければ良くないわけですね。エビデンスを得るための最もレベルが高い方法として、RCTとそれを集めたメタ解析と言われているのですが、RCTは適用基準を相当厳しく決められています。実際の医療の現場では患者背景というのは千差万別ですから、RCTの結果というのは、現実の医療に実装できないものが多いんですね。
── なるほど。
必ずしもRCTが全てではないというわけです。これがリアルワールドデータを使ったレジストリー研究につながってくる。いろんな患者背景を十把一絡げにして行った研究っていうのがすごく大事なのです。ただし、患者背景が複雑になるので、必要な症例数が膨大になってくるわけです。ですから、ナショナルレジストリーを作る流れとなり、整形外科でもJOANRっていうナショナルレジストリーが作られています。日本整形外科学術総会の初日に年次報告を出す予定です。公益社団法人としては、国民全部にこういった情報を提供することに意味があるということで、一般国民向けに発表する予定なのですね。
運動器の手術では、おそらく使えるデータとしてはレセプトデータが最も広範囲に患者を集めてるデータです。JOANRは全ての手術を登録してるわけじゃないですが、レセプトデータが正しい分母だと仮定すると、およそ8割がもうカバーできています。1階部分は診療報酬算定のためのエビデンスを作ろうということで、手術時間などの簡単なデータしか入っていませんが、脊椎脊髄病学会が2階部分で合併症データを入れているんですね。15万件ぐらいの合併症データを公表できるようになる。本当に脊椎手術のナショナルトレンドに近いものが出せるようになるのです。医療者にとっても正しい現状が分かり、自分の医療レベルが全国の中でどれぐらいの位置にあるのかっていうこともわかるし、患者さんに正しいことを説明できるし、いろんなメリットがあります。
日本の整形外科ではレジストリー研究が第1歩を踏み出したところなので、ここからより真実が見えてくるかなと思っています。
── 格到日新シンポジウムが4つありまして、先ほどの「脊椎外科のエデュケーション:On the Job Trainingから一歩前へ」というテーマ以外に、残り3つあります。
残りの「病態の本質に迫る基礎研究」、「難治性脊柱変形に対する治療:治療の本質を考える」、「転移性脊椎腫瘍の治療:その目指すもの」も、事物をしっかりと観察しているようなものを選ばせてもらいました。
その中で転移性脊椎腫瘍について話すと、患者さんがいま何を求めているのかということを、しっかり見極めて治療を選ぶ必要がある。がんの患者さんたちの治療薬が極めて進んでいて、ステージ3とかステージ4のがん患者さんも何年も生存する可能性があるわけです。
かなりの長期間生存できるようになってきてる時に、姑息的治療の持つ意味が昔と全く異なってきている。根治は望めないとしても、できるだけ自分らしく長く生きて生活できることを求められています。今回の格到日新シンポジウムの転移性脊椎腫瘍に関しては、集学的な治療からTESまで全て含めてどんな治療法があるのか、患者さんが何を求めていて、そしてどういうゴール設定が今の時代に合ってるのかっていうのをもう一度考え直そうということで選ばせてもらいました。
── 続いて、基調講演、特別講演、文化講演、招待講演についても教えてください。
まず、野原 裕名誉教授ですね、野原名誉教授は、実は12年前に日本脊椎脊髄病学会学術集会の会長でいらしたのですが、その年に東日本大震災が生じて学会開催中止となったのです。それで、僕のメンターの1人である野原名誉教授に、本当は会長講演をする予定だったんですけど、今回は基調講演をお願いして、50年前に医学部卒業した頃から脊椎外科のことを話してもらおうと思います。野原名誉教授には、ものすごい苦労話がたくさんあって、非常に僕らのためになる話です。
その後、僕が格到日新の話をして、その後にファナックっていう工業用ロボットの世界ナンバーワンの企業の稲葉善治会長・CEOにお話いただきます。彼にお願いしたのは工業用ロボットの話です。いま世間を席巻してるダビンチってありますよね。ダビンチは、ロボットというよりはマニピュレーターなんですね。人間の手技を手伝うための道具なんですよ。
── なるほど。
では、ロボットっていうのは一体何かっていうと自動化。自動車の世界でも、カーナビから自動運転になってきてるじゃないですか。ダビンチではなくて、 ナビゲーションを使った手術の自動化をしないと、ロボティクスにならないと思ってるんですよ。ダビンチの手術は多くの診療科で保険収載されてますけど、加算があるものはないですね。なぜ加算がないかっていうと医者のコストが変わらないからです。医者のタスクシフトにならないから、保険料の加算ができないんです。
今、脊椎領域のロボティクスには椎弓根スクリューを入れるためのロボットアームがありますね。ナビゲーションデータを基に位置を決定するので、そこにスクリューを入れるのは学生でもできる。法律の改定が必要なんですけど、ここを自動化するのは簡単なはずです。そこで椎弓根が破れて神経の障害が起こるリスクがあるのかどうかも、今の技術ならモニタリングできる。ある意味、椎弓根スクリューは非常に簡単な技術なので、そこを自動化できれば、例えばロボットが椎弓根スクリューを入れている横で、僕らが側方進入椎体間固定を人間の手で行う、とか出来そうですよね。そうすると、後方手術のチームがいらなくなり、医師がロボットにタスクシフトすることになるので、人件費の大幅削減になります。すると、保険点数を上げることができるんですよ。もちろん安全面などクリアしなければいけない問題がたくさんあるのですけれども、ロボティクスっていうのはそういう方向に向かうべきだと私は考えていて、工業用ロボットで世界のナンバーワン企業のファナックの稲葉さんに自動化の話をしてもらうということです。
── めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。
いま、多くの医者はダビンチに注目してますけども、本当の意味のロボットではない。ロボティクスという自動化技術に脊椎外科医がインスパイアされれば良いなと思って、稲葉さんにお願いしたんですね。
── 素晴らしい。文化講演についても教えてください。
自分は独協医科大学医学部で医学部長をやらせてもらってて、医学教育の担当なのです。今の医学教育に重要なポイントがいくつかありますが、コアカリキュラムで医師に求められる資質の1番目に出てくるのがプロフェッショナリズムなのです。医者としては知識や技術よりも、医者として、いかにふさわしい態度で行動するかが求められている。その1つが人とのコミュニケーションなのです。山根基世さんは、NHKのアナウンス室長をやってたインタビューのプロなんですね。彼女にインタビュアーから、医療面接の極意を主に若い先生たちに話してもらいたいと思っています。 医者がどういう風に患者さんに接して、良い医療ができるか、彼女は医療面接に関してもかなり興味持っていますので、プロフェッショナリズムの基本をお話していただこうという風に思ってます。
今回の基調講演、それから会長講演、それから特別講演、 文化講演の流れはこういった一連の流れで企画をさせていただきました。
── 素晴らしいですね。4月13〜15日という会期でオンサイトで開催されますが、その後のオンデマンド配信もあるのでしょうか。
オンデマンド配信は、日本脊椎脊髄病学会学術集会が終わってから日本整形外科学術総会まではやります。どうしても札幌まで来ていただけない人もいらっしゃると思うのでオンデマンドで聴けるようにはしてますが、久しぶりの札幌だと思うので是非現地にお越しください。
── 北海道、楽しみです!本当にご多忙の中、お時間を取っていただき、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。