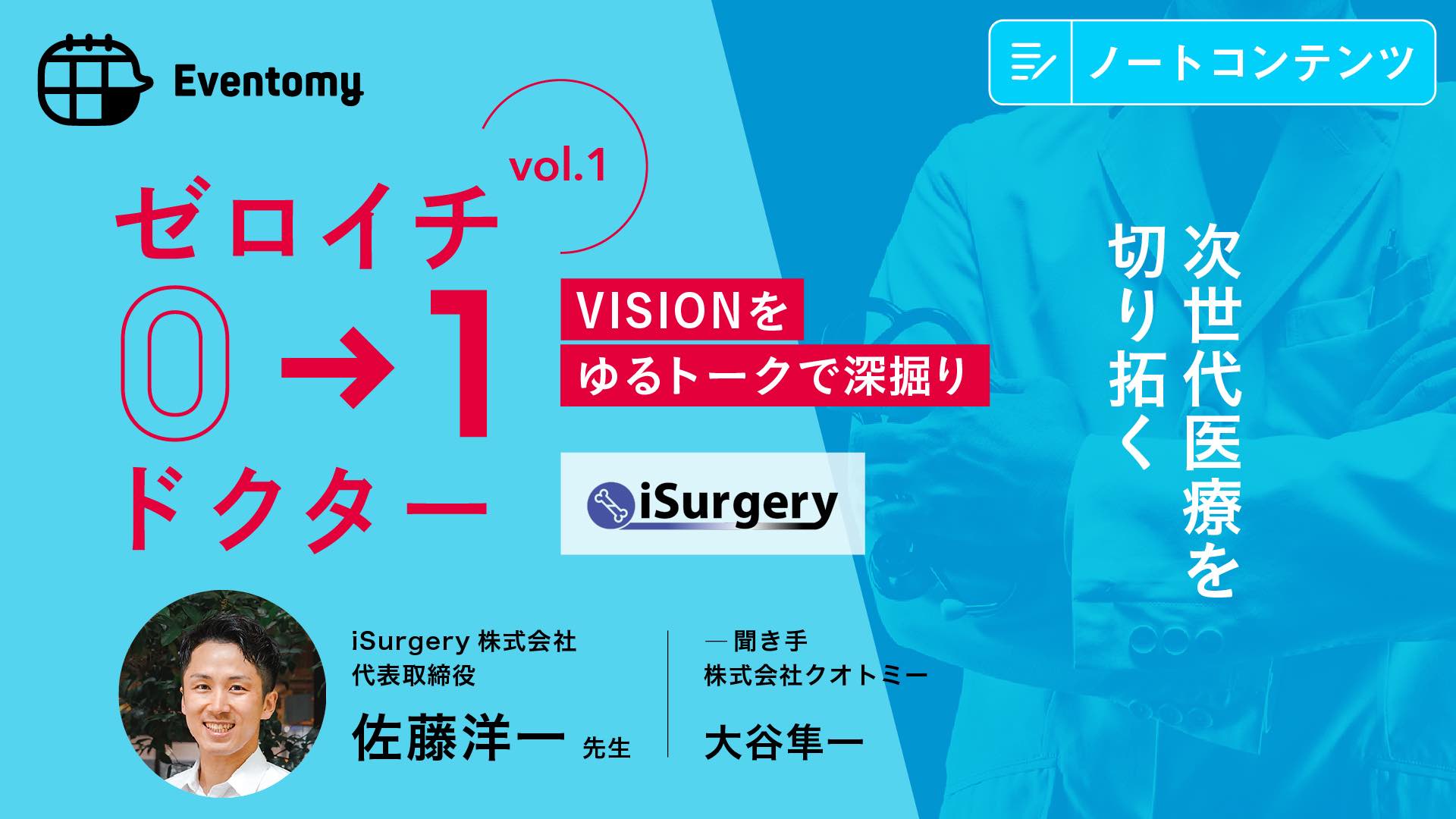
iSurgery株式会社 佐藤洋一先生
現代の医療には、多くの課題が山積し、新しい形の医療が求められている中で、次世代医療を切り拓くゼロイチドクターが誕生しています。彼らのビジョンをクオトミー代表の大谷が緩く深堀りするトークイベント「ゼロイチドクター」。
初回は胸部レントゲン画像から骨密度を計測するAI医療機を開発されているiSurgery株式会社代表取締役の佐藤洋一先生をゲストにお招きしております。
── 佐藤先生、簡単に自己紹介からお願いします。
初めまして。株式会社iSurgery代表の佐藤と申します。バックグラウンドは整形外科医ですが、8年ほど臨床をして、3年前にAIと出会って「これは世界が変わりそうだな」と夢を見てしまいました。
そこからAIの社会実装を色々やっていくうちに、これだけはやり遂げたいと思うものが見つかったので、臨床医のキャリアを1回ストップして、2022年4月から会社でAI医療機器を作っています。
── 医師で起業家というキャリアは結構珍しいと思うんですけど、振り返ると、医学部の時にも医学以外の勉強したいとか、例えばプログラミング勉強していた、色々な学問に興味あったりしたんですか?
そうですね、あんまり起業だったりとかには実際興味はなかったです。すごく高尚なイメージがあったし、僕は全然勉強もできなかったし。ただ少し、課外活動とかは好きでした。あと、誰かと一緒に何かをすることは結構好きだったんですね。
もともと医学部1年目、2年目はヨットをやっていて、3年目の時に同級生の1人が、みんなで学生団体作って、海外支援をしようみたいな話をしてくれて。それ、ちょっと大学生っぽいなと思ったんですよね。それで一緒にやってみたら、すごく楽しくて3年目から6年目までずっとやっていました。
── 海外支援は、医療に関係あることですか?
そうですね。一言で言うと、ラオスに病院を作ろうっていうことです。学生団体の形で1〜2カ月に1回、例えば日本で屋台を出店したりとか、イベントを開いたりとかして、収益を集めて現地に持っていきました。
でも、ただ現地にお金を渡して終わりではもったいないので、ラオスには半年に1回ぐらいみんなで足を運んで現地視察していました。ラオスの健康科学大学という1番大きい大学と協定を結ばせていただいて、どこに支援したらいいかとか、どういう形の支援がいいかとかを、学生なりに現場のニーズを聞きながらやっていました。
── すごいです。ちゃんと現地でのニーズを聞いたんですね。
そうですね。現地の人の顔を見られたので、日本に戻っても頑張れました。日本では楽しくやってたんですけど、相手の顔が見えていたのは実体験に基づくものになるので、すごく良い経験だったなと思います。
今も会社を運営していてすごく思うんですけども、やっぱり骨折している患者さんを診ていて何とかしたいなっていう原体験が、次のモチベーションにつながって色々やっています。初めてラオスに行った時、色々衝撃を受けました。ちゃんと医療が届いていたら救える命も多分あると思うし助かる人たちもいたはずで、そういう人たちを見てると、何とか力になれたらな、と思ってやっていました。
── そういう活動を医学部3年目から4年間、みっちり取り組んで、佐藤先生たちが卒業した後も誰かが引き継いで今も残ってるのですか?
僕はぶら下がっていただけですけど、後輩たちが引き継いでくれていて、毎年何人か入っています。僕らの代は10人ぐらいで始まって、毎年7人ぐらいずつ集まって、20〜30人ぐらいの団体ですね。すごく楽しかったですね。
── 医学生で部活を頑張っていた話は割とあると思いますが、社会活動、しかもグローバルな活動ができる機会はなかなかないので、すごいですね。そんな佐藤先生が整形外科を目指したのはなぜですか?
父親が整形外科の医師でしたので、やっぱりその影響はすごく大きかったですね。僕は物心ついた時から日曜大工というか、木に穴開けたりとかネジ打ったりとかを、家でやっていたんです。研修医になって整形外科を回っている時、手術に入ってドリルをした時「あ、これだ!」ってDNAが覚えていてですね(笑)。
それまでは結構、父親に対する反抗心が強くて、教師になろうとか脳外科医、救急医、総合診療医だとか色々言ってたんですけど、やっぱりDNAには勝てなくて、いつの間にかハンマーとかノミとか手に持っています。
── やっぱりDNAだったんですね。
勝てなかったですね。もう少し華やかな科に行きたかったのですが、、、今は整形外科に進んで良かったと思っています。
── ご家族、お父さんも喜ばれたでしょう。
すごく頑固おやじなので、僕はいまだに2人で飲んだりとかできていないんですけども、内心は嬉しいんじゃないかなと思ってますけど……ちょっと分かりません。
── お父さんと同じ医局なので、お父さんが先輩ということですね。
そうですね。結構相談に乗ってくれて、良い方向のアドバイスよりも、悪い方向に行かないようなアドバイスをくれます。例えば、こういうガイドラインがあるからこれは気を付けた方がいいとか、世の中の流れはこうなってるから、こっちの流れは多分良くないから行かない方がいいぞとか。
個人情報の話だったりとか、保険点数が今後こういう感じの方向になっていくから、こっちの方は多分勝ち筋が少ないからとか、そういうちょっと戦略的な話もそうですけれども。そういう見方があるんだ、と思いますね。
臨床の末端で働いてるだけだと見えてこない世界、いわゆる組織同士のつながり、医局のつながりだったりいわゆる政治的な話だったりとか、そこを教えてもらえるってのは、自分にとってはすごくいいかな。まあ、あまり活かせていないと思うんですけど。
── そういう情報は医師になって何年目で話していたんですか?
ちゃんと聞くようになったのは、会社を始めてからですね。それまではあんまり響かなかったというか、手術ばっかりやっていたので、そんなに興味がなかった気がします。
── 臨床が楽しかったんですね。
そうですね。
── そんな佐藤先生がAIと衝撃的な出会いをしたそうですが、それはいつ頃ですか?
2019年で、医師になって6年目ですかね。6年目まで名古屋市内の病院にずっと勤務していました。研究も好きで、素人に毛が生えたような研究をずっとやってたんですね。骨折に関する色々な研究をしていたのですが、自分としても1つ筋というか持ち味を見つけたいなとずっと思っていたんです。
その時にちょうど医局人事で、少し田舎の方に行くことになりました。それまで三次救急でバリバリやってたのに、いきなり時間にゆとりができてしまったんです。それで喪失感というか、モチベーションが落ちてしまって――。1週間ぐらい本当に毎日、ストロングゼロをずっと飲み続けていたんですけど、その時、三重県で開催された学会でたまたまAIの講演を聴いて「あ、これだ!今の何も目の前にない状況から、これを辿って掘り下げていこう」と。自分の道筋としても、AIを掘り下げていけば何か見えるかもしれないし、特にまだ若くて知識も経験もない人間が、1つの飛び道具で誰かと戦うならもうこれしかないなって、そこから一気に飛び込んだ感じです。
── なるほど。何の学会でAIの講演があったんですか?
第132回中部整形外科災害外科学会でした。理化学研究所の山本陽一朗先生が講演してくれました。
── 講演で衝撃を受けるところが感度高いというか、実臨床に活かせると頭の中でつながったんですね。
そうですね。先生のお話がお上手だったのが大きいですが、自分でもできそうだなって思ったんですよね。もちろんプログラミングもできないし、全然知識も経験もなかったんですけど、でも、なんとなくその先生のお話ぶりから「なんか未来がありそう。世界が変わりそう。0からでも、自分でも、何となくできそう」という感じがして動けました。
あと最初は1人でやろうと思ってたんですけど、医局の同期に話した時に賛同してくれてというか乗ってくれて。それで二人三脚で歩き始めたことがきっかけで、どんどんチームが増えいったことも大きかったと思いますね。
── 仲間ができてもドクター同士。エンジニアの仲間がいない中で、二人三脚でまず何をしようとなったんですか?
ググったんですよね。その時、周りにAIをやってるドクターもいないですし、エンジニアのつながりもなくて。AI研究の仕方も分からないので、1から本を読んで進めるのはどうしても時間もかかってしまうし「最短で1発大きい花火を上げたいな」って思ったんですよね。
それで1度プロに聞いてみようっていうことで、「AI」ってググったら出てきた大手企業がヒットして、そこの社員の人と名古屋でご飯食べた時に、みんなでやろうかっていうので、3人でプロジェクトをスタートして。その企業のつながりで、AIのエンジニアさんを紹介してもらったりとか、色々なつながりができてきてっていう感じです。
── 人を手繰り寄せていったのですね。
人に恵まれたっていう、本当にそれだけです。あんまり、自分で何もやってないんですけど。
── その人は、なんで佐藤先生たちに興味を持ってくれたのですか?
部活っぽかったんだと思いますよ(笑)。中学2年生みたいなノリでしゃべっていたんです。
「こういうことができたら面白いですよね」とか。いわゆるビジネスでもないし、あんまり真面目な感じでもないし、でも、ちょっと夢を語るというか「骨折とかAIで診断できたら、すごく色んな人が喜ぶと思うんですよね」とか、採算度外視で。そういうモチベだったり、ワンパクなところを多分良く思ってくれて「会社として支援することはまだできないけれど、個人的にボランティアに近い形で一緒にやらせてください」って形で入ってくれて。
彼はもともとプロダクトマネージャーのバックグラウンドがあるので、すごく良い方向に導いてくれるんですよね。もう彼とは2年半、毎週土曜日、30分から1時間ぐらい意見交換してる仲になってるんですけど、やっぱりその人との出会いがすごい大きかったなと思います。
── その人はプロダクトマネージャー的な動きをしてくれたのですね。実際に、手を動かすのはどうしていたのですか?
その時は、AIベンダーさんと契約させていただいて、業務委託費を僕らで折半して払ってお願いした感じでしたね。
── そこは1回外注したのですね。
そうですね、あんまり迷いはなかったですね。お金をどうするかっていう話で、大体240万円くらい払うっていう話になったんですよね。「240万か、、、結構高いな」と思ったんですが。
当時、クラウドファンディングとかでメーカーさんに寄付を募ったり、病院長に話をしたりしても、当たり前ですが、なかなか実績がないと乗ってもらえない。その時、同期が「これはもう、腹くくって自分らで出して1歩前に進まないと何も進まないから」って。それで勢いで120万円ずつ出してやろうみたいな感じで。
でも、奥さんに言ってなかったんで、今もずっと言われます。「あの時のお金返せー」みたいな(笑)。
── 僕の経験であったのが、外注するとこっちが言ったことをそのままやるだけで、いわゆるプロダクトマネジャーみたいな動きをする人がいないと、医師は発注の仕方がやっぱり下手だから、全然欲しいものが出てこない。で、直してくれと言ったらまた追加でお金かかるとかありがちだと思うんですけど、そのあたりは上手く進みましたか?
AIに関しては、僕らは全然知識も経験もなかったので、完全に信頼しきっていました。逆に、彼らからすると、レントゲンの見方さえわからない。「大腿骨ここ?」ぐらいのレベルだったので。お互いが分からなさすぎるからこそ、お互いを信頼しきって、毎週ミーティングして、齟齬がないようにコミュニケーションをかなり密に取っていました。だからコミュニケーションエラーは、その時はあんまりなかったですね。
── 素晴らしい。Webサービスを作るための発注ではなく、レントゲン画像を使った何かを作るだったから、向こうもよくわからないし、佐藤先生たちの言うことも伝わったんですね。
そうですね、良い出会いでした。
── それでプロダクトとして1つの形になったのですか?
そうです。半年ぐらいで、大腿骨の骨折を診断するAIができあがりました。自分も研修医の時にすごい心細くて骨折診断のAIがあればなって思っていましたが、そういう研修医の先生が大腿骨の骨折の診断をする時にAIの補助があれば診断率が上がる、という論文になりました。
── 論文にしたことだけでもすごいんですが、そこでビジネスにしようという考えはなかったのですか?
ありましたし、今もやっぱり思っていますけど。でも、段々その頃に気づき始めたのが、いわゆる診断支援だったりとか、見逃し防止といったところのAIツールは、現場の医師である僕らにとってはすごく有益なツールなのですが、ビジネスの根底である、お金を出すステークホルダー、例えば院長や理事長などは、そんなにお金を出したがらない。
骨折診断AIも現場のドクターも嬉しいし、研修医も嬉しいが、なかなか導入につながりにくいだろうな、と感じ始めた時に「ああ、これで食っていくのは無理だろうな」って早々に諦めたというか。
ただ海外、特にアメリカでは骨折診断AIでいくつかのプロダクトが出てるのを見ると、遠い未来ではなく、比較的近い未来でおそらくプロダクトは出るんだと思います。ただそれはもう自分じゃなくてもいいかなと。
── なるほど。作ったプロダクトは以前いた病院などで活躍しているのですか?
そうですね。今蒲郡市の病院のカルテの中に入っていて、研修医の先生が診断する時にはAIが使えるようにはなっています。一応前向き研究という形にはしてるので、未証認医療機器ではあるんですけど。
自分たちがいつも触ってるカルテでAIが動くのは、やっぱり感動しますね。作ったんだなっていう実感が湧きますね。
── ご自身で論文も書いたのですか?
そうですね、もちろんだいぶご指導はいただきましたけど。
── その時は、まだ会社とか法人にしようとは考えていなかったのですか?
考えていなかったですね。1度AIができたので、色んなメーカーさんに応援いただいて研究寄付金などが集まって、研究するようになってきたんですけど、そこから次のAIプロダクトをやっぱり世の中に出したいなと思い始めて。
ただ、医療機器は結構ハードル高いと思っていたので、医療機器にならない形でAIを社会実装できないかなと、色々アイデアを考えてました。その中で、整形外科医は手術をすごくたくさんやりますが、コミュニケーションがすごく煩雑だったのと、術前計画に時間が結構かかるし、できない時もあったので、そこをもっと簡便化できたらいいのかなと思って。
それで年齢・性別・身長からインプラントのサイズを予測するAIを作って、それをインプラントのオーダーシステムに乗せれば一石二鳥というアイデアを思いつきました。インプラントのオーダーシステム作ろうと。そうなるとメーカーさんやディーラーさんと話し合わなければいけないので、当時はNPO組織の一部だったんですけど、それではいけないと、会社を立ち上げました。
── 登場人物が増えましたね。さっきの大腿骨の骨折診断をAIで補助するものは医師が便利で使うが、誰もお金払ってくれないという問題がありましたが、2つ目のプロダクトはメーカーさんやディーラーさんが出てきたり、医師がたくさん使ってくれれば、確かにお金動きそうですが、結末はどうなったのですか?
これは難しいところですね。すごく良い学びがありました。ただ大枠で言うと、失敗だったというところですね。
理由としては多分2つで、まず夢を追い求めすぎたのが1つですね。もう1つは、きちんと収益が上がるものを考えなきゃいけないなというか、いわゆるコスト意識だけではなかなかビジネスって成り立たないと感じました。時代も関係すると思いますが。
── 夢を追いすぎたというのは、年齢と性別とか身長だけではインプラントサイズが決まらないということですか?
いえ、それはできます。AI自体はできたんですけれど、結局医療と安全のバランスがやっぱり大事になってきて、ある程度サイズを絞ったところで、オプションサイズを減らそうとかは安全面の話に入るので、どんなにAIがサイズをバシッと当てたとしても、結局介入する量があんまり変わらないので、コストダウンにつながらないという話になりました。
今までのように医師が電話や対面でディーラーさんなどに話をするよりもアプリは確かに便利だと評価されるけど、行動変容させることはやっぱり難しくて。思い描いている世界に向かっていくことはやっぱ難しいなと思うし、世の中にはメーカーさん、ディーラーさんがたくさんいて、それぞれがWinになるような方向性を目指すには、結構政治的なことも絡むんだと学びました。
── 医師にとっては術前計画を立てる時の効率性は上がるけど、メーカーさんやディーラーさんのコストカットにはならず、効率的になったわけでもないということですね。
はい、もちろん最初は多分忖度というか医師がやるから手伝ってくれた部分もあったと思うんですけど、全体的にはメーカーさんもディーラーさんも協力してくれました。僕らなりにも、工場見学させていただいたり、ドキュメンタリー撮ったりして、構造が分かれば分かるほど、物流に関する問題は本当に沼のようになっていて、、、だから今までずっと誰も手をつけてないんだということが、段々分かったんです。
だから、これはブルーオーシャンじゃなくて、難しすぎるから解決できてないんだなっていう。そこにあえて踏み込むのは、確かにベンチャーだからチャレンジしてもいいんだけれども、それ以上に見返りがあるかどうかってのは、きちんと見極めないといけないことを途中ぐらいに気付きました。
── なるほど。その時の法人には、さっきお話に出てきた同期のドクターもいたのか、佐藤先生が個人でされていたのか、どちらですか?
その時は5人ぐらいですかね。ただみんな部活みたいなノリでやっていたメンバーで、全然給料もらっていないです。
── 医師が起業するメリットですね。本業でしっかりと収入があるから。
その時の一緒にやってたメンバーの病院が違ったので、それぞれでインプラントのオーダーシステムを実際に使ってみてくれたり、フィードバックしてくれたりとか。かなり協力してくれて助けてもらったっていう感じはありましたね。
── 実際に使ってくれる仲間がいて素晴らしいじゃないですか。そのまま改善を重ねて突き進んでも良いと思いましたが、先生はスパっとそこでピボットしたんですか?
段々自分が認めなきゃいけないというか、、、現実と向き合わなきゃいけない時が来るんですね。インプラントのオーダーシステムを作って、自分の子どものように可愛いわけですね。だから、それが世の中で認められない、使われないという事実に段々気づくわけだけど、気づかないようにする期間が大体半年〜1年くらいあるわけです。
これは多分無理だな、でももう少し粘ってみようみたいな、いわゆる損切りできない感じでずっとやってて、でもやっぱりどこかでケジメをつけないといけない。でも、実際ディーラーさんやメーカーさんが応援してくれてるので、兼ね合いを見つけながら、一応クローズするという形を決めました。
── すごいですね。その時に法人も畳んで「普通の医師に戻ります」くらいの引き際だったんですか?
実は、1年ぐらいやった時に、今の胸部X線写真の話も出てきていたのです。去年、他の整形のAIの研究されてる先生方に相談して「一緒にデータ集めてあげるから、やってみようか」みたいな感じですごく応援していただいて。アイデアベースで、AIもできてなかったんですけど、やっていくうちに実現可能性も上がっていって「これは失敗せずにできそうだ」という実感が出てきたんです。
1番覚悟が生まれたのは、やっぱり投資家の人がお金出すって言ってくれた瞬間で。その瞬間、世の中で使われる価値がついたと思ったんです。自己満足に作ったインプランドオーダーシステムではなくて、ちゃんとお金を出してまで応援してくれたりとか、お金を出して買ってくれる人がいるなった時に、これは多分自己満足のものじゃなくて、ちゃんと世の中に受け入れられるものなんだ。だったら、これをちゃんと刷新して、世の中に出そうと。そこで覚悟を決めた感じですね。
その時にキャリアをちょっと悩んで、起業家の道に決めた感じです。
── AIの研究をしているドクターに相談して、データ集めるのを手伝ってもらってというのは、まだ医師の範疇から出ていないと思うんですけど、そこから投資家に話に聞きいくのは普通のドクターから見ると飛躍していますよね(笑)。もともと関係性があったんですか?
今、名古屋大学の医局にいるんですが、そこのつながりでピッチイベントで喋った時に「これはいけるよ」という話をいただきました。そこから少しずつベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などと話をするようになっていった感じです。
── なるほど。大学発スタートアップとか、大学とかでピッチコンテストとかを主催するような時流があって、そこに出たらみたいな話があって、出たらつながれたっていうことですね。
そうですね。いわゆる研究レベルのものから、ちゃんと社会でバリバリやっているビジネスマンの方たちに喋った時の反応が、自分が思った以上に良かったということですね。
── パッと聞いても「なるほど!」と思いますし、健診で絶対レントゲン撮るので、アイデアとして素晴らしいですもんね!どのように思いついたんですか?
それこそ、さっきの話に戻るかもしれないですが、ビジネスにする時、やっぱりお金になることはすごく大事です。さっきの骨折診断とかの経験から、AI医療機器を出す時には治療につなげないと儲からないと思ったんですね。
そうなると、やっぱり病気を見つけるような形になってくる。整形外科の中で市場が大きいところは骨粗しょう症やリウマチ。それで骨粗しょう症のマーケットを狙っていこうと思うと、やっぱりまず診断のとこで入りたいなと。
骨折診断のAIを作っていたので、椎体骨折さえ見つかれば、もう骨密度を測らなくても治療介入できますよね。そうすると製薬企業にも絡めるなと思って。それならレントゲンで椎体骨折を見つければいいやと思ったんですが、背中のレントゲン撮って椎体骨折見つけるのはちょっと普通すぎますよね。そんな誰でもできることではなくて、もっと一般的に誰でもどこでも撮るような画像、撮影頻度が高いもので椎体骨折を見つけたいと思って、最初、胸部のX線写真から椎体骨折を見つけることを想定したのです。ただ、AI結果を見ると、椎体骨折を見ているパターンだけでなく、実際は肋骨や色んなところを見てたりとかして、不思議に思っていました。それが椎体骨折ではなく、骨密度を見てるんじゃないかなと途中で段々気づき始めたんです。実際に骨密度を確かに測ってるのが分かってきて、これいけるんじゃないかっていうとこで決めました。
── AIが教えてくれたんですね。AI系の研究をしたことがないから分かりませんが、途中経過を見るのですか?
はい、いわゆるヒートマップと言って、グラデーションになって、AIがどこを見てるかってのが分かってくるので。
── 骨粗しょう症関連の薬を持ってるような製薬企業は興味を持つでしょうね。病院に来て診断されて薬を使い始める前に、健診レベルで骨粗しょう症とかの可能性を指摘されるのは、疾患啓発的なところでも、文脈として今の時代に合っていますね。
そうですね。やっぱり簡便に骨粗しょう症の検査ができるのはすごく大事だなと思っていて。これも結構実体験ベースなんですけど、もともと骨折治療がすごい好きで、オペもガンガンガンガンしていて、患者さんも喜んでくれていました。
でも結構患者さんに相対する時に心が痛むわけですよね。この後どうなるんですかという質問に、要介護になる可能性もありますよ、歩けなくなる可能性もありますよって、喋れば喋るほど自分の中では心がすり減ってるところがやっぱりあって。そもそもやっぱり骨粗しょう症って治療すべきだよなって、ずっと思っていたんですよね。
でも、行動変容は難しい。啓発活動で、その人たちの関心を骨粗しょう症の方に向かわせて、健診を受けてもらうっていうのは、すごく難しいと思うんですよ。それなら行動変容なく、一般市民の方が別の目的でなんか撮っているようなもの、レントゲンだったりとか、心電図とか、採血とかなんでもいいんです。必ず撮るもので骨粗しょう症が診断できれば、彼らは追加の、被爆も検査も時間もいらない。
実施してる側も特別な検査機器もいらないのでみんなWinで、かつ、骨粗しょう症にぶつかるような世界観っていうのができるなっていうのを、途中で思ったです。
── 投資家が入る時に事業にコミットすると決めましたが、そこは投資家から言われたのか、佐藤先生自身がそうしなきゃダメだなと医師のキャリアを諦めたというか、中断したのか、どちらなんですか?
自分で決めた感じですね。実際、投資家とそのガチガチに話し始めたのは、医師のキャリアを中断した後の2022年5月以降になってくるので。
── 自分の意思でフルコミットするんだと。
僕自身が2年間、2足の草鞋でやってて結構しんどかったんですよ。日中ずっと病院に行って、家に帰っても会社のことをずっとやって。で、子どもが生まれて、家の時間も必要になってくる。もう全然時間なくて、段々苦しくなってきて。
欲張りに何でもやりたい、だけど時間は限られているんで、、、指の間から砂が落ちていく感覚がすごいあったんですよ。いろんなやらなきゃいけないことがすごくたくさんあるのに、どんどんどんどん砂が落ちていく――。そうなった時に、これはやっぱり何かを選ばなきゃいけない、欲張りになりすぎてもいけないなって。そういう思いがあって、いろんな人に迷惑かけちゃいましたけど、医師のキャリアを中断する決断をしたって感じですね。
── チャンスだったのですね。
そうですね、もうこれをやらずして死ねないんだというか、絶対後悔するなと思って。全てのタイミングがあっていたんだと思うんですよ。今の自分のタイミングしかできないし、アイデアもあって、AIができあがっていて、応援してくれる人がいて、こんな良いメンバーが集まっていて。「やらない人がいるのか?やるしかないよね」と。そうなったら、やっぱりもう中途半端になってもいけないということで、あんまり迷いはなかったです。やるしかないという感じで。
── 仲間はどうやって集めたんですか?
それも完全につながりですね。さっき話した大手企業の方から始まって、AIのエンジニアもそうですし、薬事関連をやっていただいてる方は、確かピッチイベントで見ていただいて、ジョインしていただいたりとか。今は一応、業務委託で何人か入っていただいてるんですけど、それも人のつながりですね。
── 今何人ぐらい業務委託の方がいるのですか?
コアメンバーが3人で業務委託が2人っていう感じです。
── チームですね。エクイティファイナンスって最初難しくて分からないし、失敗すると後戻りできないので、自分は結構それに気を遣いました。佐藤先生は迷いなくどんどん進めてる印象ありますが、そこら辺はどうしたのですか?
めっちゃ難しいと思います。お金を出したいと言ってる人を断るのって、すごく難しいと思いましたね。やっぱりコミュニケーションが、お金に絡むところなんで大事だなと実体験として思いますね。
── ソフトバンク系からの出資で資金調達されていますが、そことの出会いは?
DeepEyeVisionという会社の代表、髙橋秀徳先生に紹介してもらいました。MEDISOという厚生労働省のベンチャーのサポートプログラムがあって、そこで話をした時に、当時私が勤めていたJCHO東京新宿メディカルセンターに、DeepEyeVisionの髙橋さんも勤務されていますよ、と聞いて。翌週ぐらいに名刺持って眼科の部屋に行っていって話をしたら、すぐ色々教えていただいて、資金調達を考えてるっていう時に紹介してくださったという感じです。
── そのつながりは大きいですね。投資先から紹介されたら、向こうも「これは」とやっぱり思いますよね。
そうですね。基本誰かの紹介で、どんどんお願いをしていったっていう感じですね。やっぱりそっちの方が相手側も信頼できると思う。
── 間違いないですね。その前のラウンドにはエンジェル投資家さんもいたのですか。
いなかったですね。VCさんだけですね。
── いろんなVCさん回りした中で感じることありますか?医療には疎い方もいると思いますし、逆にAI×医療だと引き合いが強いなーとか、何か感触はありましたか?
2022年8月に調達していて、4月〜7月で多分20〜30社ぐらいのVC回ったんですね。その中ですごく成長できたなと思っていて。
そこまでいわゆる臨床はやっている、AIも分かってきた、ただ、ビジネスのことは全く分かっていないわけです。素人がビジネスのプロに対して壁打ちしまくるわけです。毎週毎週、2〜3社のVCさんに喋って突っ込まれて返答するたびに、こういうことを見られてるんだなと分かってきて、段々ブラッシュアップされていきました。
4月にプレゼンした内容と、6月〜7月にプレゼンした内容とでは、全然レベルが変わってると思うんですよね。それぐらい毎週VCさんと喋るたびに、成長させてもらって、あの時期はすごく良かったなと思います。
── 素晴らしい。それは、佐藤先生がきっとアンラーンと起業家としてラーニングを繰り返してるからですね。
VCさんがお忙しい中で時間を使ってくださって、すごく親身に指導してくれたので、そのおかげだと思います。
── 医療機器を目指すことになると、そういう感じのトラクションをつけたり、ベンチマークでラウンドも進んでいくのですか?
そうですね。マイルストーンとしては、医療機器を販売するだったりとか、契約する病院をいくつにするとか、そういう形になってくるかなと思います。
── 先生の世界観だと、将来どのような感じになるのですか?胸部レントゲン画像でAIを使って骨粗しょう症診断ができると、どんな未来が期待できますか?
整形外科のオペがなくなっちゃうかもしれないですね(笑)。でも本当に、1人でも骨折は減った方がいいと思います。あとはニーズがあるなら海外にも輸出したいですね。
── 海外でそういうことやっている人はいませんか?
今のところは競合はなさそうです。
── 日本は健診を受けていそうなイメージありますが、海外はそんなに受けていないのでしょうか?
最近聞いたのですが、むしろ海外の方が多いらしいですね。海外の方が、がん検診の検診率は高いという話を聞きました。海外でも欧米と途上国とではやっぱり違って、東南アジアはもちろん健診の文化がないですけど、欧米は健診率高いみたいです。
── 発展性がありますね!ドクターが、佐藤先生に何か協力できることや、佐藤先生からドクターの人に何かメッセージ、もしくは要望とかあれば教えてください。
もしAIの研究をお考えの方は、お金とかも全然関係なく、おこがましいですが、相談に乗れます。仲間が増えることはすごい良いことだと思うし、やっぱり裾野が広がるってすごい良いことだと思うので、少しでもご興味がある方はご連絡いただけると、僕らとしても学びがあると思いますので。
── 今回はゼロイチドクターで胸部レントゲンから骨密度を計測するAI医療機器を開発されている、iSurgery株式会社の佐藤洋一先生をお招きして、お話を聞きました。佐藤先生、ありがとうございました!
はい、ありがとうございました。